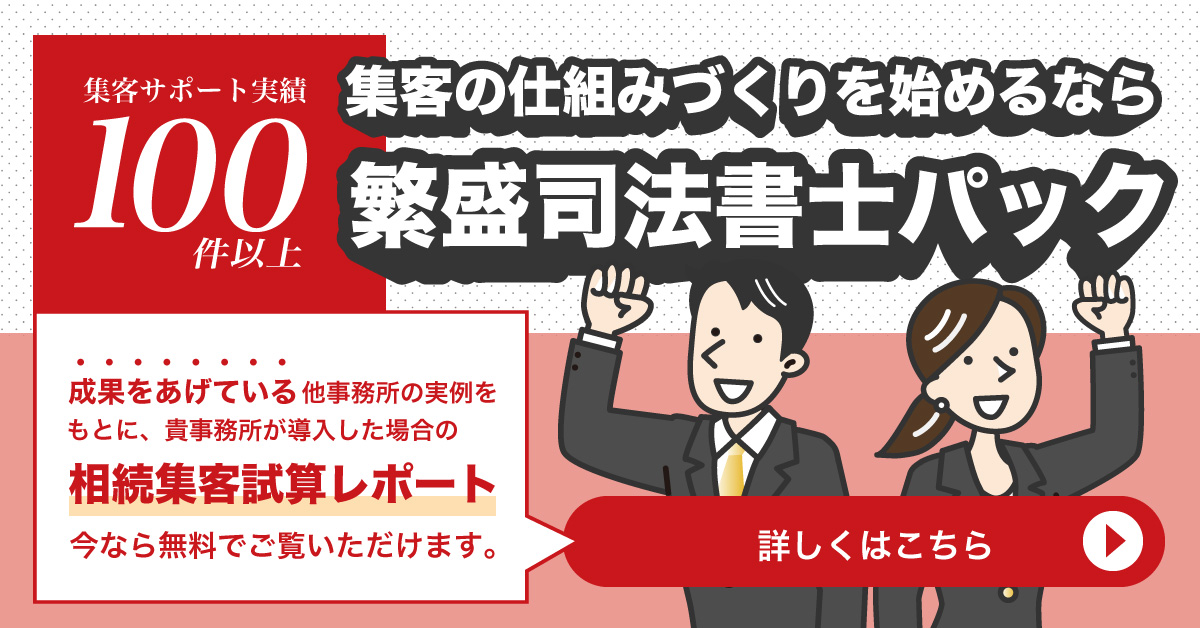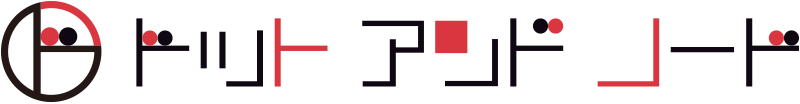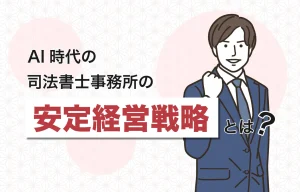司法書士は名刺で差をつけよう!載せるべき事柄やデザイン例を紹介
司法書士という職業は専門性が高い一方で、士業以外の人からすると、どのような業務をしているのかが分かりにくいです。
だからこそ、初対面で渡す名刺には自分の専門分野や強みなどを記載して、相手から信頼を得られるようにデザインしたいものです。
しかし、初めて自分で名刺を作成するとなると、途端に「何を記載すればいいのか」「どういうデザインにするべきか」「どこへ印刷を発注するべきか」と悩んでしまうでしょう。
この記事では、司法書士が名刺に載せるべき事柄やおすすめの発注先などについて解説していきます。
司法書士が名刺を作成すべき理由

そもそも、なぜ名刺を作成するべきなのでしょうか?
司法書士が名刺を作成する意味やメリットは、次の通りです。
- 自分が何者かを明示するため
- 得意分野や業務内容をアピールできるから
- 他の士業・司法書士と差別化を図れるから
ここからは、司法書士が名刺を作成すべき理由について解説します。
自分が何者かを明示するため
相手から「信頼できる」「安心して任せられる」と思ってもらえないと、仕事につながりません。
自分が何者かを明示して、不信感を取り除いて安心感を覚えてもらうことが大切です。
「自分の名前は何か」「どこに事務所を構えているか」など、自己開示して信頼してもらうために名刺を作成します。
得意分野や業務内容をアピールできるから
司法書士といっても、不動産登記や企業法務、認定司法書士が対応する簡易裁判所での訴訟代理、成年後見業務など、業務内容は多岐にわたります。
自分の得意分野や対応できる業務内容をアピールすれば、その分野で困ったときに依頼してもらいやすくなります。
「登記の仕方が分からないので〇〇さんに相談しよう」「成年後見人に選任されたから××さんを頼ろう」というように、特定の悩みが生まれたときに自分を想起してくれるでしょう。
他の士業・司法書士と差別化を図れるから
士業に馴染みがない職種に就いている人からすると、士業ごとの業務内容についてイメージしづらいという場合が少なくありません。
登記の手続き代理(代理申請)や登記相談など、司法書士にしか認められていない業務を名刺に載せれば、弁護士や公認会計士など他の士業と区別してもらいやすくなります。
たとえば、登記の手続き代理(代理申請)や登記相談など、司法書士法第3条に基づき司法書士のみが対応できる業務を名刺に記載すれば、弁護士や公認会計士など他の士業と明確に区別してもらいやすくなるでしょう。
また、「相続手続き累計〇〇件」「企業法務を××年担当」など実績や経歴も載せると、他の司法書士と差別化を図れるでしょう。
司法書士が名刺に載せるべき事柄

司法書士が名刺を作成する際、具体的にどのような内容を記載すればよいのでしょうか?
名刺に載せる事柄は、以下の通りです。
- 基本情報
- 保有資格や所属団体
- 対応できる業務内容
- QRコード
ここからは、司法書士が名刺を作るときに必ず載せるべき内容を見ていきましょう。
基本情報
司法書士が基本情報として名刺に最低限載せるべき内容は、以下の通りです。
- 氏名
- 事務所名
- 役職
- 連絡先(電話番号・FAX・メールアドレス)
- 事務所の住所
- ウェブサイトのURL
- 登録番号
なお、登録番号を記載することで、相談者が日本司法書士会連合会の登録情報と照らし合わせて確認できるため、客観的な信頼性の裏付けになります。
保有資格や所属団体
司法書士の資格はもちろん、他に保有している資格があれば名刺に併記しましょう。
〇〇(地名)司法書士会など所属している団体があれば、信頼につながるので記載してください。
対応できる業務内容
自分が対応できる業務内容を名刺に記載しましょう。
「相続」「不動産登記」「法人登記」など具体的な業務内容を記載すると、相手がいざ困ったときに相談してもらいやすくなります。
QRコード
自身や事務所のウェブサイト・ブログ・SNSなどへ簡単に誘導できるため、QRコードも載せましょう。
QRコードは無料のWebサービスを利用すれば簡単に作成可能です。
たとえば「QRコード 無料作成」などで検索し、自身のウェブサイトのURLを入力すれば、すぐに画像形式で生成できます。
司法書士におすすめの名刺のデザイン例

司法書士が名刺に載せるべき事柄が分かっても、デザインで迷ってしまう方は少なくないでしょう。
司法書士におすすめの名刺のデザイン例として、以下の2パターンを取り上げます。
- 基本的な名刺デザイン例
- 業務分野別の名刺デザイン例
ここからは、名刺のデザイン例を具体的に紹介します。
基本的な名刺デザイン例
基本的な名刺デザイン例は、以下の表の通りです。
色やフォントなどに悩む場合は、こちらの内容を参考にしてみてください。
| 項目 |
内容 |
|---|---|
| 色 | 紺・グレー・茶色などの落ち着いた色調がおすすめ。 |
| 図柄 | できるだけシンプルに仕上げる。
ポップで派手な装飾は避ける。 |
| フォント | 明朝体またはゴシック体がおすすめ。
一般的で読みやすいものを選ぶ。 |
| 事務所のロゴ | ロゴがあれば掲載する。 |
| 用紙の素材 | 特に規定はないが、厚手の上質紙なら重厚感や高級感を演出できる。 |
| 加工 | マットコート(しっとり系)や光沢コート(つるつる系)などがある。
箔押し(ピカピカする部分)やエンボス(文字が浮き出る)などの特殊加工は、高級感や存在感を演出できる。 |
| サイズ | 日本での一般的な名刺サイズは、55mm×91mm。
カードケースや財布に収納しやすいサイズなのでおすすめ。 |
| 縦書き・横書き | 縦書きは真面目さ・誠実さ・伝統的な雰囲気を演出できる。
横書きは情報量が多くても読みやすく、デザインの自由度が高い。 |
業務分野別の名刺デザイン例
業務分野別の名刺デザイン例は、以下の表の通りです。
自身の業務分野を強調したい方、名刺から得られる印象を大切にしたい方は、参考にしてみましょう。
| 項目 |
内容 |
|---|---|
| 不動産登記 | 家・建物のモチーフ、落ち着いた色調 |
| 商業登記・企業法務 | ビジネス感を重視、シャープなデザイン |
| 相続・成年後見業務 | 温かみのある色使い、家族をイメージ |
| 債務整理 | 安心感を与える優しいトーン |
司法書士が名刺作成するときの発注先

せっかく名刺のデザインイメージが固まっても、どこでどのように印刷してもらえばいいのか分からない方は多いでしょう。
司法書士が名刺作成するときの発注先は、次の通りです。
- オンライン名刺作成サービス
- 印刷業者・デザイン会社
以下では、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
オンライン名刺作成サービス
オンライン名刺作成サービスでは、用意された多数のテンプレートから任意のものを選んで、自分で名刺をデザインして発注します。
テンプレートを利用するので、発注費用が安価でありながら、大量印刷に素早く対応してもらえるのがメリットです。
司法書士として独立したばかりで経費を多くかけたくない方や、コスト・スピードを重視している方におすすめです。
ただし、1からオリジナリティのあるデザインの名刺を作りたい方や、自分で見やすいデザインになっているか判断がつかない方には向いていません。
印刷業者・デザイン会社
名刺で他のビジネスパーソンと差別化したい場合や、完全オリジナルで凝ったデザインの名刺を作成したい場合は、印刷業者やデザイン会社への発注がおすすめです。
デザイナーが見やすいように丁寧にデザインを考えてくれ、一風変わった用紙を確保しているので、自分の要望に合う逸品に仕上がります。
図柄やフォントにこだわりたい方や、一般的な厚紙ではつまらないと思う方は、印刷業者やデザイン会社に名刺作成を依頼しましょう。
ただし、プロのデザイナーによるデザイン費や高級な用紙代などがかかるので、費用は高めに設定されていることが多いです。
司法書士が名刺を活かすタイミングとマナー

司法書士が名刺を渡すのは、次のようなタイミングです。
- 初めて会う相談者にあいさつするとき
- 税理士や行政書士など、他の士業と連携するとき
- セミナーや交流会で自己紹介するとき
名刺は自己開示に必要なアイテムです。
したがって、基本的には初めて会う方、全員に渡すことになります。
また、「立場が下の方(訪問した側)から上の方へ渡す」「商談終了後にしまう」など、名刺に関するマナーも守りましょう。
司法書士の名刺の保管方法と持ち歩き方

名刺は司法書士としての第一印象を決定づける重要な営業ツールです。
そのため、見た目だけでなく渡す瞬間までの取り扱いにも気を配る必要があります。
仮に、くしゃくしゃにヨレた名刺を差し出した場合、相手に「この人はだらしないかも」とネガティブに思われてしまう恐れがあります。
そのため、以下の点に注意して、司法書士は名刺を大切に扱わなければなりません。
- 名刺は専用の名刺入れに入れる
- カバンの中でバラバラにならないように、名刺入れの口をしっかり留めて持ち運ぶ
- 相手からもらった名刺も名刺入れで一緒に管理し、折ったり破いたりしないように注意する
名刺の管理が雑だと、相手から仕事も雑に対応しているように見られます。
名刺は「配るだけで終わり」ではなく、「渡す直前までの状態」も含めて信頼を伝えるツールです。
司法書士が名刺を作り替えるべきタイミング

司法書士の名刺は、一度作って終わりではありません。
名前や事務所情報などに変更点がなくても、次のような理由で名刺を作り直す必要が出てくることがあります。
- 得意分野が変わった(たとえば、登記から相続に特化した)
- デザインが古くなってきたと感じる
- 登録番号や事務所名が変更された
- 相手から「読みづらい」と言われた
- 紙がすぐヨレるなど、物理的な劣化が気になる
- 新たなターゲットに向けて内容を見直したくなった
名刺の見直しは、「在庫が切れたとき」だけでなく、「仕事の方向性やアピールポイントを変えたいとき」にも積極的に行うべきです。
全く同じデザインのものを機械的に発注するのではなく、定期的に見直して、必要であれば切り替えましょう。
司法書士の名刺作成におけるQ&A

司法書士が名刺作成時に悩みやすいポイントをまとめました。
Q&A形式で取り上げたので、気になる疑問があればチェックしてみましょう。
名刺作成の相場はいくらですか?
名刺作成の相場は、モノクロかつ片面印刷で、100枚で1,000円程度です。
しかし、オンライン名刺作成サービスなら自分でデザインする分、もっと安く発注できます。
サービスを比較して、自分の予算に合うものを選びましょう。
顔写真は載せるべきですか?
名刺に顔写真を載せると、相手に親近感や安心感を与えられ、印象に残りやすいのがメリットです。
ただし、写りが悪いと逆にマイナスな印象を与えるだけでなく、顔写真がSNSなどに無断転載されるなど、個人情報の悪用につながる恐れもあります。
「顔写真は絶対に載せるべき」とも言い切れないので、よく検討してから判断してください。
両面印刷と片面印刷どちらがいいですか?
名刺に事務所のウェブサイト・地図・QRコードなど、多くの情報を載せたいなら両面印刷がおすすめです。
ただし、両面印刷は片面印刷よりも費用が高くなるうえに、裏面のデザインが表面のデザインと調和していないと、全体の印象がちぐはぐになり、見栄えが悪くなります。
「どのような内容を載せたいか」「どこに配置したら見やすくなるか」をよく考え、自分で名刺の構成を描いてから印刷する面を決めましょう。
デジタル名刺って便利ですか?
最近ではスマートフォンで閲覧できる「デジタル名刺」なるサービスが登場しており、デジタル名刺のみ、または紙の名刺と併用している人が増えています。
デジタル名刺を使えば、クレジットカードのような厚さ・大きさの台紙に印刷されたQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、事務所のホームページ・LINE・SNSなどに簡単にアクセスできます。
名刺を切らす心配がなく、環境負荷の軽減にもつながりますが、導入時には初期費用がかかり、紙媒体を重視する相手には不向きな場合もあるため、目的や相手の層に応じて使い分けることが重要です。
司法書士の名刺は「入り口」!web集客業務を丸投げしたいならドットアンドノードへ

今回は、司法書士の名刺について解説しました。
名刺は自己開示に必要不可欠なアイテムであり、作成すれば得意分野や業務内容を簡単にアピールでき、他の士業・司法書士と差別化を図れるようになります。
オンライン名刺作成サービスや印刷業者などに発注して、集客ツールの一部として活用しましょう。
とはいえ、名刺は司法書士として信頼される「入口」に過ぎず、それだけでは集客につながりません。
もし名刺から自分の名を知ってもらい、依頼につなげたいなら、Web集客にも取り組んでみませんか?
弊社ドットアンドノードでは、実際に司法書士が月に20件近い問い合わせを獲得している「繁盛司法書士パック」を提供中です。
初期費用0円でスタートできるので、Web集客に力を入れたいとお考えの司法書士は、遠慮なくお問い合わせください。