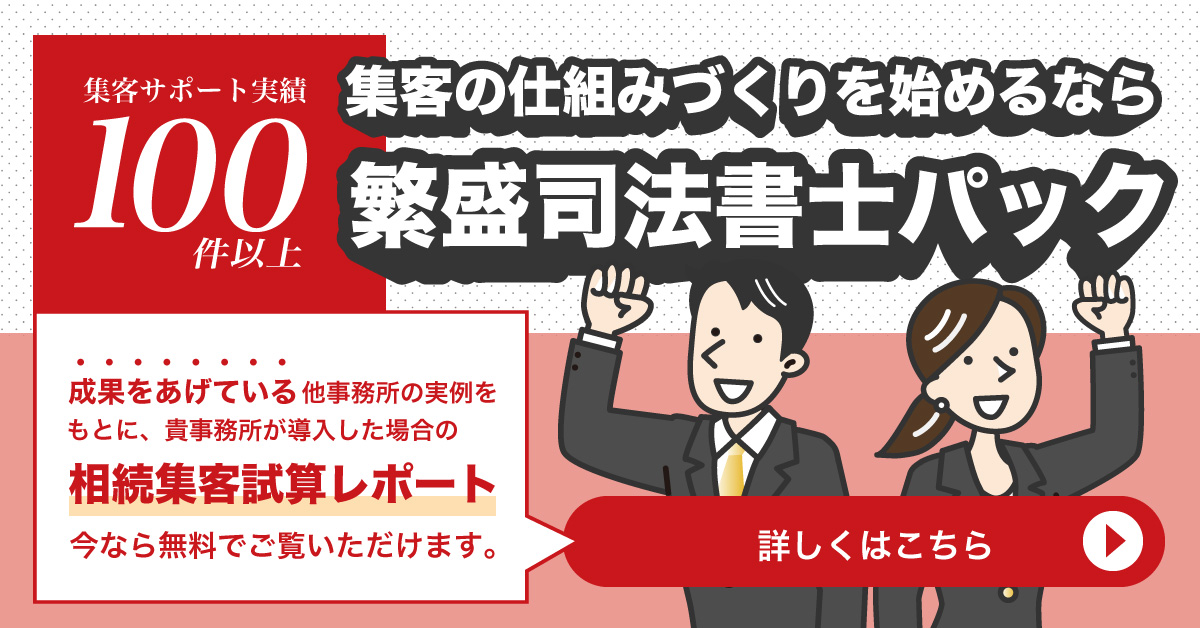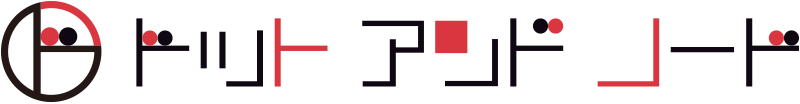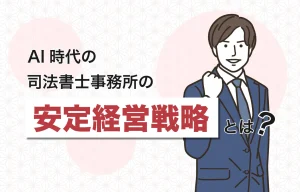開業した司法書士がブログで集客するには?メリットやロードマップを解説
開業したばかりの司法書士にとって、どのように顧客とつながり、信頼を得るかは大きな課題です。
そのような方には、低額で運用できて自分の考え方やスキルなどを伝えられるツールであるブログの運営がおすすめです。
たとえば、開業後にブログで自分の業務内容を丁寧に発信したことで、半年後に月5件以上の問い合わせを獲得できるようになるケースが考えられます。
こうした実例があるからこそ、ブログの活用は有効な手段といえるのです。
しかし「何を書けばいい?」「そもそもどうやって開設するの?」といった不安を抱えている場合も少なくないでしょう。
この記事では、開業直後の司法書士が集客につなげるためのブログの運営方法と、実際に開設するまでのロードマップを分かりやすくご紹介します。
開業した司法書士がブログを運営する重要性とは

司法書士が開業した直後は、どうしても認知度が低いことから、迅速に集客するために1人で簡単に運用できるツールを使う必要があります。
また、インターネットが発展した現在では、相談したい司法書士をネットで探す方が多く、ブログによる情報発信が集客・信頼構築に直結します。
総務省が発表した「令和6年通信利用動向調査」によれば、インターネット利用者のうち「検索サービスを利用する」と回答した割合は全体の79.4%にのぼります。
また、「ホームページやブログの閲覧・書き込み・更新」を行っている層も57.4%**存在しており、司法書士を探す際にネット検索とブログ閲覧を活用する動きは極めて一般的といえるでしょう。
こうした背景からも、司法書士がブログを通じて情報発信を行うことは、集客および信頼構築の観点から意義深いといえます。
開業した司法書士がブログを運営するメリット

開業した司法書士は、どうしてブログを開設するべきなのでしょうか?
司法書士がブログを運営するメリットは、以下の通りです。
- 集客につながりやすい
- 専門性を簡単にアピールできる
- 顧客との信頼関係を構築しやすい
- 安価で運用できる
ここからは、4つのメリットをそれぞれご紹介します。
集客につながりやすい
SEO対策を施した記事を投稿し続ければ、検索エンジンで上位表示しやすくなり、中長期的な読者の流入が期待できます。
たとえば、2024年にFirstpagesageが公開した調査結果「Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025」によると、Google検索結果の1位ページのクリック率は平均39.8%。
SEO対策によって上位表示されることで、ブログへのアクセス数は大きく増加する可能性が高まります。
「コンテンツに読み応えがある」「司法書士の人柄が面白い」などブログのファンになってもらえれば、いざ読者が困ったときに相談してもらいやすくなるでしょう。
専門性を簡単にアピールできる
大量の文書を日々取り扱う司法書士にとって、自分で文章を書くことは苦にならないでしょう。
得意な文章作成スキルを発揮して、「成年後見人とは?」「会社の登記には何が必要?」など司法書士の業務に関する専門的なコンテンツを発信すれば、簡単に自分の専門性をアピールできます。
たとえば、「遺言書の書き方」についてわかりやすく解説した記事を投稿し、「この記事を読んで相談したくなった」という問い合わせにつながるケースも考えられます。
このように専門的な情報発信は実際の集客にも効果的です。
顧客との信頼関係を構築しやすい
ブログで司法書士自身の生活や人柄を伝えれば、読者に親近感を覚えてもらうことにも役立ちます。
読者からの質問に答えたり、個人が特定されない範囲で実例を公開したりすれば、信頼関係を構築しやすいでしょう。
ただし、守秘義務に関する司法書士法第24条に基づき、依頼者の許可なく個人情報を特定できる形での事例紹介はできません。
(秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。引用元:司法書士法 第24条
そのため、内容を一般化するか、本人の同意を得ることが必要です。
安価で運用できる
ブログを開設するには、レンタルサーバーの契約や独自ドメインの取得などが必要ですが、年間で数千円程度しかかかりません(※2025年時点)。
初期費用を含めても、年間1〜2万円ほどで運用可能です。
特別な機材や高額なソフトなどを購入する必要がなく、誰でも安価で運用できるため、ブログは中長期的な集客ツールとして向いています。
【司法書士向け】ブログ開設から運用までのロードマップ
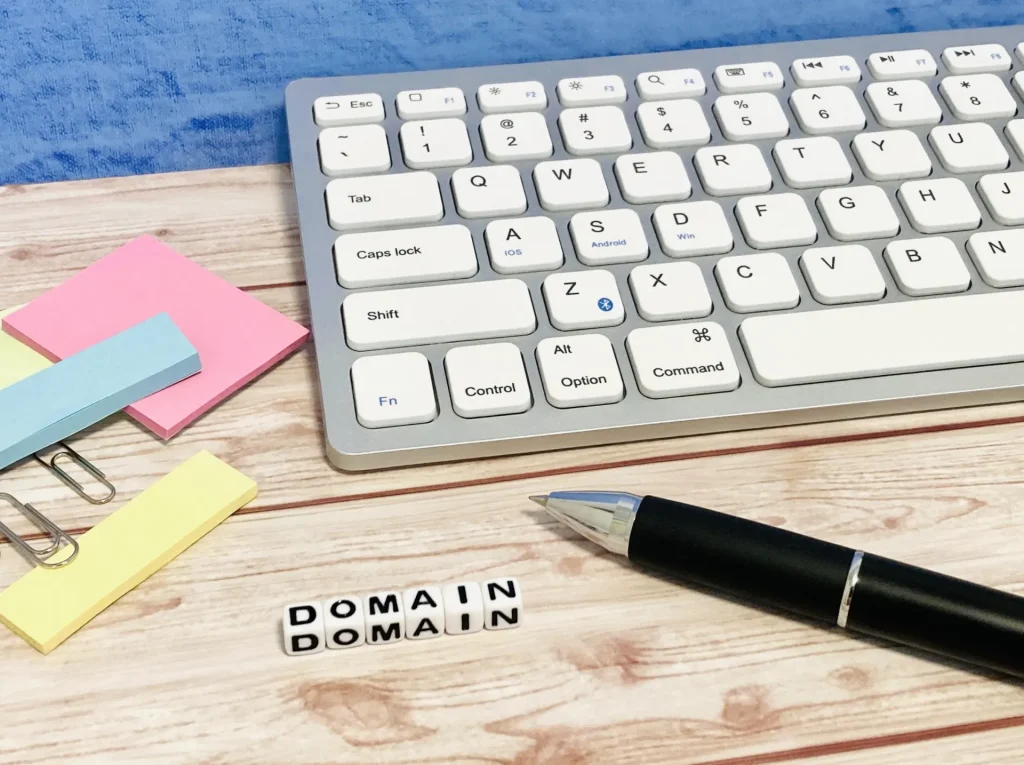
司法書士がブログを運営したい場合、どのようなことに着手すればよいのでしょうか?
ブログの開設から運用までのロードマップは、次の通りです。
- ブログ開設前の準備をする
- 実際に記事を書く
- ブログ開設後の改善に取り組む
ここからは、ロードマップについて具体的に解説します。
ブログ開設前の準備をする
「今まで一度も司法書士に依頼した経験がない個人」「商業登記や債権回収などで悩んでいる事業者」など、ブログで扱うテーマや対象とする読者、掲載する内容のトーンや方針などを明確にします。
本格的に運用するか、無料ブログで気軽に始めるか決める
まずは、「どこまで本格的に運用するか」を自分のスケジュールや予算に応じて考えてみましょう。
将来的に集客ツールとして育てていきたい場合は、独自ドメインを取得し、サーバー契約をしてWordPressなどでブログを構築するのが効果的です。
一方で、「まずは試してみたい」「書けるかどうか様子を見たい」という方は、アメブロやnote、はてなブログなどの無料サービスを使って気軽にスタートしてみてもよいでしょう。
実際に手を動かしてみることで、自分に合った方法が見えてくることもあります。
実際に本格的に運用する場合は、次のような準備が必要になります。
- 【本格的に運用する場合】ドメインを取得する
- 【本格的に運用する場合】サーバー契約する
それぞれについて、順番に説明していきます。
【本格的に運用する場合】ドメインを取得する
本格的にブログを運用する場合は、独自ドメインを取得するのがおすすめです。
ドメインとは「○○.com」「○○.jp」など、ブログのURLとなる住所のようなもの。
独自ドメインを持っていることで、ブログの信頼性が増し、読者からの印象も良くなります。
ドメインは「お名前.com」「ムームードメイン」などのサービスを利用すれば、年額1,000円前後で取得可能。
司法書士名や事務所名を含めたドメインにすれば、ブランドとしての認知にもつながりやすくなります。
たとえば「tanaka-shihou.com」のように事務所名を含んだドメインを使い、名刺やチラシと連動させることで、問い合わせ時に「Webで見て覚えていた」という反応を起こせるケースも考えられます。
【本格的に運用する場合】サーバー契約する
ドメインを取得したら、次はレンタルサーバーの契約です。
サーバーとは、インターネット上にブログのデータ(記事、画像など)を保管しておくクラウド上の倉庫のような存在。
サーバーにアクセスすることで読者がブログを閲覧できる仕組みです。
ドメインとサーバーを紐づけることで、あなたのブログがインターネット上に公開されます。
「ConoHa WING」「さくらのレンタルサーバ」「エックスサーバー」など、初心者向けのプランが充実したサービスを選べば、月額500円〜1,000円程度で始められます。
多くのレンタルサーバーでは、WordPressをボタン一つで簡単にインストールできる機能もあるため安心です。
プロフィール欄を作り、内容を決める
ブログでは、「どんな人が書いているのか」がわかると、匿名の場合よりも読者の信頼感が大きく変わります。
司法書士としての経歴、得意分野、事務所の所在地、趣味や人柄が伝わる情報などを盛り込み、安心感を与えるプロフィール欄を用意しましょう。
プロフィールは、記事ページのサイドバーや「運営者情報」などの固定ページに掲載することがおすすめ。
写真付きで紹介すると、より親しみを持ってもらいやすくなります。
また、Googleの検索評価基準である「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点からも、プロフィール欄の設置は有利に働くとされています。
とくに司法書士のような専門職は、誰が書いているのかを明示することで信頼度が向上するでしょう。
免責事項ページを設置し、情報提供の範囲と責任の所在を明確にする
司法書士がブログを運営する場合、読者が記事内容を誤解して損害を受けた場合に備える必要があります。
「本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断はご自身でお願いします」「当方は責任を負いかねます」などと記載して責任を明確にし、法的トラブルを避けるための免責事項ページを作成してください。
たとえば、ブログ記事で紹介した手続きの手順を読者が誤解して実行し、不利益を被った場合、「内容を鵜呑みにしたことによる損害」について責任を問われるケースもあります。
そうしたリスクを避けるためにも、免責事項の設置は欠かせません。
WordPressでは「投稿」ではなく「固定ページ」で作り、フッターやメニューに常時リンクを設置します。
書き方に迷う場合は「司法書士 ブログ 免責事項 テンプレート」などで検索すると、雛形が見つかるので参考にしてみてください。
実際に記事を書く
実際に司法書士という職業や業務内容、事務所などについての記事を書きましょう。
たとえば「なぜ大手事務所を辞めて独立したのか」「開業初日にやったこと」「顧客ゼロから初受任までの道のり」など、開業初期のリアルな体験をテーマにした記事は、読者の共感を得やすく、おすすめです。
ブログ運営に余裕が出てきたら、以下のポイントも意識してみましょう。
- お知らせ欄を設置して最新情報を発信できるようにする
- SEO対策を意識する
- ブログ記事から問い合わせできるように導線設計をする
ここからは、ブログ記事以外で取り組むべき事柄について解説します。
お知らせ欄を設置して最新情報を発信できるようにする
臨時休業・イベント告知・セミナーの満枠情報などを、普段投稿している記事とは別に「お知らせ欄」で発信すると、ブログが稼働中である印象を与えられて信頼感につながります。
「この事務所は今もちゃんと活動している」といった印象を持ってもらいやすくなるため、定期的なお知らせは信頼感を醸成するのです。
また、ブログが最新の情報で更新されていると、読者が「ここに相談しても大丈夫そう」と思いやすくなります。
書き方は「○月○日〜○日は臨時休業します」「×月×日に開催予定のセミナーは満席になりました」など、短文で問題ありません。
トップページやサイドバー、フッターに常時表示させることで、読者が事務所に関する最新情報を見逃しにくくなり、問い合わせ率の向上につながるケースもあります。
WordPressを使う場合は「ウィジェット機能」で簡単に設置できます。
末尾に「最新のお知らせは、この欄で随時ご案内しています」というように補足を入れると、読者にとって親切です。
【本格的に運用する場合】SEO対策を意識する
「司法書士に関するキーワード」を調査し、ブログに書くべきテーマを決めましょう。
たとえば、「Googleキーワードプランナー」は月間検索数の把握に優れており、「ラッコキーワード」は関連語の広がりを視覚的に確認しやすいツールです。目的に応じて使い分けてみましょう。
「どういうコンテンツを執筆すれば、読者に司法書士について理解してもらえるのか」「読者は何について悩んでいるのか」など、読者の検索意図を深く考察します。
一目で注目を引くタイトルをつけたり、PREP法を用いて簡潔に執筆したりするなど、読者にとって分かりやすい記事になることを目指しましょう。
また、専門知識がないと分かりづらい司法書士に関する専門用語を解説したり、自分が携わった事例を出して読者に具体的にイメージしてもらえるよう心がけてください。
「成年後見制度」など難解な用語には、文中に注釈を入れたり、ページ下部に「用語集」を設けたりすると、読者の離脱を防ぎやすくなります。
吹き出し形式の補足を活用するのも効果的です。
読者が読みやすいように見出しタグを活用したり、決定したキーワードを自然な形で記事内に盛り込んだりするなど、SEOに強いコンテンツ作りを意識しましょう。
さらに、投稿する記事に関する内部リンクや外部リンクを設置すると、SEO対策を強化できるのでおすすめです。
【本格的に運用する場合】ブログ記事から問い合わせできるように導線設計をする
ブログ記事内にCTA(Call To Action)を設置すると、読者からスムーズに問い合わせを受けられるためおすすめです。
CTAでは無料相談・資料請求・メルマガ登録など、どのような種類の行動を促すのかも検討しましょう。
ブログ開設後の改善に取り組む
ブログは「開設して記事を投稿して終わり」ではなく、不備がないか常にチェックして、改善し続けることが大切です。
ブログの弱点を見つけ出して改善するためには、以下のアクションを取りましょう。
- 効果測定をする
- PDCAサイクルを回す
以下では、ブログの改善に取り組むときのポイントを解説します。
効果測定をする
Googleが提供している「Google Analytics」というサービスを使えば、数日から数年単位で読者のアクセス状況を解析できます。
PDCAサイクルを回す
同じくGoogleが提供する「Google Search Console」というサービスでは、投稿した記事の検索順位を調べられます。
検索順位を頻繁にチェックし、順位が低い記事はリライトするなどPDCAサイクルを回しましょう。
たとえば、検索順位が20位以下に落ちている記事は、「タイトルを見直す」「導入文をより具体的に書き直す」「内部リンクを増やす」といったリライト作業を行いましょう。
1ヶ月後に再度効果を測定することが重要です。
司法書士がブログからの集客を最大化するコツ

せっかくブログを開設するからには、読者の増加、ひいては集客につなげたいですよね。
次のコツを踏まえて、司法書士がブログからの集客を最大化しましょう。
- SNSと連携させる
- Googleビジネスプロフィールに登録してMEO対策を施す
- 読者からのリアクションに応え、信頼関係を構築する
ここからは、顧客を獲得するための具体的なポイントを、それぞれ見ていきましょう。
SNSと連携させる
ブログにX(旧Twitter)・Facebook・Instagram・LINE公式アカウントなど、他のSNSのリンクを貼って連携します。
たとえば、XやFacebookでブログ更新を告知すれば、フォロワーを通じて短時間で多くのアクセスを獲得でき、ブログ単体よりも集客スピードが大幅に向上するケースが考えられます。
また、各SNSからブログへ遷移できるリンクも貼って相互に連携させれば、より多くの方にブログへアクセスしてもらえるでしょう。
Googleビジネスプロフィールに登録してMEO対策を施す
MEO(Map Engine Optimization)とは、Googleマップ上での検索結果に上位表示されるように最適化することです。
たとえば「◯◯市 司法書士」で検索したとき、上位に事務所が表示されると、地元住民からの問い合わせが増加する可能性が高まります。
地域密着型を謳っている司法書士であれば、MEO対策にも力を入れることがおすすめです。
Googleマイビジネスと連携させたり、事務所が所在する地域に関する情報を積極的に発信したりしましょう。
読者からのリアクションに応え、信頼関係を構築する
ブログ記事のコメント欄を開放し、読者からの感想・批評・質問などに答え、信頼関係を作ることも重要です。
「読者の意見に誠実に向き合っています」「読者の声を大切にしています」という姿勢が読者に伝われば、集客につながる可能性を高められます。
ただし、コメントには迅速かつ丁寧な対応が必要。
しかも、まれに不適切な投稿がされるリスクもあります。
必要に応じて承認制を導入したり、ガイドラインを設けて運用するのがおすすめです。
開業した司法書士がブログ運営でつまずきやすいポイントと乗り越え方

開業した司法書士の全員が、ブログ運営を常にスムーズに行っている訳ではありません。
ブログ運営でつまずきやすいポイントは、次の通りです。
- 執筆する時間が確保できない
- 投稿する記事のネタがない
- 読者が全然集まらない
- 更新することに疲れてしまった
以下からは、挫折してしまう理由とその乗り越え方を踏まえてご紹介します。
執筆する時間が確保できない
司法書士の業務で忙殺されて、記事を執筆する時間が確保できないと、更新が止まってしまう可能性があります。
更新が長期間にわたり停止していると、読者に「すでに廃業しているのでは?」「依頼してもきちんと向き合ってくれないかもしれない」と思われ、印象が悪くなる恐れがあります。
「バスタイムで湯船に浸かっている15分で9割完成させる」「夜の9〜10時まではブログに時間を割く」など、日々のルーティンに組み込んだり、事前に時間を決めておいたりすると取り組みやすいのでおすすめです。
投稿する記事のネタがない
自分の専門分野はもちろん、ニュースや法改正をテーマにしても、いつかネタが切れてしまうかもしれません。
読者や顧客からの質問をヒントにしたり、他の司法書士ブログやQ&Aサイトを参考にしたりすることがおすすめです。
読者が全然集まらない
頑張って更新しているのに読者が集まらない場合、専門的すぎて読者に伝わらなかったり、営業色が強すぎて敬遠されたりしている可能性があります。
日々の中で感じたことや趣味についてなど、たまには日記のような内容の記事を投稿して、読者に親近感を持ってもらうことが大切です。
たとえば、ペットや休日の過ごし方を綴った記事に「親しみを感じて相談しました」という読者の声が届くなど、人柄が伝わる内容は相談への心理的ハードルを下げる効果があります。
更新することに疲れてしまった
「毎日記事を投稿する」「2日に1回は記事をリライトする」など、張り切りすぎて短い投稿頻度を設定すると、いつか挫折してしまうことが懸念されます。
「週に1回だけ更新する」「毎週火曜日と金曜日に投稿する」など、自分にとって無理のない範囲で投稿し、長続きさせることを意識しましょう。
ブログで集客を目指す司法書士はドットアンドノードへ

今回は、開業した司法書士のブログの重要性やメリットなどについて解説しました。
ブログはほとんどコストがかからないにもかかわらず、顧客との信頼関係を構築しやすく、専門性を簡単にアピールできる集客ツールですので、気になる方はぜひ運営に挑戦してみましょう。
もし「ブログでの集客に自信がない」「1人での運用には不安がある」という方は、Webでの集客に特化しているサービスの利用を検討してみてください。
弊社ドットアンドノードでは、Web集客を丸投げできる「司法書士専門のWeb集客パック」をご用意しております。
司法書士の方でWebからの安定した集客を獲得したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。