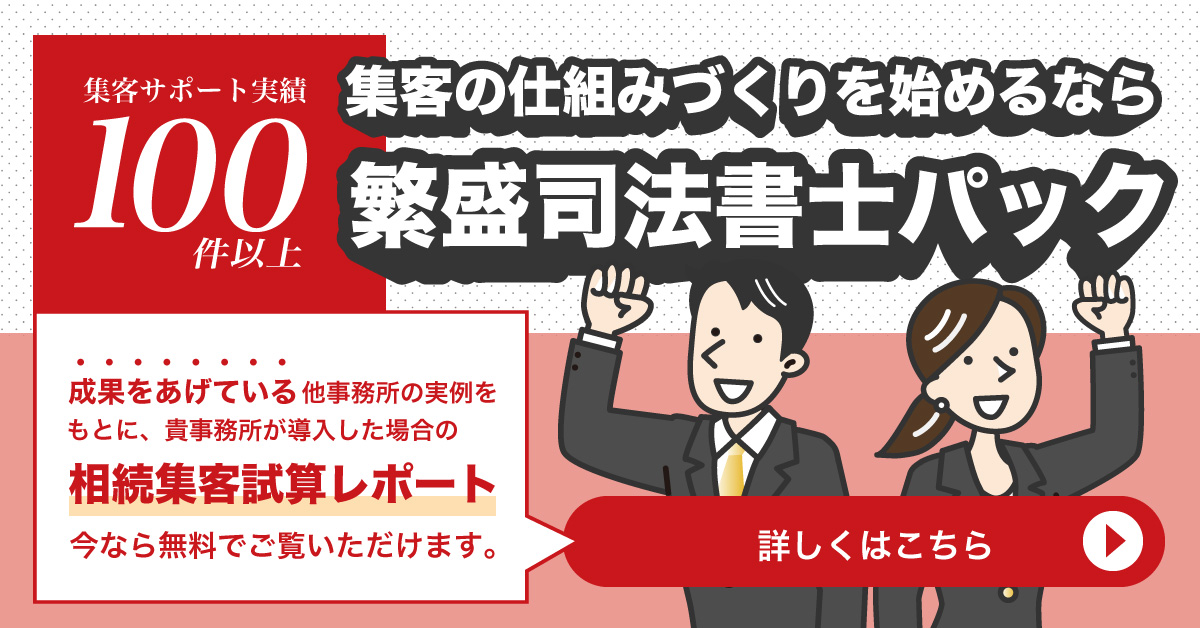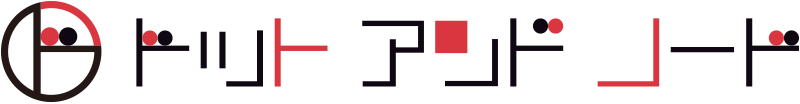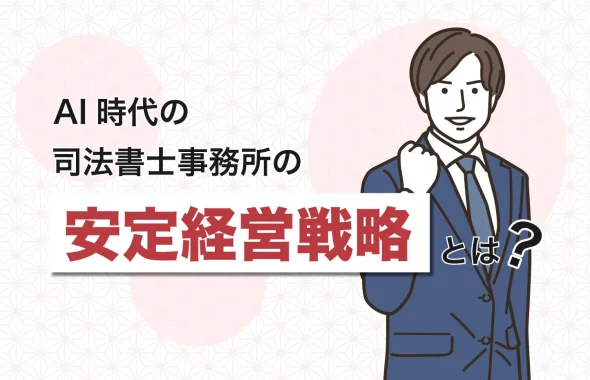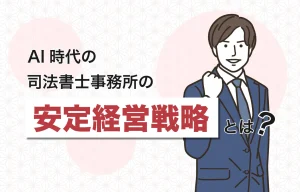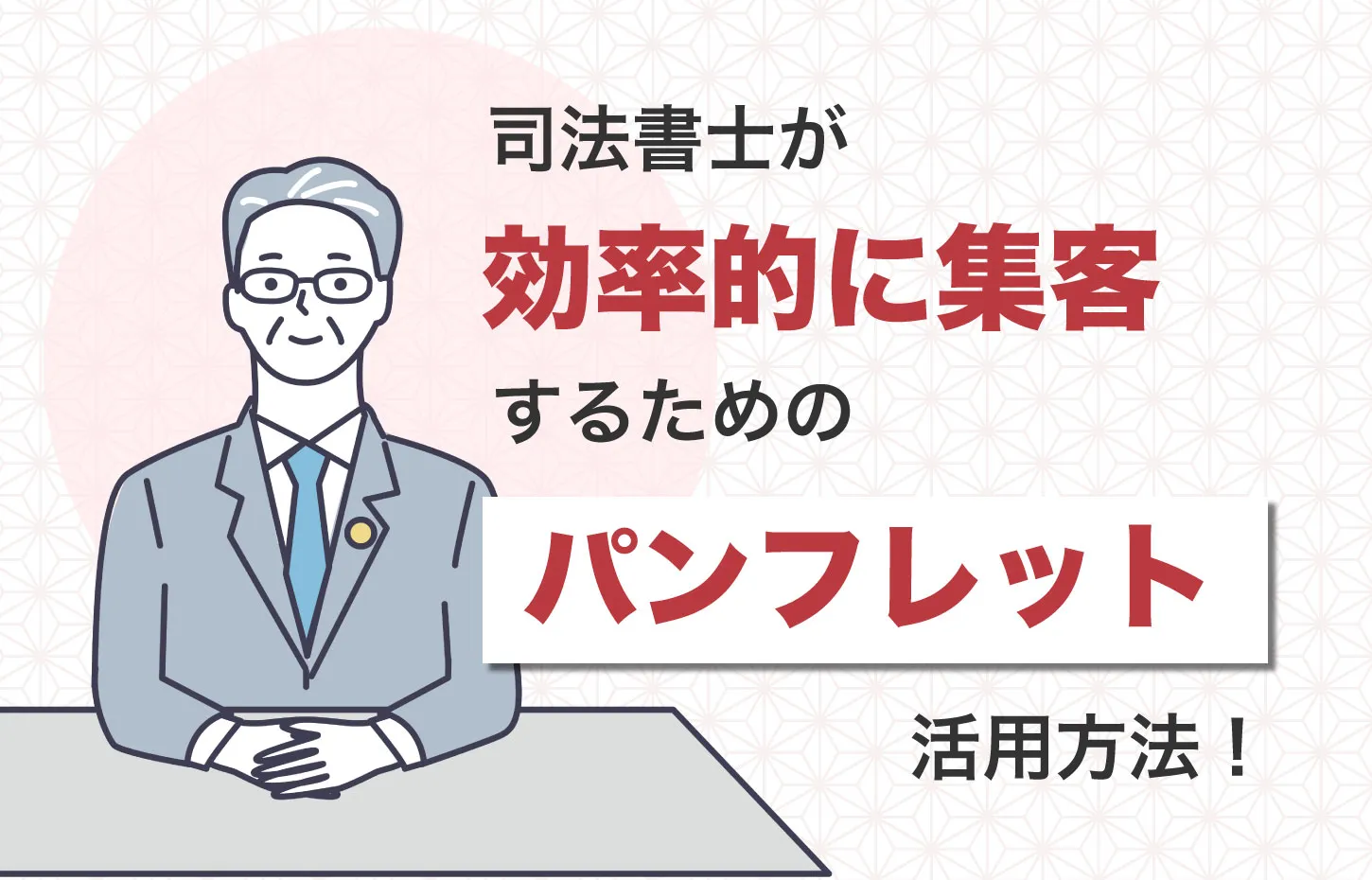
司法書士が効率的に集客をするためのパンフレット・リーフレット・アクセスブックの活用方法について解説
司法書士の集客にはさまざまな手法が使われます。
ホームページやWeb広告といった方法を駆使する事務所が増える中、紙媒体であるパンフレットも未だに有効な集客方法です。
しかし、その活用方法を誤ると、せっかく作ったパンフレットが無駄になってしまうことがあります。
本記事では、司法書士が集客に使うパンフレットについて、リーフレット・アクセスブックといった類似のものとの違いや、集客における活用方法について解説します。
司法書士に役立つパンフレット・リーフレット・アクセスブックとは

司法書士が集客のために用いるツールとして、パンフレットが挙げられます。
法律に不慣れな一般市民に対しても、信頼感や安心感を与える重要なコミュニケーション手段です。
パンフレットと同類のものに、リーフレット・アクセスブックがあるので、内容や違いを見てみましょう。
パンフレットとは
パンフレットとは、視覚的なデザインとテキストによって業務内容や法律の制度などについて解説することを目的とする、数ページにわたる小冊子をいいます。
パンフレットは、紙に印刷されて小冊子形式であり、その内容をWebでダウンロードして見られるようにPDFファイルで用意するのも効果的です。
たとえば日本司法書士会連合会は「相続手続チェックブック~想いをバトンタッチ~」というパンフレットをWebで公開しています。
難解な相続手続について具体的な手続の流れを視覚的に示すことで、読者の理解を助け、安心感を与えようとするものです。
パンフレットは相談を検討している層に対して有効で、展示会やセミナー、相談会、郵送資料、Webダウンロードなど、さまざまな場面で活用できます。
リーフレットとは
リーフレットは、パンフレットよりも簡素で、通常は1枚の用紙を折って使う形式が一般的です。
情報量は比較的少ないものの、要点を簡潔に伝えることができるため、通行人への配布や受付での手渡しなど、気軽に興味を引く目的で活用されます。
たとえば、司法書士事務所の業務概要、無料相談の案内、特定業務(相続登記、遺言作成など)の紹介などを掲載し、視認性の高いレイアウトやキャッチコピーで印象づけるのが効果的です。
特に地域密着型で集客したい司法書士にとっては、駅前での配布や地域の店舗との連携など、アナログな接点を作る上で欠かせないツールといえるでしょう。
内容はコンパクトでも、事務所の特色や強みをしっかりと打ち出す工夫が重要です。
アクセスブックとは
アクセスブックとは、特定のテーマに関して詳しい情報を収録した小冊子やガイドブック形式の広報物です。
日本司法書士会連合会が発行している「よくわかる相続:司法書士」のような形式が該当します。
内容としてはパンフレットに近いものがあるのですが、パンフレットが営業ツールとしての役割であるのに対して、アクセスブックは特定テーマに関する読み物としての役割があります。
役所や図書館・公民館など人が集まるところで読み物として持ち帰れるようにしておくことで、効果があるでしょう。
司法書士の集客のためのパンフレット等の使い方

司法書士が集客のためにパンフレット等はどのような使い方をするのでしょうか。
パンフレットの使い方には主に次の4つの方法が考えられます。
- 関心を高めるために使う
- 検索による比較を避けるために使う
- 相談・依頼という行動を顧客に起こさせるために使う
- 顧客に自分たちの存在を共有してもらうために使う
以下から、それぞれの使い方について詳しく見ていきましょう。
関心を高めるために使う
パンフレットは、司法書士の業務や自分の事務所に対しての関心を高めるために使います。
特定のことについてわからないことがある場合インターネットであれこれ検索して必要な情報を探します。
パンフレットがあることによって、司法書士とは何か、どんな相談ができるのか、弁護士や行政書士など他の士業との違いはなにか、といった初歩的な情報をパンフレットで伝えます。
そのパンフレットの中で自分の事務所が問題解決に役に立つとわかれば、興味をもってもらえて相談をしてもらえるようになります。
検索による比較を避けるために使う
パンフレットは検索による比較を避けるために使います。
ある問題に直面していて、司法書士に依頼する必要がある場合、次のステップとして行われるのはインターネットにおける検索です。
検索することで実績、価格、ホームページから受ける印象、などによって司法書士を比較します。
最初からパンフレットがあれば、司法書士を必要とする人は情報をそのパンフレットを用いてのみ整理するようになるので、あらためて検索して比較されずに済む可能性も。
また比較される場合でもパンフレットの存在が信頼性を高めるツールとなることもあります。
相談・依頼という行動を顧客に起こさせるために使う
相談・依頼という行動を顧客に起こさせるためにパンフレットを使います。
Webの情報やパンフレット等では一般的な情報提供に留まるのが通常です。
具体的に相談や依頼という行動に移すにあたって、決め手となるものが必要になります。
パンフレットが手元にある場合電話やメールがしやすいとともに、パンフレットを用意できるレベルにある事務所であると印象づけることが可能に。
信頼性が高まるため、相談・依頼という行動に移ってもらいやすくなります。
顧客に自分たちの存在を共有してもらうために使う
顧客に自分たちの存在を共有してもらうためにパンフレットは使えます。
一度依頼をした顧客が満足をした場合、同じ境遇にあって困っている人がいた場合に、自分の経験を共有します。
たとえば、相続登記の手続きの依頼を受けた顧客が、同じように相続登記の司法書士を探している人がいるときに、紹介してもらうことができます。
紹介時にパンフレットがあれば、紹介の際に手渡してもらえたり、PDFで用意している場合にはダウンロードURLを他の人に教えることが考えられます。
また、相続や成年後見といった分野では相続人や家族全員で検討するためのツールとして共有されやすいです。
パンフレットは、すでに顧客になった人や案件に関する関係者が共有するためのツールとしても利用できるといえます。
パンフレット等を作成するのが向いている司法書士

「集客の方法として、パンフレット等を作成するのが向いている司法書士」の特徴として次の2つが挙げられます。
- Web広告・SEO対策・SNSマーケティングなどの効果を挙げている
- 依頼になかなか結びついていない
ここからは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
Web広告・SEO対策・SNSマーケティングなどの効果を挙げている
すでにWeb広告やSEO対策、SNSを通じて集客チャネルを構築できている司法書士事務所にとって非常に効果的です。
たとえば、広告や投稿を見て興味を持った見込み客に対し、パンフレットを送付したり、ダウンロードできる形式で提供したりすることで、問い合わせや面談への移行率を高められます。
また、住所やメールアドレスといった情報を得られるので、セミナーをする場合にお知らせをしたり、法改正に関する情報を提供するなど、司法書士側からのアプローチが可能となります。
依頼になかなか結びついていない
従来のマーケティング施策が依頼になかなか結びついていない司法書士にとっても、パンフレット等は効果的です。
ホームページにアクセスがあっても、なかなか依頼に結びつかないその原因のひとつとして「サービス内容が十分に伝わっていない」「料金や対応範囲に不安がある」ことが挙げられます。
検索や広告でのアクセスでは再度訪問されない限り情報は断片的にしか伝わりません。
見やすく丁寧に作られた紙媒体で視覚的・論理的に説明することで、相談・依頼しようとしている人の不安を払拭することが可能です。
たとえば、手続きの流れ・費用の目安・相談事例・専門性の強みをまとめたパンフレットを配布することで、依頼者の心理的ハードルを下げられます。
とくに、年齢層の高い顧客や、家族と一緒に検討するケースが多い分野(相続・成年後見など)では、資料を持ち帰って共有できること自体が大きな価値になるでしょう。
パンフレット等を作成するのが向いていない司法書士
パンフレット等を作成するのが向いていない司法書士にも特徴があり、次の2つが挙げられます。
- 商圏に競争相手がいない
- Web広告・SEO対策・SNSマーケティングなどで認知が不十分
以下から、それぞれの特徴について深く見ていきましょう。
商圏に競争相手がいない
地域に司法書士事務所がほとんど存在せず、そもそも競合がいない環境にある場合は、パンフレット等による集客は急務ではないかもしれません。
ターゲットへのアプローチに紙媒体を使うより、直接の口コミや既存顧客との関係性を強化する方が効率的なケースもあります。
もちろん、今後の信頼構築や行政・地域団体との関係強化のためにパンフレットを備えること自体は悪くありませんが、「集客」の手段として優先すべきかどうかは見極めが必要です。
Web広告・SEO対策・SNSマーケティングなどで認知が不十分
まだWeb広告やSNSでの認知獲得に十分取り組んでおらず、そもそも「見込み客に存在を知られていない」段階の司法書士が、いきなりパンフレットを作っても十分な効果は期待できません。
パンフレットは興味を持った人に対して理解を深めてもらうツールとして有力ですが、無関心層に広くアプローチする手段として弱いといえます。
まずはWebサイトの整備、SNSや広告による露出強化、地域内での認知活動など、集客の「導線」を整えることが優先されるべきです。
司法書士がパンフレット等を作成する方法

司法書士がパンフレット等を作成する方法にはどのようなものがあるでしょうか。
自分たちで制作する方法と制作会社に委託する方法の2つと、自分たちで制作する場合にはどのような事項をパンフレットに記載すべきかをお伝えします。
自分たちで制作する
パンフレットやリーフレットを自分たちで制作する方法は、コストを抑えつつスピーディーに行えるというメリットがあります。
PowerPointやCanvaなどの無料ツールを使えば、ある程度のデザイン性をもったものを作ることも可能です。
ただし、商用利用の場合はライセンス範囲を確認して使用する必要があります。
しかし、自作には注意も必要です。素人感のあるパンフレットは「安っぽい=信頼できない」という印象を与えてしまい、せっかくの集客ツールが逆に依頼を遠ざける結果にもなりかねません。
費用面だけで判断せず、ツールとして機能するかを検討すべきでしょう。
ここからは、パンフレットを制作するにあたって最低限記載しておくべき要素、重視したいデザインについて見ていきましょう。
パンフレットに記載すべき情報
パンフレットは、司法書士事務所にとって、名刺よりも多くの情報を伝えられ、Webサイトほどではないにせよ、十分な情報量を持つツールです。
せっかく目を留めてくれた人がいても、肝心な情報が不足していれば「なんとなく不安」「この人に相談しても大丈夫なのか分からない」と感じさせてしまうこともあります。
安心して相談へ進んでもらうには、次のように最低限載せるべき情報を丁寧に盛り込むことが大切です。
- 名前・住所・電話番号・メールなどの連絡先
- 資格・所属団体・登録番号などの信用情報
- 相談できる内容(例:相続、登記、会社設立、債務整理など)
- 相談の流れ(予約の仕方、初回無料の有無など)
- 顔写真やスタッフ紹介
- 地域とのつながり(例:地元のイベントや相談会への参加、地名入りの紹介文、「このまちで30年」などの表現)
以下からは、司法書士のパンフレットに必ず記載したい要素を紹介します。
名前・住所・電話番号・メールなどの連絡先
相談を検討してもらうためには、まず「どうやって連絡できるのか」が明確であることが必要です。
住所や電話番号だけでなく、メールアドレスやQRコードでのLINE予約など、複数の連絡手段を用意しましょう。
資格・所属団体・登録番号などの信用情報
「本当に専門家なのか?」という不安を払拭するために、司法書士の資格、登録番号、所属会(例:東京司法書士会など)を明記します。
公的な情報は信頼感を高めるポイントになります。
相談できる内容(例:相続、登記、会社設立、債務整理など)
具体的に何が相談できるのかを示すことで、読者は「自分の悩みに対応してもらえるか」が分かります。
サービス一覧やカテゴリごとの説明を簡潔に記載すると親切です。
相談の流れ(予約の仕方、初回無料の有無など)
「まず何をすればいいのか」が分からないと相談に踏み切れません。
予約方法、相談方法(対面・オンライン)、初回無料の有無などを記載すると、行動へのハードルが下がります。
顔写真やスタッフ紹介
人となりが見える情報は、相談者の不安を和らげる効果があります。
司法書士本人の顔写真や、スタッフの簡単な紹介、経歴・一言コメントなどがあると、親しみや信頼につながります。
地域とのつながり(例:地元のイベントや相談会への参加、地名入りの紹介文、「このまちで30年」などの表現)
地域密着型であることを伝える表現は、親近感や信頼感を高める要素です。
たとえば「このまちで30年」「○○町で暮らす方々のために」などの文言や、地域イベントへの参加実績などを盛り込むと効果的です。
記載する情報が整っていてこそ、パンフレットは「安心して相談できる専門家」としての第一印象を形成します。
余白を活かしながら、読みやすさ・見やすさにも配慮した設計を意識しましょう。
パンフレット制作で意識したいデザイン
パンフレットは、ただ情報を詰め込むだけでは意味がありません。
重要なのは、以下の要素を踏まえて「読む気になるデザイン」に仕上げること。
- 字を大きくし読みやすくする
- 色をシンプルにし見やすくする(白、青、グレー系など)
- 事例やイラストを入れてわかりやすくする
- 伝えたい内容をしぼる
- 裏面にも目を向けてもらう工夫をする(地図や特典など)
特に高齢者や法律に不慣れな方が対象となる司法書士業務では、見やすさ・わかりやすさ・安心感がカギとなります。
文字だらけで圧迫感のあるパンフレットは読まれずに終わってしまうため、視線の流れや情報の整理にも配慮が必要です。
以下からは、制作時に意識すべきデザインのポイントを紹介します。
字を大きくし読みやすくする
特に高齢者層に配布する場合は、文字の大きさが非常に重要です。
小さな文字はそれだけで読む意欲を削いでしまうため、最低でも12〜14pt以上の文字を基本とし、見出しや強調部分はさらに大きめに設定しましょう。
色をシンプルにし見やすくする(白、青、グレー系など)
派手な色使いはかえって読みにくく、信頼性を損なうことがあります。
司法書士の業務に適したカラーは、白や青、グレーなどの落ち着いた配色。
背景と文字のコントラストにも配慮し、視認性を高めましょう。
事例やイラストを入れてわかりやすくする
文字だけでは伝わりづらい内容も、具体的な相談事例やイラストがあると一気に理解しやすくなります。
たとえば「相続登記の流れ」などを図解することで、法律に詳しくない読者にもイメージを持ってもらいやすくなります。
伝えたい内容をしぼる
情報を盛り込みすぎると、かえって伝えたいことがぼやけてしまいます。
読み手の立場に立ち、「何を知ってもらいたいのか」を絞り込むことで、シンプルで訴求力のある構成に仕上がります。
余白も読みやすさの一部と考えましょう。
裏面にも目を向けてもらう工夫をする(地図や特典など)
パンフレットの裏面は見落とされがちですが、工夫次第で注目を集めることができます。
事務所へのアクセス地図や、無料相談の特典情報などを掲載すれば、読者が「最後まで目を通す」動機につながります。
パンフレット制作でよくある失敗パターン
パンフレットは、見込み客に「この人に相談してみよう」と思ってもらうための重要なツールです。
しかし、せっかく制作しても、次のような失敗によって逆効果になってしまうことも少なくありません。
- 専門用語ばかりで意味が伝わらない
- パンフレットが古くて今の業務と違う
- 料金が書いていない(不安にさせる)
- 連絡先が目立たない(結局どこにかければいいの?となる)
- 「安心感」がない(怖そう、冷たそうなどの印象)
特に司法書士という専門職の場合、「内容が難しそう」「怖そう」「わかりにくい」といった印象を与えてしまえば、それだけで依頼のチャンスを逃してしまう可能性があります。
以下からは、よくある失敗例見ていきましょう。
専門用語ばかりで意味が伝わらない
「登記簿謄本」「債務整理」「所有権保存登記」など、業界用語が並ぶと一般の方には意味が伝わりません。
なるべく平易な言葉に言い換える、補足説明を入れるなどの配慮が必要です。
パンフレットが古くて今の業務と違う
何年も前に作ったまま更新していないパンフレットは、実際の業務内容とズレが生じるリスクがあります。
「成年後見は今はやっていません」「事務所の場所が変わりました」などがあると、逆に不信感を与えてしまいます。
料金が書いていない(不安にさせる)
「いくらかかるかわからない」と思わせると、それだけで相談のハードルは上がります。
具体的な金額が難しい場合でも、「相談料は30分無料」「相続登記は〇万円〜」などの目安があると安心感につながります。
連絡先が目立たない(結局どこにかければいいの?となる)
連絡先がパンフレットの端に小さく載っているだけでは、見落とされがちです。
電話番号やQRコード、LINE・メールなどの問い合わせ手段は、目立つ場所に大きく掲載し、行動を促すレイアウトにしましょう。
「安心感」がない(怖そう、冷たそうなどの印象)
固すぎる表現や事務的なレイアウトは、「相談しにくい」という印象を与えます。
顔写真、やさしい言葉づかい、親しみやすい色づかいなどによって、相談者が「ここなら大丈夫」と思える雰囲気を演出しましょう。
失敗が生じやすいパターンを避けることで、パンフレットは読む人に寄り添う存在となり、信頼される第一歩になります。
情報と印象、両面から安心感を与える工夫を心がけましょう。
制作会社に依頼する
専門の制作会社に依頼すれば、デザイン性の高いパンフレットをプロの視点で仕上げてもらえます。
構成やコピーライティング、イラスト・写真選定までを一括して任せられるため、ブランディングや集客効果の面でも安心です。
とくにターゲット層が高齢者や相続などのセンシティブな分野の場合、言葉の選び方ひとつで印象が大きく変わるため、プロのライター・デザイナーの手腕がものを言います。
また、紙の印刷だけでなくPDF版・Web掲載用の形式も同時に納品してもらえば、デジタル集客との相乗効果も得られます。
費用は数万円~数十万円と幅がありますが、長期的に活用できるツールと考えれば、十分に費用対効果のある投資です。
制作会社の探し方
制作会社を選ぶ際は、「士業や司法書士に特化した実績があるか」を重視しましょう。
単にパンフレットが作れるだけでなく、法律サービスの特徴や依頼者の心理を理解している制作会社であれば、相談者目線の的確な内容が期待できます。
「士業 パンフレット 制作」「司法書士 チラシ 作成」などのキーワードで検索し、事例や実績が豊富な会社を選ぶのがコツです。
特に、相続・登記・成年後見といったテーマに特化したテンプレートを持っている会社なら、初期打ち合わせもスムーズです。
また、士業向けWeb制作を手がける会社では、Webページとの一貫性を意識したデザイン提案をしてくれる場合もあり、ブランディングの統一にも繋がります。
司法書士の集客にパンフレットは有効!司法書士の集客に強い制作会社に依頼しよう

本記事では、司法書士の集客のためのパンフレット等についての利用方法について解説しました。
司法書士が集客のためにパンフレットを作ることはWeb集客時代にあってもなお有効ですが、優先順位や役割を考えて作成しないと無駄になったり逆効果となることもあります。
制作にあたっては、士業や司法書士業務の特性を知った制作ができる会社に依頼することをおすすめします。
ドットアンドノード株式会社はAISASモデルを活用した集客戦略と営業支援に強みを持っており、士業・司法書士業務の特性に沿った訴求設計から、反響を生むパンフレット制作までワンストップで支援可能です。
事務所の魅力を伝える印刷物づくりに本気で取り組む場合には、メール相談からお気軽にご連絡ください。