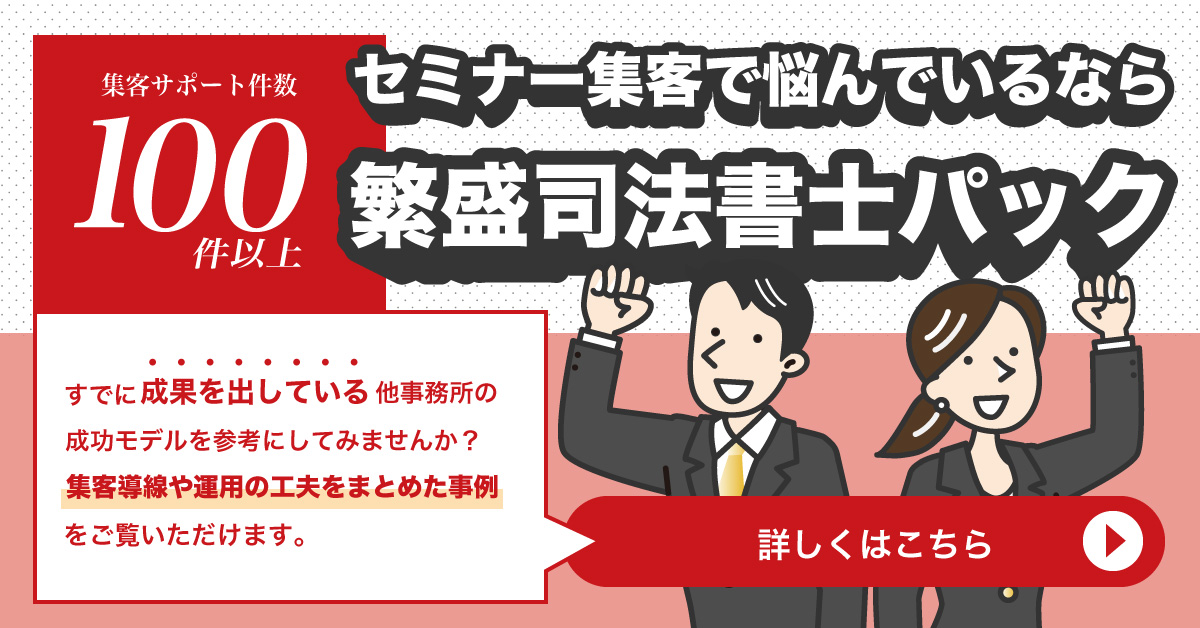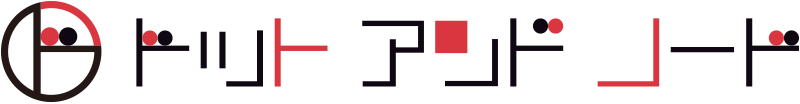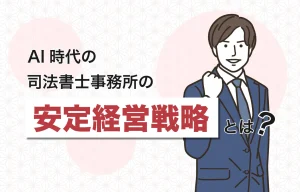司法書士がセミナーで集客する方法|失敗しない準備とフォローアップ戦略
司法書士が顧客を獲得する方法のひとつとして、セミナー集客があります。
相続や不動産登記など専門知識が必要な分野では、セミナーという直接説明できる場を設けることで信頼を得やすいもの。
司法書士にとって、相談や依頼につながるチャンスになりやすいのです。
通常の営業では低かった成約率も、セミナーを介した場合、成約率が高いという声もきかれます。
本記事では、司法書士がセミナーを活用して集客を成功させるためのステップや工夫をわかりやすく解説します。
司法書士がセミナー集客するメリット

セミナーは司法書士の「専門性」を示せる場。
他の集客手段にはない強みがあります。
信頼性や専門性を具体的にアピールでき、見込み客と直接会えるため相談につながりやすいのが特徴です。
また、一度の接触にとどまらず、長期的な関係を築くきっかけとなり、他士業との差別化にもなります。
司法書士がセミナーをするメリットとして、次の4つがあります。
- 信頼性・専門性をアピールできる
- 見込み客との直接的な接点がもてる
- 参加者と長期的な関係を構築できる
- 他士業との差別化になる
以下からは、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
信頼性・専門性をアピールできる
セミナーでは司法書士が持つ専門知識をわかりやすく伝えることで、「この人に任せたい」という印象を持ってもらいやすくなります。
セミナーの場は、専門知識を披露し問題解決能力を示せるだけでなく、人柄や信頼性を直接伝え、他社との違いもはっきりと示せる場です。
難解な法律用語を日常的な表現に噛み砕いて解説し、具体的な事例を交えて説明してみましょう。
すると、参加者に専門性と信頼感が伝わり「この先生なら安心だ」と感じてもらえる可能性が高まります。
見込み客との直接的な接点がもてる
セミナーは、広告やホームページだけでは得られない「直接会話」の機会です。
参加者の悩みや疑問をその場で聞きながら対応できるため、距離が縮まり信頼が深まりやすくなります。
「セミナーで直接会って人柄に触れたことで、この人なら信頼できると感じた」と参加者は思いやすく、顔を合わせて話す効果は見逃せません。
ほかにも講義中に質問を受け付けるなど双方向のやりとりを行えば、参加者は積極的に参加でき、より親近感を抱いてもらえるのです。
参加者と長期的な関係を構築できる
セミナー後もフォローを続けることで、一度きりで終わらない長期的な関係づくりが可能です。
今すぐ依頼に至らなくても、定期的な情報提供や連絡によって将来的な相談につながるもの。
セミナー参加者は一般の問い合わせ客に比べて顧客単価が高くなったり、参加者からの「紹介発生」が起こる率も高い傾向があります。
つまり、セミナーからの顧客は長期的には価値の高い見込み客になるのです。
セミナー後も継続的な接点を保つことで、信頼関係が深まり「困ったときはあの先生に相談しよう」と思い出してもらえる可能性が高まります。
他士業との差別化になる
長く開業している場合、地域で同業の司法書士が増えるケースがあるかもしれません。
そんな中でセミナーを開催すれば、専門性を前面に出し、他事務所と差別化できます。
ただ資格を持っているだけでは選ばれにくい時代です。
自らの知識や経験を直接発信できるセミナーで、他の司法書士との差を示せるわけです。
たとえば、相続や遺言といったニーズに特化したセミナーを開催するなど。
すると「その分野に強い司法書士」というブランディングにもつながり、競合士業との差別化を図れるのです。
司法書士がセミナーを企画する手順

セミナーを成功させるには次のような事前の準備が欠かせません。
- ステップ1.目的とターゲットを決める
- ステップ2.テーマと内容を設計し、当日の進行次第を決める
- ステップ3.開催形式と会場、開催頻度を決める
- ステップ4.集客・告知を行う
- ステップ5.セミナー当日の運営を行う
- ステップ6.フォローアップする
目的やターゲットをはっきりさせ、テーマや会場選びから当日の運営、終了後のフォローまで一連の流れを押さえることが大切です。
以下からは、セミナー企画の基本ステップをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1.目的とターゲットを決める
まず最初に「セミナーを開く目的は何か」を定めましょう。
「相続相談の案件を増やしたい」「不動産登記の依頼につなげたい」などゴールを具体的に設定してみてください。
その上で、「対象とする顧客層」をできるだけ具体化しましょう。
セミナーの目的を設定することで「最終的にどういう集客を実現したいか」がはっきりします。
ターゲットを定めることで「誰に情報を届けたいか」も決まります。
たとえば「相続対策セミナー」であれば、相続に関心のある高齢者やその子世代がターゲットに。
このように目的・ターゲットを起点に据えることで、後のテーマ設定や集客方法も効果的に計画できるのです。
ステップ2.テーマと内容を設計し、当日の進行次第を決める
ターゲットの悩みに直結するセミナーテーマを設定し、内容は具体的で実用的なポイントに絞りましょう。
「相続の基本」「不動産登記の流れ」など参加者にとって身近で役立つテーマだと興味を引きやすくなります。
専門知識を一般の人にも理解できる言葉で伝える工夫も大切です。
さらに、当日の進行についても概要を決めておきましょう。
たとえば、開会の挨拶や自己紹介、講義と質疑応答の時間配分、閉会後の個別相談案内など。
大まかな流れと担当者の配置を考えておくのです。
受付係や司会進行役、質疑応答のサポート役などをあらかじめ決めておくことで、当日の運営がスムーズになり参加者の満足度も高まります。
ステップ3.開催形式と会場、開催頻度を決める
オンラインかオフラインか、開催形式を選び、参加者が集まりやすい方法を検討しましょう。
対面開催の場合はアクセスしやすい会場(自社事務所、公共施設、貸会議室など)を確保しなければなりません。
オンラインの場合はZoomなど使いやすいツールを選びましょう。
開催頻度も重要です。
単発開催だけでなく定期的に開催することで認知度が高まり、信頼感も増します。
実際、毎月決まった日にセミナーを継続開催して習慣化したところ、回を重ねるごとに参加者が増えた事例もあります。
ただし頻度が多すぎると希少性が薄れるため、対象層に合わせ適切な間隔を検討してください。
最初は季節ごとや四半期ごとなど無理のない頻度で始め、反応を見ながら調整するのがおすすめです。
開催形式・会場によって当日の進行にも違いが出るため、直前までリハーサルを行い、不安要素を潰しておきましょう。
ステップ4.集客・告知を行う
設定したターゲットにセミナー開催の案内を届ける方法を選び、効果的に告知しましょう。
具体的には、オンラインであれば事務所ホームページやブログ、SNS、メールマガジン、プレスリリースなどを活用。
オフラインであればチラシのポスティングや地域紙への掲載、人脈を通じた口コミなど、複数チャネルで周知します。
一つの手段だけに頼らず、Webとリアル双方からアプローチすることで、より多くの見込み客にセミナーのことを、ひいてはあなた自身のことを伝えられます。
告知の際はセミナーの日時・場所・テーマ・対象者・申込方法など必要情報を漏れなく伝え、魅力が伝わるよう工夫しましょう。
特に初開催時は周知に時間がかかるため、開催日の1〜2か月前から順次告知を始めると安心です。
ステップ5.セミナー当日の運営を行う
当日はスムーズな進行と参加者が満足できる環境づくりを徹底しましょう。
開始前に会場設営やオンライン接続確認、配布資料の準備を済ませておいてください。
受付では参加者を笑顔で迎え、名簿チェックや資料配布を迅速に行いましょう。
講義中は一方的に話し続けるのではなく、適宜、質問がないか訊いたり、専門用語を噛み砕いて説明したりして参加者の理解度を高めるべき。
複数スタッフが確保できる場合は、役割分担が重要です。
受付係・案内係・質疑応答の補助スタッフなどを配置しておけば、講師(司法書士)は講義に専念でき、参加者も安心して内容に集中できます。
当日、円滑な運営ができれば、参加者の満足度に直結します。
細かな気配りを忘れずに行いましょう。
ステップ6.フォローアップする
セミナー終了後は、参加者との継続的なつながりを持つため計画的にフォローを行いましょう。
アンケート記入をお願いし回収する、退出時に個別相談の予約を受け付ける、といった流れをあらかじめ準備しておくのです。
終了後はできるだけ早くお礼メールを送り、セミナー資料や関連情報を共有しましょう。
「本日はご参加ありがとうございました。ぜひご家族とも資料をご覧ください」など感謝の気持ちを伝えると好印象です。
お礼の際、アンケートで寄せられた悩みに触れ、「〇〇の件で詳しい説明をご希望の場合は個別相談も承ります」など次のアクションを促す一文も添えましょう。
参加者との名刺交換や後日の個別相談案内は必須です。
こうしたアフターフォローによって信頼関係を維持し、「また相談したい」「知人にも勧めたい」と思ってもらえる長期的な関係構築を目指します。
司法書士によるセミナーでの集客方法

集客の成否は告知方法の選び方に左右されます。
オンラインとオフラインそれぞれの手法を組み合わせ、ターゲットに届く告知をすることで効果的に参加者を集められます。
以下からは、オンライン集客、オフライン集客それぞれの具体的な方法を紹介します。
オンラインでの集客
次のようにオンラインを活用すれば、地域を超えて多くの方にセミナー情報を届けられます。
- 事務所ホームページ・ブログ
- SNS広告・Google広告
- メールマガジン・LINE公式アカウント
複数の手段を組み合わせることで、狙ったターゲット層へ効率的にリーチ可能です。
さらにSEO記事やプレスリリースを活用すれば、検索やニュース経由で新たな見込み客にアプローチしやすくなります。
コロナ禍以降、セミナーのオンライン化が進みました。
今や、「セミナー」という媒体の半数以上はオンライン開催という状態です。
逆にいえばそれだけセミナー開催の敷居が低くなったことも意味しており、オンライン集客は今や司法書士にとっても欠かせない手法。
各手法について、以下から詳しく見ていきましょう。
事務所ホームページ・ブログ
公式サイトやブログにセミナー告知を掲載しましょう。
信頼性のある公式情報として、参加申し込みしてもらうための効果的な方法です。
セミナー概要や講師プロフィール、過去の開催報告などを載せておくと、訪問者に安心感を与え興味を持ってもらいやすくなります。
またSEO対策を施した記事コンテンツを掲載すれば、検索でヒットして新規層の流入も期待できるもの。
ドットアンドノードでは、司法書士事務所向けにホームページの制作・運用からSEO記事の執筆代行、SEOコンサルティングまでトータルに支援しており、多彩な手法で集客力向上をサポートしています。
HP運営は専門家に任せることで、士業としての他の業務にも力を入れられるようになります。
SNS広告・Google広告
FacebookやInstagramなどSNSの広告、およびGoogle広告(リスティング広告)でもセミナー開催を伝えましょう。
ターゲットを絞った配信ができ、短期間で効率的に集客できる手段です。
たとえば「相続セミナー 静岡」など特定キーワードで広告を出せば、興味のある地元層に絞って訴求でき、高い成約率が期待できます。
リスティング広告を活用すると、セミナー申し込みや問い合わせ件数を数倍に増やすことも可能。
ドットアンドノードでは、Google広告やSNS広告の運用支援も行っており、セミナーの認知を最短で広げるための施策を提供しています。
プロの手で無駄なく広告運用することで、少ない予算でも必要な人に確実に情報を届けることができるのです。
メールマガジン・LINE公式アカウント
既存顧客や見込み客にダイレクトに情報を届けられるメールマガジンやLINE公式アカウントも、セミナー集客におすすめです。
セミナー開催の案内を直接通知できるため、参加率アップにつながります。
また、日頃から有益な情報を発信しておけば読者との関係性が深まり、「この先生のイベントなら参加したい」と感じてもらいやすくなるもの。
特にLINEは開封率が高く、気軽に反応を得やすいツールです。
ドットアンドノードでは、LINE公式アカウント運用やメール配信を活用した継続フォローの仕組みづくりもサポートしています。
たとえば、ステップ配信で定期的に相続知識を提供するなど。
セミナー参加者との接点を維持し、次回イベントや個別相談への誘導をスムーズに行えるようになります。
オフラインでの集客
地元密着の集客には、次のようなアナログ手法もおすすめです。
- 地域メディア・広報誌
- ポスティング・ポスター掲示
- 人脈(士業ネットワーク・異業種交流会・既存顧客による紹介)
特に高齢者層などWebに馴染みが薄い層にセミナー開催を伝えるには、紙媒体での告知が欠かせません。
ほか信頼できる方からの紹介であれば参加ハードルが下がり、質の高い見込み客を得られます。
以下から、各種オフライン施策を詳しく見ていきましょう。
地域メディア・広報誌
地域の新聞や広報誌、ケーブルテレビのイベント告知欄などにセミナー情報を掲載すれば、地元住民に広く周知できます。
司法書士事務所が自治体と協力して市民向けセミナーを開催し、事前に市の広報紙で募集をかけたところ、盛況となった例も増えています。
地域密着のメディアは信頼感が高く、「地元で活動する専門家」という安心感を持ってもらいやすいこともメリットです。
特に自治体の広報や地域情報誌は中高年層の目に留まりやすいため、相続や遺言セミナーの告知に適しています。
開催前後に地域紙やチラシで告知を行えば、より多くの参加者を集めやすくなります。
ポスティング・ポスター掲示
チラシのポスティングやポスター掲示も、身近な場所で繰り返し目に触れさせることで参加意欲を高められる手法です。
配布エリアは、ターゲット層に合わせて選定しましょう。
たとえば相続関連セミナーの場合、高齢者が多い地域や団地に重点的にチラシを配布すれば反応率が高まります。
ポスターは司法書士事務所の近隣や公共施設の掲示板、スーパーや銀行の張り紙コーナーなど、人目につく場所に貼りましょう。
デザインは一目で内容が伝わるよう工夫を。
問い合わせ先もしっかり明記しましょう。
繰り返し目にすることで認知が広がり、「そういえば今度○○でセミナーがあるらしい」「あ、そうだね!あそこに貼ってるあれでしょ!」というように、話題にしてもらいやすく、口コミが広がる効果も期待できます。
人脈(士業ネットワーク・異業種交流会・既存顧客による紹介)
司法書士同士や他士業とのネットワーク、さらには異業種の知人や既存顧客からの紹介も集客には欠かせません。
たとえば税理士や不動産業者と連携し、「うちの司法書士仲間が相続セミナーをやるのでぜひ」と顧客に声をかけてもらえば、あらかじめ高い信頼度を持ってくれている見込み客を得られます。
士業同士で合同セミナーを開催するのもおすすめ。
たとえば、司法書士と税理士が合同で相続対策セミナーを開催するなどです。
また既存顧客で満足度の高い方にお願いして知人を誘ってもらったり、感想をSNSで発信してもらったりすれば、口コミ効果が広がります。
「○○事務所のセミナーに参加して相談したらとても良かった」というリアルな声ほど、新規参加者の安心感につながるものはありません。
人脈をフル活用し、信頼の輪を広げる、集客力を高めていきましょう。
司法書士セミナーを成功させる方法

セミナーを成功させるには、次のような工夫が欠かせません。
- 専門知識をわかりやすく伝える
- 信頼関係を築く工夫をする
- 集客から当日運営までの導線設計をしっかり決める
- 開催後にフォローアップを徹底する
せっかく集まった参加者には満足してもらい、相談につなげたいもの。
専門知識を参加者が理解できる形に落とし込むことと、イベント内外で丁寧に信頼関係を築くことが大切です。
以下から、それぞれの具体的なポイントを解説します。
専門知識をわかりやすく伝える
参加者が理解しやすい、次のような工夫を取り入れることで、セミナーの満足度と信頼性が高まります。
- 専門用語をかみ砕いて解説する
- 図や事例を交える
- 一方的な講義にせず参加型にする
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
専門用語をかみ砕いて解説する
専門的な法律知識も、伝え方次第でわかりやすくできます。
難解な専門用語は日常的な言葉に置き換え、かみ砕いて解説しましょう。
たとえば「相続人不存在」という言葉は「相続する人が誰もいない状況」のように平易な表現に言い換えるなどです。
図や事例を交える
図表やイラストを用いたり、身近な事例を交えて説明したりすると、内容が具体的にイメージしやすく、理解が深まります。
たとえば家系図の図を示して相続関係を説明したり、実際にあった相談ケースをモデルに流れを解説したりしてみましょう。
一方的な講義にせず参加型にする
一方的な講義にせず、参加型にする工夫も重要です。
適宜質問を募集したり、簡単なワークや〇×クイズを取り入れたりすると、参加者が主体的に考え関心を高めることができます。
「知識を得た上で楽しかった」と感じてもらえれば、セミナーの満足度は格段に上がるものです。
参加者が抱える悩みに直結するテーマを設定する
セミナー内容は、参加者のニーズに直結しているほど効果的です。
「相続の基本」「不動産登記の具体的な手続き」といった、参加者が実際に直面しそうなテーマを選びましょう。
身近で具体的な内容ほど「ぜひ聞いてみたい」と感じてもらいやすくなります。
事前に参加申し込み時のフォームで簡単な悩みや関心事をヒアリングしておくのもおすすめです。
「相続税について知りたい」「親名義の不動産を自分に変えるには?」など声を集めておけば、当日の説明に反映させることができます。
参加者の知りたいことに答える形でセミナーを設計すれば満足度が高まり、「自分のためのセミナーだった」という特別感にもつながります。
逆に、焦点がぼやけたテーマだと印象に残らず次の行動にも結びつかないため、誰に何を届けるセミナーかを明確にしておきましょう。
信頼関係を築く工夫をする
セミナー中、および前後の対応で信頼関係を築くことを意識しましょう。
まず冒頭でしっかり自己紹介の時間を取り、資格や実績だけでなく人となりが伝わるエピソードも交えて話します。
「なぜ司法書士になったか」「趣味は○○で〜」など適度にパーソナルな話題を入れると親近感が湧き、共通点などが見つかれば相談しやすい雰囲気になるもの。
講義内では実際にあった相談事例を紹介すると具体性が増し、「この先生は経験が豊富なんだな」「自分と似たケースも扱っている」と参加者は感じます。
たとえば「以前○○市にお住まいの方からこんな相続相談を受けまして…」といった実例を(個人が特定されない範囲で)話すなど。
参加者に「自分ごと」化してもらい、信頼性と説得力が増すためです。
また、質疑応答や個別相談では誠実な姿勢で臨むことが何より大切。
専門家として正確に答えるのはもちろん、どんな初歩的な質問にも丁寧に耳を傾けてください。
わからないことがあればその場で適当に答えず「後日調べてご連絡します」と対応するのも誠実さの表れです。
真摯な対応ができれば、参加者は安心できるもの。
「この先生なら信用できる」という気持ちを強めていただきましょう。
集客から当日運営までの導線設計をしっかり決める
セミナー開催を集客で終わらせず、相談受注につなげるには、参加前から終了後までの導線設計が重要です。
まず、参加申し込み時点で簡単なヒアリングフォームを用意しましょう。
申し込みフォームに「現在お困りのこと」「セミナーで特に知りたいこと」を書いてもらう欄を設けておけば、参加前からニーズを把握でき当日の説明や個別フォローが的確にできます。
またセミナー終了時には、無料相談会や個別相談の案内を必ず行いましょう。
「本日はご清聴ありがとうございました。お時間ある方はこの後個別相談も承りますのでぜひお声がけください」とアナウンスしたり、後日使える無料相談チケットを配布したりするのも効果的です。
その場で次のステップを提示することで相談につながりやすくなります。
さらに退出時にも、アンケートを書いてもらいましょう。
アンケートには満足度や感想に加え、「現在困っていること」「個別に相談したいこと」の質問項目を入れておきます。
回答から一人ひとりの悩みや関心度を把握し、後日のフォローに活用するわけです。
「相続登記でお悩みと書かれていましたが、ぜひ一度詳しくお話ししませんか?」と声をかけるきっかけになるからです。
このように「セミナー集客→参加→相談予約→成約」までの流れをあらかじめ設計しておくことで、集客した見込み客を確実に顧客化する率が高まります。
開催後にフォローアップを徹底する
セミナーは開催して終わりではありません。
終了後の対応によって、相談や依頼につながるかが決まります。
参加者へはできるだけ早くお礼と資料提供の連絡をしましょう。
セミナー翌日までには「ご参加ありがとうございました」のメールを送り、講義資料や関連する記事URL等を共有しましょう。
資料は参加者自身の復習になるだけでなく、家族や知人と共有してもらうことで周囲へのPR効果も期待できます。
次に、回収したアンケートを読み込み、個別対応が必要な人にはこちらからアプローチを。
「○○について詳しく相談したいと書かれていましたが、お力になれればと思います。一度無料相談をいかがでしょうか?」といった具合に、相談予約につなげるフォローをしましょう。
セミナー参加者向けに個別相談の導線を用意しておくのも大事です。
たとえば「◯月◯日〜◯日限定でセミナー参加者優先の無料相談会を実施」「希望者には事務所での個別相談をご案内」といった機会を設けて案内しましょう。
その後も継続して情報発信をすることが長期的な関係構築につながります。
セミナー参加者をリスト化し、定期的に役立つニュースやコラムをメールやLINEで配信すれば、「ためになる情報をくれる頼れる先生」というポジションを維持できます。
そうして信頼関係を育めば、いざという時に相談や依頼につながりやすくなるのです。
満足度が高ければ依頼や紹介につながり、長期的な集客効果が得られるのです。
司法書士の集客成功事例

司法書士がWebやセミナーを活用して集客に成功した事例として、次が挙げられます。
- Web集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に
- 案件の半分以上がホームページからの成約に
- 安定的に業績が伸びるスキームが出来た
いずれもドットアンドノード株式会社の支援を受けた事務所の例で、セミナー集客やWeb集客を仕組み化することで顧客獲得に大きな成果を上げています。
それぞれ、以下から詳しく見ていきましょう。
Web集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に
杠(ゆずりは)グループ様のケースでは、ドットアンドノードの支援によりWeb集客の仕組み化を行った結果、問い合わせ件数が約1.5倍に増加しました。
具体的には、ホームページ上に相続や不動産に関する専用の集客ページを設置し、Google広告やSNS広告で見込み客を誘導する導線を構築しました。
セミナー開催前後の問い合わせが大幅に増え、セミナー参加者以外からのWeb経由の相談も着実に増加しています。
担当者の方は「Web上で常に相談窓口が開いている状態になり、セミナーをやらない月でも安定して問い合わせをいただけるようになった」と手応えを語っています。
案件の半分以上がホームページからの成約に
荒俣司法書士事務所様は、以前よりホームページから集客を試みていたものの月に1件あるかないかという状況でした。
しかし、ドットアンドノードの「繁盛司法書士パック」を導入後は、毎月3件以上の安定した成約が実現しました。
「今では、仕事の半分以上がこちらのホームページ経由で来ています」と荒俣先生。
Web経由の新規案件比率が、50%を超えるまでになっています。
さらに広告から流入した見込み客の成約率は80%程度と高水準で、ほぼ丸投げで運用を任せても安定した成果が出ているとのこと。
以前はホームページからの問い合わせが月に1件あるかないかで悩んでいたところ、ドットアンドノードによる集客特化型サイトの構築と広告運用代行により劇的に改善したのです。
「問い合わせさえあれば、成約できるかは自分次第。問い合わせが来るようになったのが何より大きい」とのコメントもいただいており、安定した集客基盤が築けたことがうかがえます。
安定的に業績が伸びるスキームが出来た
静岡鉄道様(静鉄不動産相続サポートセンター)のケースでは、新規事業として相続サポート事業を立ち上げる際にドットアンドノードの支援を受け、広告・HP・問い合わせまでの一連の流れを構築しました。
そして、毎月4〜5件の問い合わせと1〜2件の契約獲得をコンスタントに実現。
商談に至ったお客様からは、ほぼ100%ご契約いただける状態になりました。
さらに事業開始から5年間黒字を継続。
広告費を増額した後には単発で3億円の売上案件も生まれるなど、大きな成果に結びついています。
静岡鉄道様は当初、資格取得や知識習得を進めつつも「どうやって相続に悩むお客様と商談の場を作るか」が課題でした。
ドットアンドノードが培ってきた司法書士向け集客ノウハウを応用した仕組みによって安定的に案件を獲得できるスキームを確立したのです。
長く信頼を築くために司法書士セミナーを開催しよう!

セミナー集客は準備や運営に手間がかかりますが、信頼を築き顧客との出会いを広げる大きなチャンスです。
最初から完璧を目指す必要はありません。
小さく始めて、改善を重ねることで必ず成果が見えてきます。
本記事で紹介したポイントを参考に、まずは一歩踏み出して自分に合った形でセミナーを開催してみましょう。
「セミナーを開催しても集客が安定しない」「次につながらない」と感じている司法書士の方も少なくありません。
ドットアンドノード株式会社は、司法書士事務所向けに「繁盛司法書士プラン」を展開。
ホームページ制作から広告運用、問い合わせ獲得までを一括代行し、6か月で成果が出なければ解約可能です。
リピート率は96%と高く、大阪の事務所では月17件の問い合わせ・8件成約(2023年8月実績)を達成しました。
AISASモデルに基づき、WEB広告・SEO・プレスリリース・営業支援を組み合わせて継続的な顧客獲得を実現します。
無料WEB診断で、地域需要と競合を分析することも可能であるため、ぜひお気軽にお問い合わせください。