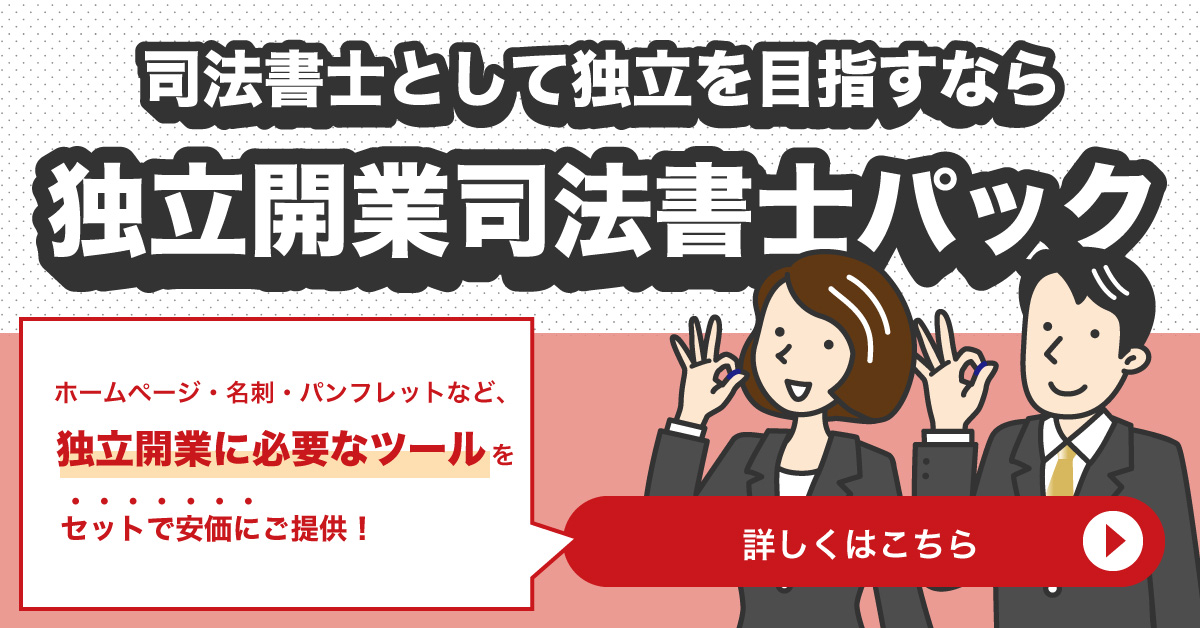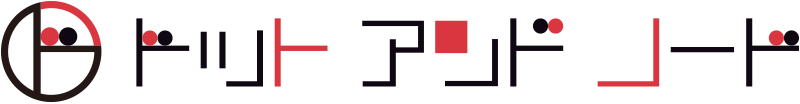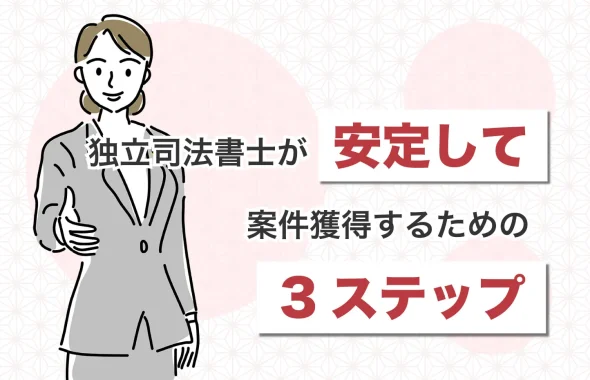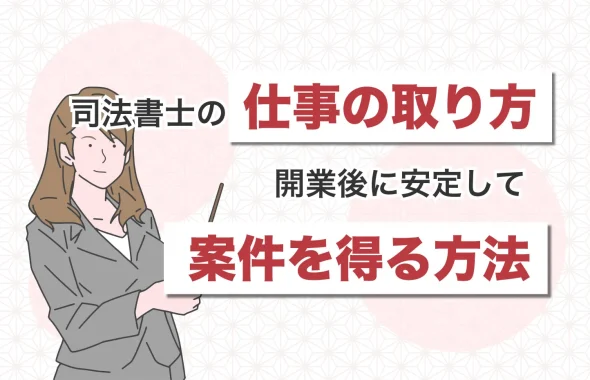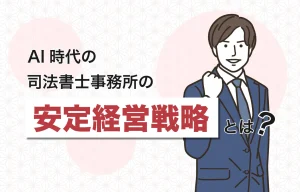司法書士必見!人脈で仕事を増やすための戦略と注意点についてわかりやすく解説!
独立したばかりの司法書士や、経営が伸び悩んでいる司法書士にとって、人脈は案件を広げるための最重要資産です。
資格や知識があるだけでは、仕事の幅は限られます。
信頼できるつながりを築くことで紹介や協業の機会が生まれ、経営の安定と成長につながるのです。
本記事では「司法書士の人脈」をテーマに、なぜ大切なのか、どう作り、どのように育てるか、そして注意点までを解説します。
司法書士にとって人脈が大切な理由

司法書士として独立すると、信頼できる人脈を通じた紹介こそが、案件獲得の鍵になるもの。
司法書士にとって人脈が大切な理由として、以下が挙げられます。
- 仕事の紹介につながるから
- 紹介の方が成約率向上やリピートに繋がりやすいから
- 協業・連携により幅広い案件に対応できるようになるから
- 人脈が司法書士としてのキャリアの安定と成長を支えてくれるから
ここからは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
仕事の紹介につながるから
人脈を通じた紹介があると、新規案件の発生率は上がります。
独立後、「案件が思ったより来ない」と悩む司法書士は多いものです。
しかし、待っているだけでは依頼者は来ないというのは当然のこと。
実際、司法書士の仕事は顧客が自分で検索して依頼するケースだけでなく、人脈からの紹介で依頼が舞い込むことがよくあります。
たとえば、相続や会社設立の相談者がまず他士業(税理士や弁護士など)に連絡し、そこで「信頼できる司法書士がいる」と紹介されることで案件に繋がることが多いのです。
資格や知識を持っているだけでは依頼は自動的に増えないため、信頼できる人とのつながりが仕事の入り口を広げます。
専門性だけで完結せず、「誰と組むか」「誰から紹介されるか」が業務拡大のカギとなる点をまず押さえておきましょう。
紹介の方が成約率向上やリピートに繋がりやすいから
広告やWeb経由で初めて知り合う顧客に比べ、紹介を通じて来た顧客は成約率が高く、リピートにもつながりやすいとされています。
こうした状態は紹介者が「この司法書士なら安心だ」と保証してくれるため、初対面でも顧客側に信頼感が生まれて、起こるのです。
いわば「信頼の連鎖」によって、紹介元の信用がそのまま司法書士にも移った状態。
したがって、スムーズに契約まで進みます。
たとえば、過去にあなたに依頼した顧客が、知人にあなたを推薦した場合。
知人は既に、元の依頼客からあなたの評価や実績を聞いているので、安心して相談できます。
紹介した側の信用にも関わるため、司法書士も「期待に応えよう」と、より丁寧に対応するでしょう。
このように紹介のネットワークから来た案件は、お互いの信頼関係を土台にしているため契約成立もしやすく、長期的なお付き合いに発展しやすいのです。
ドットアンドノードでは、司法書士事務所向けにSEO対策やWeb広告運用を支援し、紹介と並ぶ「もう一つの入り口」を強化するサービスも提供しています。
紹介ネットワークによる集客力に加えて、Webマーケティングの力も併用することで、より安定した案件獲得が可能になります。
協業・連携により幅広い案件に対応できるようになるから
人脈は単に「案件を紹介してもらう」だけでなく、他士業との協業によって提供できるサービスの幅を広げることにも直結します。
たとえば相続案件では、司法書士だけでなく弁護士・税理士・不動産業者など複数の専門家の知見が必要になる場合があります。
日頃から他士業と連携できる人脈があれば、ワンストップで顧客の課題を解決できるチームを編成しやすくなるもの。
異なる専門家同士が連携することで業務を同時並行で進められ、顧客の満足度が高まるというメリットもあります。
たとえば、会社設立の場面で税理士が経理面を、司法書士が登記をそれぞれ担当すれば手続きが迅速に完了し、依頼者の手間と時間を大幅に減らせます。
このように、専門家同士の協業は「1+1が3にもなる」というような付加価値を生み、顧客満足度向上につながります。
司法書士にとって人脈は、自分一人では対応しきれない幅広い案件にも対応できる力の源泉。
他士業ネットワークを築くことで、自事務所の提供価値そのものを高めることができるのです。
人脈が司法書士としてのキャリアの安定と成長を支えてくれるから
人脈は単なる案件獲得の手段ではありません。
司法書士としての長期的なキャリア形成を支える基盤でもあります。
信頼できる先輩や仲間とのつながりからは、新たな知識や実務ノウハウを学ぶ機会が得られるものです。
たとえば、先輩司法書士に業務上の疑問を相談してアドバイスをもらったり。
ほかにも、同業の仲間から最新の業界動向を共有してもらったりと、人脈を通じて、一人では得られない情報や知恵を吸収できます。
また、人脈がきっかけで新しい分野の案件に挑戦するチャンスを得ることもあります。
たとえば司法書士仲間から「一緒に新サービスを立ち上げないか」と声がかかれば、自分だけでは踏み出せなかった領域へ踏み出すこともできるのです。
さらに、心配事や経営上の悩みを相談できる「同志」がいることは、精神的な支えにもなります。
先輩や同業者の助言のおかげでピンチを切り抜けた経験を持つ司法書士も多く、「人脈は案件・学び・相談相手という三つの価値を同時に生む」ものといえます。
長い目で見れば、人脈こそが司法書士としての安定と成長を支える土台ともなるのです。
司法書士が人脈を広げる方法

具体的に司法書士が人脈を広げていく方法は、次のとおりです。
- 同業者ネットワークを活用する
- 他士業との接点を持つ
- 協業や連携しやすい業界のビジネスパーソンと接点を持つ
- 地方自治体の相談員に登録する
- 法テラスや消費生活センターに協力する
- NPO・市民団体に協力する
- SNSで自ら情報発信を行う
- 地域イベントやセミナーに参加・協力する
- 異業種交流会に参加する
- 経営者コミュニティに参加する
人脈形成のポイントは「適切な場に足を運び、出会いを増やし、縁を継続的に育てること」です。
以下からは、司法書士が人脈を広げるための具体的な方法を紹介します。
同業者ネットワークを活用する
まずは司法書士同士の横のつながりを強化しましょう。
司法書士会が主催する研修会や勉強会、懇親会は絶好の交流の場です。
そうした会合には積極的に参加し、同期や先輩司法書士と名刺交換をしてみてください。
交換した名刺は渡しっぱなしにせず、後日SNSでつながって関係を維持するのもポイントです。
「○○研修でお会いしました○○です。本日はありがとうございました」といったメッセージを送っておけば、相手の記憶にも残りやすくなります。
司法書士同士が繋がっていると、業務の情報交換ができるのはもちろん、場合によっては他の司法書士から仕事を紹介し合うこともあります。
たとえば自分が手が回らない案件を信頼できる仲間に振ったり、逆に仲間から業務を手伝ってほしいと依頼されたりすることもあるでしょう。
普段から顔見知りになっておくことで、「ちょっと教えてほしい」「一緒に対応しよう」と声を掛け合える関係が築けます。
同業ネットワークは孤独になりがちな個人事務所経営の支えにもなるため、ぜひ活用してください。
他士業との接点を持つ
司法書士にとって、弁護士・税理士・行政書士など他士業とのネットワークは顧客紹介や協業の宝庫です。
他士業と知り合うきっかけとしては、異業種交流会や専門家向けセミナー、地域の士業連絡会などがあります。
たとえば地元の商工会議所が主催する合同勉強会に参加すれば、さまざまな士業の先生方と名刺交換できます。
その際、「私は相続登記を専門にしています。先生のクライアントで相続手続きが必要な方がいたらご相談ください」というように、共通の顧客ニーズを意識した自己紹介を心がけると良いでしょう。
大切なのは、お互いの業務領域でメリットを感じられる役割分担を意識することです。
「登記は私が担当しますので、税務の検討が必要な際はぜひ○○先生にお願いしたいです」という具合に話せば、相手も安心して協力関係を築けます。
他士業との接点づくりは一朝一夕には成果が出ないかもしれません。
しかしながら、信頼関係ができれば、顧客を紹介し合える「Win-Winの関係」が生まれます。
ぜひ、積極的にさまざまな士業との交流にチャレンジしてみてください。
協業や連携しやすい業界のビジネスパーソンと接点を持つ
司法書士と相性が良く、協業・連携によって案件獲得につながりやすい業種が次のとおりです。
- 不動産
- 金融(銀行・信用金庫)
- IT
- 保険
- 葬儀
- M&A
- コンサル
意識的にそうした業界の方々と繋がりを持つことで、仕事の幅を広げるチャンスが増えます。
以下から、司法書士と特に親和性が高い業界別にメリットや関係構築のコツを詳しく紹介します。
不動産
不動産業界は、司法書士との協業機会が多い代表的な業種です。
土地建物の売買や抵当権設定では必ず登記手続きが伴うため、不動産会社や宅建業者は司法書士を必要とします。
メリットとして、不動産会社から物件売買のお客様を紹介してもらい、売買契約に伴う所有権移転登記を任されるケースが起こりやすいことが挙げられます。
また逆に、自分の依頼者が不動産の売却先や物件管理会社を探している際に、不動産業者を紹介してあげることで感謝され、関係が深まることも。
接点を作るには、地元の不動産業者の勉強会や交流会に参加してみましょう。
最近では、司法書士を招いた不動産取引のセミナーなども開催されています。
名刺交換した後は、「何か不動産案件でお役に立てることがあればいつでもご相談ください」と一言添えると印象に残ります。
不動産会社とは継続的なやり取りが大事。
取引がなくても新年の挨拶や情報提供の連絡をするなど、小まめなコミュニケーションで関係を深めていきましょう。
金融(銀行・信用金庫)
銀行や信用金庫など金融機関も司法書士にとって重要な協業先です。
住宅ローンや事業融資の実行時には抵当権設定登記が必要になるため、金融機関から司法書士へ業務依頼が発生します。
金融機関と繋がるメリットは、継続的に登記案件を紹介してもらえる可能性があることです。
特に地元密着の信用金庫などは地域の中小企業や個人と強い繋がりがあり、相続や事業承継の相談が持ち込まれることもあります。
その際に信頼できる司法書士を紹介したいと考えるため、ネットワークに入っておく価値は大きいです。
接点を持つ方法としては、地方銀行・信金が主催する経営者向けセミナーや交流会に参加することが考えられます。
融資担当者や支店長クラスと名刺交換する機会があれば、「融資案件で登記が必要な際はぜひお声がけください」と自己アピールしてみましょう。
ポイントは、信用第一の金融マンに対して誠実で堅実な人柄を示すことです。
約束を守る、報告連絡をしっかり行うなど基本を徹底し、小さな依頼でも迅速丁寧に対応すれば、「この先生なら安心だ」と評価され、継続的なお付き合いにつながります。
IT
一見すると司法書士とIT業界は接点が薄そうですが、IT業界の人脈も近年は要注目です。
IT企業はスタートアップや新サービス立ち上げに伴う会社設立や増資・組織変更など「登記ニーズ」があります。
また、知的財産の管理や利用規約の法務相談で弁護士とも連携が必要になることから、総合的な士業のネットワークを必要としていることも。
司法書士がIT業界と繋がるメリットは、ベンチャー企業から継続的な商業登記の依頼を得られる可能性があることです。
実際、新規に会社を起こすIT起業家にとって、司法書士は会社設立時から株主総会議事録の作成、登記変更まで長く付き合える頼もしいパートナーとなり得ます。
接点を作るには、地元のIT関連勉強会や起業家コミュニティに顔を出すなどがおすすめ。
最近ではコワーキングスペースで開催されるスタートアップ向けイベントなどもあり、専門外の分野であっても、新鮮な出会いが期待できます。
名刺交換時には「ITベンチャーの法務サポート経験があります」と自己PRできる実績があると理想的です。
無くても、「会社設立や登記でお手伝いできますのでお気軽に」と伝えつつ、SNSでフォローして情報発信を追うなど、関係構築に努めましょう。
保険
保険業界も、司法書士と協力関係を築きやすい分野です。
生命保険会社や損害保険会社の営業パーソンは日々個人・法人問わず多くのお客様と接しています。
その中で相続対策や事業承継、財産管理の相談が出た際、司法書士の出番が生まれます。
たとえば、顧客が「遺言を書いておきたい」「家族信託に興味がある」と保険営業に相談すれば、営業担当者は信頼できる司法書士を紹介したいと考えるもの。
逆に司法書士側から見ても、遺言執行や信託設定の際に保険商品を活用する提案ができれば、保険営業にとってもメリットがありWin-Winです。
接点作りには、保険会社主催の勉強会(FP向けや保険営業向けのセミナーなど)にゲスト参加させてもらう方法があります。
また知り合いに保険営業の方がいたら、「相続や信託の話が出たら力になれます」と伝えておきましょう。
コツは、お互いの営業を手伝う意識を持つことです。
司法書士が保険を直接販売するわけにはいきませんが、たとえば遺産分割の相談者に「生命保険を活用する方法もありますよ」と助言すれば保険営業につなげられます。
そうした協力姿勢を普段から示しておけば、逆に保険側から法務相談の顧客を紹介してもらえる関係になっていきます。
葬儀
葬儀業界とも人脈を持っておくと、相続関連業務でプラスになります。
葬儀社は故人が亡くなった直後のご遺族と接するため、当然ながら相続手続き全般の相談を受ける機会が多くあります。
信頼できる司法書士を知っていれば、「相続登記や遺産整理は専門家を紹介できます」とご遺族に提案可能。
葬儀社側も、サービス品質を高められます。
司法書士にとっては、葬儀社からの紹介で相続登記や相続放棄の手続きなどタイムリーな案件を獲得できるチャンスです。
接点を作る方法としては、地域の葬祭業者組合のイベントなどに参加するなど。
また、個別に地元の葬儀社に飛び込みで挨拶に行き「司法書士ですが、相続手続きでお困りの遺族の方がいたらお役に立てます」と営業するのも手です。
ポイントは、葬儀直後の遺族対応に慣れていることをアピールすること。
たとえば過去に相続相談会で遺族対応をした経験があれば伝えると安心感につながります。
葬儀社とは頻繁に会う機会は多くないかもしれませんが、定期的に顔を出して「最近どうですか」と状況を聞くなどすると記憶に留まり、いざという時に声をかけてもらいやすくなります。
M&A
M&A業界は司法書士にとって新しい協業のチャンスがあります。
中小企業の事業承継が課題となる中、経営者がM&A仲介会社に相談する場面が増加しているのです。
株式譲渡契約の締結や役員変更登記など、司法書士が必要とされる法務手続きが数多く発生します。
M&A仲介会社にとっても、法務をスムーズに進められる司法書士とのネットワークはサービス向上につながるメリット。
司法書士にとってのメリットは、案件規模が大きく一件ごとの報酬も高額になりやすいこと。
さらに、継続的な関係構築が可能なことです。
株式譲渡登記や組織再編登記などは収益面でも有利です。
接点を作る方法としては、金融機関や商工会議所が開催する事業承継セミナーに参加すること。
そこで仲介業者やM&Aコンサルタントに「会社の譲渡に際して登記をサポートできます」と自己紹介しておけば、信頼を得られるきっかけになります。
M&A案件は頻繁ではありませんが、一度つながれば実績づくりや収益増につながるため、常にアンテナを張っておくことが大切です。
コンサル
経営コンサルタントや士業系コンサル会社とのネットワークも、司法書士にとって有益です。
経営コンサルタントは企業のさまざまな課題解決を支援しますが、その中に法務・登記に関する事項が含まれることがあります。
たとえば「株主構成を変更してガバナンス強化を図りたい」という相談があれば、司法書士の商業登記の出番です。
また、相続コンサルタントが高齢の個人顧客に遺言や家族信託を提案する際にも司法書士との協業が考えられます。
コンサル業界と繋がるメリットは、課題解決型の案件を継続して紹介してもらえる可能性があることです。
コンサルタントは常に顧客の課題を探っているため、その解決策として信頼できる司法書士を求めることがあるのです。
接点を作るには、異業種交流会や経営者コミュニティで積極的にコンサル職の人と会話してみましょう。
「専門は司法書士ですが、経営課題の法務面でお役に立てることがあるかもしれません」といった切り口で自己紹介すると興味を持ってもらえるかもしれません。
コンサルタントは成果主義でビジネスをしていることが多いので、自分の専門領域でどんな価値が提供できるかを具体的に伝えることが大切です。
「事業承継なら家族信託の組成支援ができます」など、相手のサービスを補完できるポイントを示し、良きパートナーとして覚えてもらいましょう。
地方自治体の相談員に登録する
自治体が開催する法律相談会や登記相談窓口に協力することも、人脈拡大につながる方法です。
多くの市区町村では定期的に無料相談会を実施しており、司法書士会から相談員を派遣しています。
こうした相談員として参加すると、地域住民から直接相談を受ける中で自分の存在をPRできます。
さらに、一緒に運営に携わる行政職員や地元NPOスタッフなどとも顔見知りになり、人脈が広がるのです。
地方自治体の相談員登録をするのであれば、所属司法書士会に問い合わせましょう。
公的な場に協力することは社会貢献にもなり、「地域の頼れる司法書士」という信頼感をつくることにもつながります。
実際に相談会で知り合った方から後日正式に依頼を受けるケースや、自治体職員から「この件は○○先生に相談してみては」と住民を紹介されるケースもあります。
地道な取り組みですが、地域に根差した人脈づくりとして検討してみてください。
法テラスや消費生活センターに協力する
日本司法支援センター(法テラス)や各地の消費生活センターと連携するのも、人脈を広げる方法です。
法テラスでは法律専門家による相談業務を行っています。
司法書士も、民事法律扶助契約を結べば相談員として活動できます。
また、消費生活センターが開催する多重債務や悪徳商法に関する相談会に、司法書士が協力者として参加することも。
諸団体に関わることで、同じ場に集まる弁護士・行政書士・地方自治体職員などと知り合える利点があるのです。
たとえば法テラスの連携会議に出席すれば、裁判所職員や市役所担当者とも情報交換できます。
実際に、ある司法書士は消費者被害防止の勉強会での縁から、後に行政書士や警察OBと協力して高齢者向けセミナーを開催する機会を得ました。
最初は小さな接点でも、そこから相談案件にすぐ対応し、紹介元に信頼を返すことで、持続的な関係に発展します。
公共性の高い機関との連携は社会的信用も得られます。
余裕があれば、ぜひ協力してみてください。
NPO・市民団体に協力する
地域のNPO法人や市民活動団体と繋がることも、人脈形成のためにおすすめです。
たとえば高齢者の見守り活動をするNPOや、空き家対策を進める市民団体など、司法書士の知識が活かせそうな分野は多々あります。
そうした団体が主催する、地域相談会や市民セミナーにボランティア参加してみましょう。
初めは顔を覚えてもらうことが入口。
継続して協力するうちに、団体の職員や他の協力士業と親しくなれます。
そして、活動を通じて知り合った方から個別の案件相談を受け、「ぜひお願いしたい」と依頼につながるケースもあります。
たとえばある司法書士は、地域の空き家問題のワークショップに専門家ボランティアとして参加し、後日主催NPOの紹介で相続登記の依頼を複数受けたそうです。
重要なのは依頼人に寄り添った対応を繰り返し、「安心して任せられる司法書士」という評判を築くことです。
NPO職員や団体代表から「あの先生なら大丈夫」と太鼓判を押してもらえれば、地域内での信用力が増し、新たな紹介にもつながっていきます。
SNSで自ら情報発信を行う
現代においては、SNSでの情報発信も人脈を広げる重要な手段です。
たとえば、TwitterやFacebook、LinkedInなどを活用して自分の専門分野に関する有益な情報を発信するなど。
ネット上での認知度が高まり、同業者や他業種の人から声がかかるきっかけになります。
特にFacebookは実名登録のため信頼性が高く、士業同士の交流にもよく使われています。
実際に会った方とFacebookでつながっておけば、SNS上で近況を知ることができ、関係が途切れにくくなる利点も。
また、Twitterでは専門知識や判例解説などを呟くことでフォロワーを増やすことが可能。
自分から話しかけなくても相手から「投稿拝見しています、一度お話しませんか」と連絡をもらえることもあります。
注意点として、SNSでは専門家としての信用を損なわないよう発言内容に気を付ける必要があることが挙げられます。
顧客のプライバシーに触れる内容や、誤解を招く軽率な発言は厳禁です。
SNSは拡散力が強いため、一度不適切な投稿をすると信用を大きく傷つけかねません。
発信する内容は専門的で有益なものに絞りつつ、時折人柄が伝わるエピソードも交えると親しみやすさが生まれます。
SNSを上手に活用して自分の存在感を高め、人脈形成につなげていきましょう。
地域イベントやセミナーに参加・協力する
地元のイベントやセミナーに顔を出すことも、幅広い人脈づくりのためにおすすめです。
地域の商店街イベント、異業種が集まる講演会、防災訓練など、一見業務と関係なさそうな場でも、人との出会いのチャンスはあります。
特に地域密着で活動する司法書士にとって、地元で顔が売れることは信頼の獲得につながります。
「あのイベントを手伝っていた司法書士さんね」というように覚えてもらえれば、後日思わぬ相談が舞い込むこともあるのです。
可能であれば、地域の法律相談セミナーを自ら企画して開催するのもおすすめ。
自治体や公民館と協力して「相続・遺言セミナー」などを開けば、参加者とのネットワークづくりと同時に地域貢献による信頼度アップが図れます。
重要なのは、イベント参加をきっかけに終わらせず、その後も継続して関係を育むことです。
出会った方には御礼のメールを送り、できれば次の機会も作るよう心掛けましょう。
異業種交流会に参加する
司法書士は、他業種とのネットワークで仕事を呼び込むこともあります。
そのために手軽で効果的なのが、異業種交流会への参加です。
異業種交流会ではさまざまな業界の経営者・士業・営業職などが集まり、名刺交換や情報交換が行われます。
参加する際は、業界や参加者層が自分の目的に合った会を選ぶとよいでしょう。
たとえば「経営者限定交流会」であれば会社経営者との縁が期待できます。
「若手起業家交流会」なら、スタートアップ、ベンチャーとの繋がりが作れます。
交流会では積極的に話しかけ、自分の仕事についても簡潔にアピールしましょう。
ただし営業色を出しすぎると敬遠されるので、「何かあればお役に立てるかもしれません」程度にとどめておくのがポイントです。
懇親会で連絡先を交換した後は、SNSでのつながりや後日の一対一の面談につなげるなどフォローアップが肝心です。
異業種交流会は短時間で多くの出会いが得られる反面、一度きりで終わりやすいもの。
したがって、後日のお礼メールや次回会う約束を取り付けるなど工夫して関係を深めていきましょう。
経営者コミュニティに参加する
地元の経営者コミュニティや勉強会に参加するのも、人脈拡大のためにおすすめな手段です。
商工会議所青年部(YEG)やライオンズクラブ、ロータリークラブなど、地域の経営者が集う団体に入会すれば、継続的に顔を合わせる仲間ができます。
こうしたコミュニティではビジネスの紹介だけでなく、人間関係の構築が重視されるため、長期的なお付き合いの中で信用を得ることが可能です。
「同じ釜の飯を食った仲間」として認識されれば、いざ困ったときに真っ先に相談相手に選んでもらえるでしょう。
参加するメリットは、直接の顧客紹介に加えて、経営者としての視野が広がることにもあります。
さまざまな業種の成功者から刺激を受けることで、自身の事務所経営にもプラスになるのです。
経営者コミュニティに参加する際は、ビジネスマナーや社会常識を改めて意識し、信用を積み重ねていくことが大切。
地道な努力の先に、「困ったときは○○司法書士に相談してみよう」という強固な人脈が築かれるわけです。
司法書士が人脈を広げる上で意識すべきポイント

人脈は広げれば広げるほど良いものです。
人脈づくりの過程では、常に次の点を意識しておくべきです。
- 「まず与える(GIVE)」の姿勢で動く
- 短期的な成果を求めない
- 第一印象や会話でマイナスイメージを与えないように気を付ける
- 人脈の質を定期的に精査する
どんなに出会いの場に足を運んでも、付き合い方を間違えるとかえって信頼を損ねる恐れがあります。
ここからは、人脈作りを進める上で特に重要な心得を解説します。
「まず与える(GIVE)」の姿勢で動く
人脈を育てるうえで最初に意識すべきは、「自分からまず相手に与える」という姿勢です。
得たいもの(仕事の紹介など)があって人脈作りをするわけですが、最初から欲を前面に出してしまうと相手は身構えてしまいます。
そうではなく、相手の立場やニーズをよく理解し、役に立つ情報や小さなアドバイスでも惜しまず提供することから始めましょう。
大げさなことでなくても、「それなら○○を参考にされると良いですよ」と資料を送ったり、別の専門家を紹介したりといった気遣いで十分です。
人脈作りはよく「信用の貯金」に例えられます。
日頃からこちらが積み立て(Give)をしておけば、いざ自分が助けてほしいときに引き出し(Take)できるという考え方です。
反対に、最初から自分の利益ばかり求めていると相手に見透かされ、関係は長続きしません。
Giveの精神で信頼の土台作りに徹した結果、巡り巡って紹介や協業の話が舞い込めばいいかも、くらいの長期目線で人脈と向き合いましょう。
短期的な成果を求めない
人脈作りにおいて、短期的な成果を過度に求めすぎないことも重要です。
初めて会った人から即座に仕事の紹介がもらえるわけではありません。
仮に一度紹介を受けても、それだけで安定した人脈になったとはいえません。
人間関係は、時間をかけてつくりあげるものです。
一度会っただけではまだ「知り合い」にすぎません。
何度も連絡を取り合ったり情報交換をしたりするうちに「仲間」へと変わっていくのです。
たとえば名刺交換後にお礼メールを送り、数ヶ月後に「その後いかがですか」と近況報告をするというような、小さな接点を積み重ねましょう。
「年単位での継続接触」が結果的に安定した紹介ルートを生むと意識しておきましょう。
焦るあまり、初対面ですぐ「お仕事ください」と迫るような態度は禁物です。
それでは相手に「この人は自分を利用しようとしているのでは?」という警戒心を与えてしまうだけです。
人脈作りは、マラソンのようなものです。
短期の成果に一喜一憂せず、腰を据えて関係を育てる発想で取り組みましょう。
短期志向で相手に接すると、知らず知らず「テイカー」や「狩人」のような貪欲さが出てしまい、人が離れていく原因になります。
第一印象や会話でマイナスイメージを与えないように気を付ける
人脈作りでは、第一印象が非常に大切です。
一度悪い印象を持たれてしまうと、その後いくら挽回しようとしても関係構築が難しくなるからです。
初対面の場面では、服装や挨拶、名刺交換の所作から会話の内容・態度に至るまで、細心の注意を払いましょう。
服装は清潔感のあるビジネスカジュアルないしスーツで臨み、名刺は切らさず用意しておくべき。
名刺交換の際は笑顔で相手の目を見て、はっきりと名乗りましょう。
会話では自分が話しすぎないよう注意し、相手の話にしっかり耳を傾けることを意識してください。
人は、自分の話を熱心に聞いてくれる相手に好感を持つものです。
逆に、自慢話ばかりしたり専門用語をひけらかしたりすると敬遠されます。
また、初対面でいきなり馴れ馴れしすぎるのも禁物です。
ビジネスマナーに則った丁寧な言葉遣いと礼儀を心掛け、適度な距離感を保ちましょう。
小さな所作ではありますが、確実な礼儀が積み重なって、あなたの印象を形作ります。
最初に与える印象が、今後の相談や紹介の可能性を左右するといっても過言ではありません。
特に士業は「信頼感」が命です。
初対面の瞬間からプロフェッショナルとしての振る舞いを徹底しましょう。
人脈の質を定期的に精査する
人脈を広げた後は、得られた人脈の質を定期的に振り返り、健全性を保つことも忘れてはいけません。
ただ数が多ければ良いというものではなく、自分にとってプラスになる繋がりかどうか、相手にとって役立てているかをチェックする必要があります。
具体的には、半年や一年に一度くらいの頻度で以下の点を数値で確認しましょう。
| 確認項目 | 内容 | 注意点・改善視点 |
|---|---|---|
| 紹介からの成約率 | 人脈経由で紹介された案件のうち、どの程度を受任・成約できているか | 極端に低い場合は、紹介の流れに問題がある可能性がある |
| 紹介案件でのトラブル率 | 紹介経由の顧客との間でクレームやトラブルが起きていないか | 頻発する場合は、依頼前の期待値調整や対応品質に課題がある可能性がある |
| 相互紹介のバランス | 自分ばかりが紹介を受けていないか、逆に自分ばかり紹介して負担になっていないか | Win-Winの関係になっているかを定期的に見直す必要がある |
こうした定量的な指標を持ってチェックすると、人脈の健全性を客観的に把握できます。
もし偏りや問題が見られたら、原因を探って対策しましょう。
たとえば特定の紹介者からの案件が成約に至りにくいなら、一度打ち合わせをして、お互いの顧客ニーズのすり合わせをした方が良いことも。
人脈は放置すると、質が劣化してしまうこともあります。
定期的に関係を確かめ、より良い関係を築けるようアップデートしていく意識が大切です。
司法書士が陥りやすい人脈作りの落とし穴

人脈を広げる一方で、やり方を誤ると陥ってしまう落とし穴も次のように存在します。
- 人脈づくりに時間をかけすぎて本業が疎かになる
- 一方的・依存的な関係性を築いてしまう
- 紹介料や報酬など金銭の取り決めを口で行う
- SNSでの不用意な発言で信用を失う
- 無理な営業をして人から避けられるようになる
ここからは、司法書士が人脈作りで陥りがちな失敗パターンを挙げ、対策や注意点を解説します。
人脈づくりに時間をかけすぎて本業が疎かになる
人脈を広げようとするあまり、交流会や会合に出ずっぱりで肝心の本業がおろそかになるケースがあります。
確かに人的ネットワークは大切です。
しかし、本業が止まってしまうような事態に陥ってしまっては意味がありません。
毎日のように懇親会に参加して疲弊し、肝心の依頼業務の処理が滞ってしまっては、本末転倒です。
こうした失敗を防ぐには、参加する場を選び、目的を決めてから動くことが重要です。
なんとなく誘われるまま毎回顔を出すのではなく、「今日は税理士との関係構築が目的」といった具体的な目標意識を持って参加しましょう。
また、スケジュール管理も徹底しましょう。
週に何回まで交流会に出るかルールを決め、残りの時間はしっかり業務に充てるなど、バランスを取った行動を心掛けてください。
さらに、SNS利用にも注意が必要です。
SNSは人脈づくりに有用な一方、夢中になりすぎると時間を奪われます。
SNS閲覧や投稿の時間を決め、業務に支障が出ない範囲で節度を保ちましょう。
人脈作りは大事ですが、「本業あっての人脈」であることを常に念頭に置き、優先順位を見失わないようにしましょう。
一方的・依存的な関係性を築いてしまう
人脈形成でありがちな失敗に、一方的あるいは依存的な関係に陥ってしまうことが挙げられます。
具体的には、「紹介してください」と自分が頼むばかりで相手には何も返さないケース、逆に相手からの頼みを断れず常に下請けのような立場になってしまうケースなどです。
どちらも健全とはいえず、長期的には関係が続きません。
重要なのは、お互いが利益を得られる対等なつながりを意識することです。
相手から紹介をもらったら、自分からも何かしら紹介や情報提供で返す努力をしましょう。
もし自分ばかり紹介を受けているなら、「私からもぜひ先生に合いそうなお客様をご紹介させてください」と提案してみてください。
それでもあまりにバランスが悪い場合は、その関係自体を見直す勇気も必要。
また、相手に頼られすぎて負担に感じる場合は、正直にキャパシティを伝え調整することも大切です。
双方が負担なく、メリットを享受できる関係こそ長続きします。
一方通行になっていないか常に気を配り、Win-Winのネットワークを築きましょう。
紹介先との契約前の事前合意が大事!
他士業や業者と案件をやり取りする際には、事前の取り決めを明確にしておくことが不可欠です。
たとえば、共同で受ける案件で「どの範囲まで誰が担当するのか」「情報共有の方法」「守秘義務の範囲」「万一利益相反が生じた場合の対応」など、あらかじめ文書で合意しておくべき事項は多くあります。
特に紹介手数料(紹介料)や報酬配分に関する取り決めは注意が必要です。
口頭で「報酬の○%を紹介料として渡します」などと決めただけでは、後で計算方法やタイミングの認識違いによる揉め事が起こりやすくなります。
そうならないよう、契約書や合意書でお互いの認識をすり合わせ、曖昧な表現を避けることが大切です。
紹介料や報酬など金銭の取り決めを口で行う
紹介料や報酬配分を口頭だけで済ませてしまうのは、先にもあったようにリスクが高いものです。
人脈で繋がった相手とは「信頼関係があるから大丈夫」と思いがち。
しかし、お金が絡むとどんな間柄でもトラブルが起こり得ます。
実際、紹介手数料の支払いタイミングや計算方法について事前に明確にしておかず、後から「こんなはずではなかった」と揉めた例は少なくありません。
たとえば「売上の○%を紹介料にしましょう」とその場で合意しても、売上の定義(税抜か税込か、どの段階の売上か)が双方で食い違っていた…ということも起こり得ます。
また、一度の紹介に対して将来発生した追加取引にも紹介料が必要かどうか等、細部を詰めておかないと後で関係が悪化しかねません。
こうしたお金の話こそ文書化が鉄則です。
互いに角を立てないためにも、「念のため契約書を交わしましょう」と提案するのはプロとして当然の行為です。
万一口約束で進めてしまった場合でも、後からメール等で合意内容を確認し記録に残すようにしましょう。
「金の切れ目が縁の切れ目」とならないよう、金銭面の取り決めはシビアなくらいきっちりやるのが、長く良好な人脈を維持するコツです。
SNSでの不用意な発言で信用を失う
SNSは人脈形成に便利な一方、使い方を誤ると信用を一瞬で失いかねない両刃の剣です。
実名で活動する司法書士にとって、「SNS上の発言は常に世間から見られている」という自覚が必要です。
たとえば、顧客に関することを匂わせる投稿や、特定の個人・団体を批判するような発言は絶対に避けましょう。
守秘義務に抵触する情報などを発信してしまうのは、論外です。
また、法律解釈等について断片的な投稿が誤解を招き、炎上してしまうケースもあります。
かつて、ある士業の関係者がSNSで不用意に専門外の政治的意見を述べたところ、それが拡散され依頼者からの信頼を失った例もあります。
SNS上では専門家としての品位と中立性を意識し、不確かな情報は発信しない、自分の発言に責任を持つといった基本を守りましょう。
さらに、コメント欄でのやり取りも要注意です。
感情的な応酬になれば、あなただけでなく、事務所全体のイメージダウンに直結します。
オンライン上でもオフラインと同様に節度ある対応を心掛け、常に「この投稿を見た人がどう感じるか」を想像してください。
SNSは便利なツールですが、専門家としての信頼を損なわないよう細心の注意を払って活用しましょう。
無理な営業をして人から避けられるようになる
人脈を増やそうとするあまり、出会ってすぐに仕事の話ばかり持ち出してしまうのも大きな落とし穴です。
交流会などで名刺交換して間もない相手に「何か案件ありませんか?」と詰め寄ったり、自分のサービスを長々と売り込んだりすると、相手は引いてしまいます。
いわばガツガツしすぎる営業は逆効果で、人が離れていく原因になります。
大切なのは、まず人として信頼関係を築くことです。
すぐに案件を紹介してもらおうと焦らず、雑談や情報交換を通じて相手との共通点を見つけたり、お互いのビジネス観を共有したりすることに注力しましょう。
そうする中で、「この人とまた話したいな」「一緒に仕事しても良さそうだな」と感じてもらえれば自然と次のステップに進みます。
一度会っただけで案件をせがむような態度は、相手に「利用されそうだ」と警戒心を抱かせ、人脈を築くどころか敬遠されてしまいます。
むしろこちらから相手にとって有益な人を紹介するくらいの余裕を持って接すると、「あの人は信用できる」という評価につながり、巡り巡って自分への案件紹介にもつながるもの。
「人脈作りは営業ではなく、信頼構築である」という基本に立ち返り、相手に寄り添ったコミュニケーションを心掛けてください。
人脈づくりと並行してマーケティングにも力を入れると安定する!

ここまで、人脈構築の重要性について述べてきました。
しかしながら、事務所の経営を人脈頼みだけにしないことも大切です。
司法書士が仕事を安定的に獲得するためには、人脈作りが基本ではあるものの、それ「だけ」に依存するのはリスクも伴います。
たとえば、リーマンショックやコロナ禍のように社会全体で案件が減少する局面では、人脈からの紹介も細ってしまう恐れがあります。
そのとき人脈一本頼みだと、売上減少をただ見守るしかなくなってしまいます。
一方で、人脈作りと並行して自分自身で新規顧客を開拓するマーケティングを実践しておけば、外部環境に左右されにくい安定した集客基盤を築けます。
具体的には、ホームページやブログを活用したSEO集客、Web広告の運用、チラシやDMによる地域マーケティングなど、人脈以外からも問い合わせが入る仕組みを持つことが重要です。
つまり、人脈が一時的に途切れたとしても集客がゼロになるリスクを軽減できるのです。
また、新規顧客との接点を増やすことで人脈自体も広がる好循環が生まれます。
要するに、「人脈+マーケティング」の二本柱で顧客獲得に取り組むことが、事務所経営を安定させるカギなのです。
司法書士の顧客獲得の仕組み構築事例

人脈以外のチャネルも取り入れて顧客獲得の仕組み化に成功した、次の司法書士事務所の事例を紹介します。
- 顧客獲得の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に増加
- Webからの集客の仕組みの構築により案件獲得が安定
- 紹介だけに頼らない案件獲得の流れの構築に成功
実際に自社でWeb集客の仕組みを構築することで、問い合わせ件数が大幅に増えたり、紹介だけに頼らない安定集客を実現した例があります。
それぞれのケースから学べるポイントを、以下から詳しく見てみましょう。
顧客獲得の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に増加
ある司法書士法人では、従来ホームページからの相談があっても、専門的すぎて実際の受任に繋がりにくい状況でした。
そこで発信内容を一般の方が知りたい相続の話題に切り替え、集客を仕組み化する取り組みを行ったところ、相談の質が向上し受任できる案件が増えたのです。
結果として、ホームページの月間閲覧数が2倍に増え、問い合わせ件数も1.5倍になりました。
具体的に事務所が行った工夫としては、「相続に関する記事を専門家として分かりやすく発信」「数千のキーワードから相談につながりやすいものを選定して記事に反映」「サイトのドメインパワーを強化し、制作会社から毎月改善点の報告を受ける」といった施策です。
以前は毎月30万円以上の広告費をかけても成果が出ず途中でやめた経験があったそうで。
しかしながら、月10万円の予算で相続専門のサイトを作り、広告も併用したところ施策開始6日目に早速問い合わせが入りました。
さらにその問い合わせは20万円の遺言書作成から遺産整理へと発展し、1件の相談が数十万円の売上になる成果も上がっています。
この事例からは、Web集客を戦略的に仕組み化することで、短期間で目に見える効果が出ること、そして専門特化した情報発信が、質の高い相談を呼び込むことにつながるのだと分かります。
ドットアンドノード株式会社導入事例「Web集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に」
Webからの集客の仕組みの構築により案件獲得が安定
荒俣政吉司法書士行政書士事務所では、紹介に頼らず自前で集客したいとの思いからWebマーケティングに本格的に取り組みました。
月額10万円の「繁盛司法書士パック」を導入して新しい集客専用サイトを立ち上げ、Web広告運用も開始。
すると、毎月3件ほどの安定した成約を獲得できるようになり、月によっては5~6件に増加しました。
現在では仕事の半分以上がホームページ経由で入ってきているとのこと。
まさに、紹介だけに頼らない集客体制の構築に成功しています。
特筆すべきは広告からの成約率が約80%と非常に高いことです。
問い合わせさえ入れば、ほとんど受任につながるといった状態です。
こうした状態は、Web広告で絞り込んだ見込み客を集め、信頼性の高い専用サイトで十分な情報提供をしているからこその成果。
また、同事務所では以前は旧来型のホームページ管理会社に月5万円を支払っていたものの、修正対応の遅さや不具合放置などで問い合わせが月1件あるかないかという状況でした。
それが現在ではサイト更新や不具合対応もすべて任せられ、司法書士業に集中できる環境が整ったとのこと。
もし古い体制のままだったら、問い合わせは増えず広告費と時間を無駄にしていただけです。
思い切って成果の出る形に変えたことで、少人数の事務所でも成功を掴んだわけです。
このケースから学べるのは、適切な投資とプロの力を借りてWeb集客を軌道に乗せれば、紹介がなくても十分案件を回せるようになるということです。
ドットアンドノード株式会社導入事例「案件の半分以上がホームページから成約するようになりました」
紹介だけに頼らない案件獲得の流れの構築に成功
最後に紹介するのは、静岡鉄道株式会社様(不動産・相続サポート事業部門)のケースです。
こちらは司法書士個人ではなく企業の新規事業ですが、人脈に頼らない集客フロー構築の好例です。
静岡鉄道様では、相続支援の新規事業立ち上げにあたり、当初「どのように見込み顧客と商談を作るか」について、はっきりした仕組みがありませんでした。
そこでドットアンドノードがサポートに入り、「Web広告→専用ホームページ→問い合わせフォーム」までの一連のオンライン集客動線を構築しました。
その結果、毎月4〜5件の問い合わせが安定的に入り、商談が1〜2件成立。
商談からはほぼ100%契約に至るという、理想的なフローが出来上がりました。
紹介ゼロからスタートした新事業でも、広告経由で確実に顧客接点を生み出し、定常的に契約を獲得できているのです。
さらに同社はWeb集客の成功を受けて広告費を増額し、立ち上げから5年間黒字を継続。
広告強化後には、3億円の売上となる大型案件も生まれたとのことで、大きな成果を上げています。
この事例は、人脈がなくても効果的なWebマーケティング施策によって十分案件を回収できることを示しています。
反対にいえば、人脈だけに頼っていては出会えなかったであろう大口案件も、オンライン施策によって掴み取ることができたといえるのです。
ドットアンドノード株式会社導入事例「安定的に業績が伸びるスキームができました」
人脈づくりと並行して顧客獲得の仕組みを構築しよう!

司法書士にとって人脈は案件獲得と信頼形成の土台です。
紹介や協業のネットワークを広げることは、単なる人間関係づくりではなく、事務所経営を支える基盤になります。
一方で、人脈だけに顧客獲得を依存してしまうのも望ましくありません。
景気変動や環境変化で、人脈からの案件が少なくなる可能性は常にあります。
安定的な案件獲得を実現するためには、人脈を広げるのと並行して自社で案件を獲得できる仕組みを構築しておくことが重要です。
人脈による紹介と自社集客の両輪が揃えば、多少環境が変わっても揺らがない、強固な営業基盤ができます。
ドットアンドノードでは、司法書士事務所の集客戦略立案からSEO・広告運用・営業支援まで、事務所の顧客獲得の仕組みづくりをトータルでサポートしています。
まずは、ぜひお気軽にお問い合わせください。