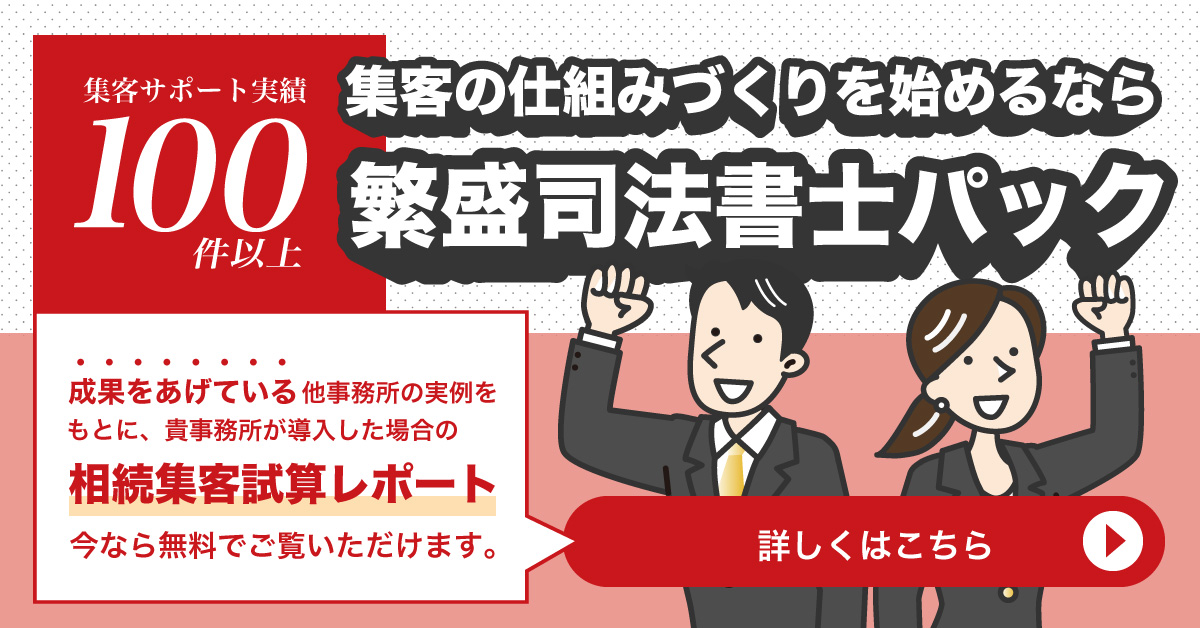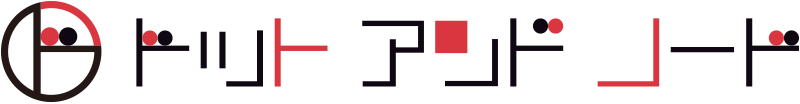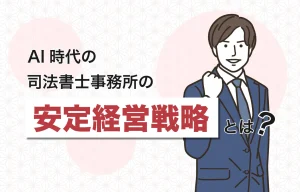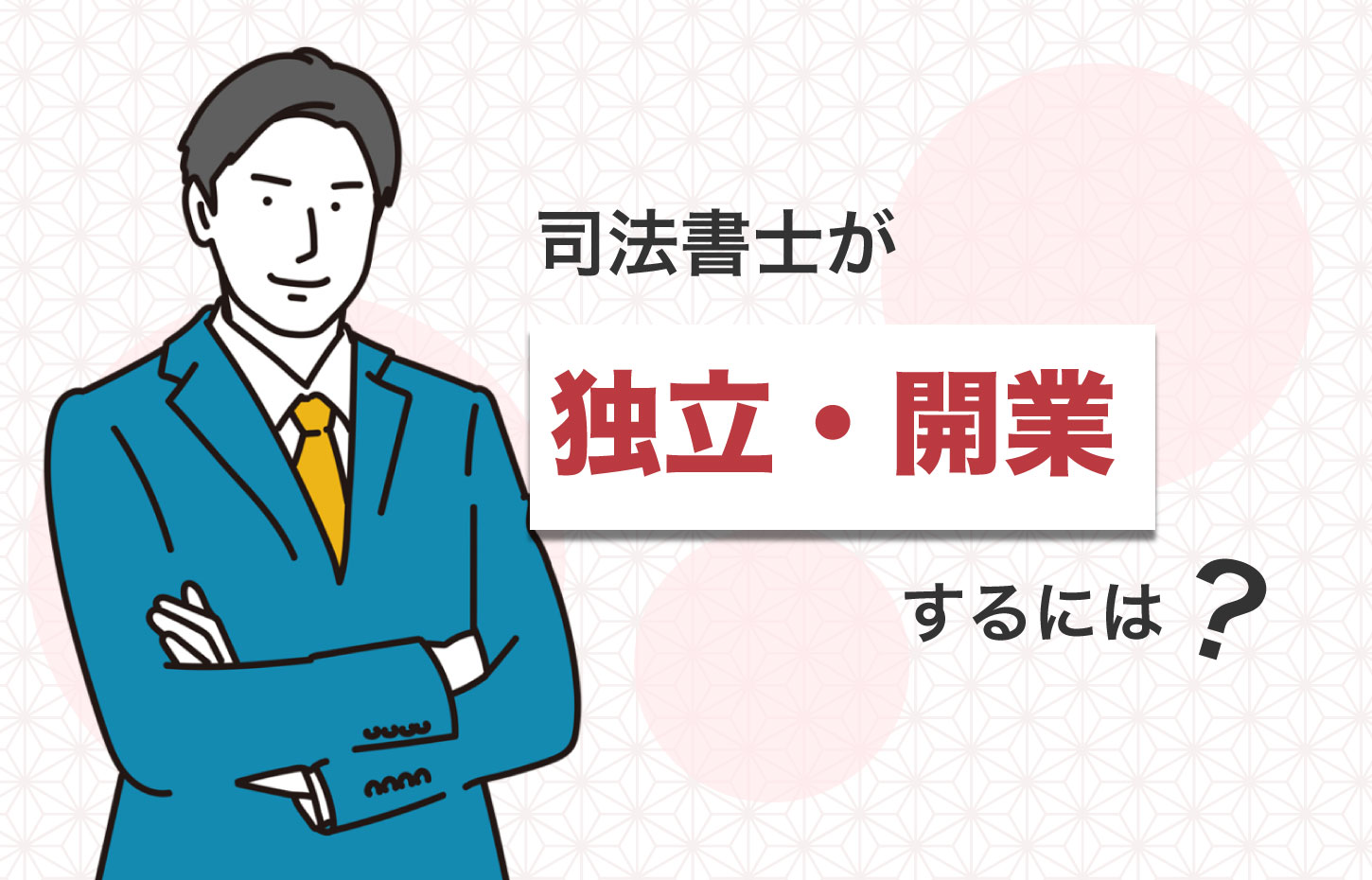
司法書士として独立開業するには?手順や成功させるためのポイントを解説
司法書士として働いていると「いつかは自分の事務所を持ちたい」と考えるもの。
しかし、実際に独立するには、お金の準備や人脈、集客の仕組みづくりなど、多くのことを考えなければなりません。
この記事では、司法書士が独立して開業するまでの手順や必要な費用、失敗しないための注意点、成功につなげるポイントなどを詳しく解説します。
司法書士が独立開業する前に確認すべきこと

司法書士の数は全国で2万3千人ほどいるといわれています。
資格を持っていれば独立できるため、毎年新しく事務所を開く方が出てきます。
需要が多い分野は「相続」「不動産登記」「会社設立」など。
特に相続は高齢化社会(年を取った人が増える社会)により、今後さらに相談が増えると見られています。
司法書士が独立して事務所を構える前には、準備しておくべき点がいくつかあります。
特に大切なのは次の3つです。
- 独立するタイミングは適切か
- 自己資金の準備はできているか
- 専門分野ははっきりしているか
以下からは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
独立するタイミングは適切か
司法書士としての実務経験が少ないうちに独立してしまうと、案件の処理やお客様対応に不安が残ります。
一般的には、資格を取ってから3〜5年ほど勤務して経験を積んだうえで独立するのが望ましいところ。
自分がどれくらいのスキルを持っているか、人脈は整っているかを振り返り、今が独立に最適な時期かどうかを冷静に判断する必要があります。
経験不足のまま独立すると、登記の手続きで誤りが出たり、顧客から信頼を得られなかったりして、仕事が続かなくなる危険もあります。
一方で、単純な登記手続きはオンライン化が進み、以前ほど件数が伸びにくいという声もあります。
そのため、ただ独立するだけでなく、自分が強みを出せる分野を早めに決めておくことが重要です。
自己資金の準備はできているか
独立開業には事務所を借りる費用、司法書士会への登録料、ホームページを作る費用など、数十万から数百万円の初期費用がかかります。
さらに開業直後は、安定して案件を受けられるとは限りません。
そのため、生活費と事務所運営の資金を半年から1年分ほど確保しておくことが安心につながります。
資金が足りない場合は、日本政策金融公庫の創業融資や補助金を検討するのも一つの方法です。
資金に余裕がないまま独立すると、案件が少ない時期に生活費が足りなくなり、廃業を迫られることもあるので注意が必要です。
専門分野ははっきりしているか
司法書士の業務は「不動産登記」「相続」「商業登記」など幅広いです。
ただし、独立直後からすべてに対応するのは難しいです。
まずは自分が得意とする分野や強みを持つ業務をはっきりさせておくことが重要。
専門性を打ち出すことで、初めての顧客からも信頼されやすくなり、他の司法書士との差別化にもつながります。
もし専門分野を決めないまま開業すると、「何を得意とする司法書士なのか分からない」と思われ、相談につながらない可能性があります。
司法書士事務所の開業手順

司法書士が開業する際には、基本的に次のステップで進めることになります。
- 司法書士としての実務経験を積む
- 独立開業に向けた事業計画を立てる
- 事務所や設備等の準備・契約をする
- 司法書士会への登録申請をする
- 人脈作り・営業を行う
ここからは、それぞれのステップですべきことや注意点を、順を追ってチェックしていきましょう。
1.司法書士としての実務経験を積む
司法書士の資格を取得したら、まずは既存の司法書士事務所に勤務して実務経験を積むことをおすすめします。
司法書士資格を取得しさえすれば、すぐにでも独立開業することは可能ですが、経験や知識なしで事務所を運営するのはかなり困難です。
目安としては3年程度、司法書士として経験を積み、業務の流れや事務所の運営に関する最低限のノウハウを理解してから独立に進みましょう。
2.独立開業に向けた事業計画を立てる
司法書士として実務経験を積み、いよいよ独立開業を現実的に考える段階に入ったら、事業計画と資金計画を立てます。
開業にあたって金融機関から融資を受ける場合、事業計画書の提出が必要です。
資金計画は、具体的な数字を盛り込み、いつごろにどれくらいの利益が出る見込みがあるかを明らかにします。
一人事務所かスタッフを雇うか
開業時に考えるべきこととして、「一人でやるか」「スタッフを雇うか」があります。
一人事務所なら固定費が少なく、自由に動けますが、案件が増えると手が回らなくなることがあります。
顧客対応や書類作成に追われ、休みが取れない状況になりがちです。
一方でスタッフを雇うと、案件が多くても分担でき、効率よく進められます。
ただし給料という固定費が増えるので、売上が安定していない時期に雇いすぎると資金が不足する危険もあります。
開業当初は一人で始め、案件が安定してからスタッフを雇うのが現実的な流れです。
3.事務所や設備等の準備・契約をする
事務所は、自分がメインターゲットとする顧客層にアクセスしやすい場所に設置するのがポイントです。
たとえば、法務局や銀行、不動産会社など関連施設が多いエリアや、特定の業種が多いエリアなどを見極めて事務所を設置すると、顧客との接触機会を増やしやすくなります。
事務所を開設するのに必要最低限な設備は、以下のとおりです。
- PC
- プリンター・スキャナー
- 電話、FAX
- 作業デスク
- 応接スペース
ただし、事務所を設置すると、賃料などの固定費が売上がないのにも関わらず発生してしまいます。
そのため、最初は自宅などで開業したり、レンタルオフィスなどを借りて固定費をできる限り少なくするのがおすすめです。
事務所を設置するにしても、規模は大きくしすぎず、必要最低限の設備と広さの場所を借りるのが重要です。
事務所の立地や形態の選び方
事務所を開く場所は、集客や信頼感に関わります。
駅から近い場所はアクセスがよく、来所しやすいため安心されやすいです。
一方で、住宅地や自宅開業なら家賃が安く済むメリットがあります。
また、最近ではレンタルオフィスやシェアオフィスを使う司法書士も増えています。
初期費用を抑えられるうえ、必要に応じて大きな会議室も使えるので、顧客対応に困ることが少なくなることがメリット。
さらに、Zoomなどのオンライン相談を取り入れれば、場所にとらわれずに全国から相談を受けられる可能性も広がります。
4.司法書士会への登録申請をする
独立開業をして、自分の事務所を構えるには司法書士会への登録申請が必要です。
司法書士登録の手続きは、司法書士事務所を開設する地域を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内の司法書士会を経由して行う必要があります。
具体的な登録入会方法は、所属する予定の司法書士会へ確認します。
また、開業をしたら税務署に開業届も提出しておきましょう。
開業届を提出することで、確定申告を青色申告で行えるようになり、さまざまな場面で節税効果が得られます。
青色申告を利用するには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を提出します(原則、事業開始から2か月以内)。
5.人脈作り・営業を行う
開業後の顧客獲得には、人脈作りと積極的な営業活動が欠かせません。
具体的には次のような活動を行い、積極的に人脈作り、営業を行いましょう。
| 活動内容 |
詳細 |
期待できる効果 |
|---|---|---|
| 挨拶状の送付 | 取引先や関連業界に向けて、独立の挨拶と事務所の開業を知らせる挨拶状を送る | 開業を知ってもらい、初期の紹介や相談につながる |
| 交流会や業界セミナーへの参加 | 地元の経営者が集まる交流会や、司法書士向けセミナーに参加し、名刺交換をする | 顔を覚えてもらい、信頼関係を作るきっかけになる |
| 地元企業への訪問 | 不動産会社や税理士事務所、金融機関を訪問し、業務提携を図る | 専門家同士の連携で案件を紹介してもらえる可能性が高まる |
人脈づくりは一朝一夕で行えるものではないので、設備などの準備をしながら並行して行うのがおすすめです。
司法書士が独立開業する際にかかる費用

司法書士が独立して開業する際には、50万円〜150万円ほどが目安となります。
主な内訳は次のようになります。
- 司法書士会への登録料:約3万円
- 事務所の賃貸料(敷金・礼金など):約20万円〜50万円
- 事務所内の家具や設備:10万円〜30万円
- パソコン、複合機、通信機器など:20万円前後
- ホームページ制作費用:10万円〜30万円
開業後すぐに安定した売上が見込めるわけではないため、こうした初期費用に加えて生活費と運転資金も準備しておく必要があります。
資金を準備しないまま開業すると、案件が増える前に資金が尽きてしまい、廃業につながる危険があります。
司法書士の収入モデルと案件ごとの目安

司法書士の収入は、取り扱う案件の種類によって変わります。
独立を考えるなら、どの分野でどのくらいの収入が見込めるかを知っておくことが安心につながります。
代表的な案件と報酬の目安は以下の通りです。
| 業務内容 |
一件あたりの報酬目安 |
特徴 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 5万円〜15万円前後 | ・高齢化の影響で相談が増えている ・関連業務(遺産整理など)に広がりやすい |
| 遺言書作成サポート | 10万円〜20万円前後 | 付随して遺産整理や登記に発展するケースあり |
| 不動産登記(売買) | 3万円〜10万円前後 | 不動産会社からの紹介が多く、安定して案件が入る |
| 商業登記(会社設立) | 5万円〜10万円前後 | 起業ブームに合わせて増えることもある |
| 成年後見 | 年間20万円〜30万円程度 | 継続報酬になるが、責任も重い |
年収のモデルとしては、開業1〜2年目で300万円〜600万円程度、軌道に乗ると800万円以上を目指せる司法書士もいます。
ただし、案件数や単価により差が生まれがち。
案件の幅を広げつつ、自分の強みを持った分野を柱にすると、安定した収入を得やすくなります。
独立開業で失敗する司法書士の特徴

独立開業で失敗する司法書士の特徴は、下記のとおりです。
- 報酬設定額を相場より安く設定しすぎる
- 取り扱う業務が限定的である
- コミュニケーションスキルが不足している
- Web集客をなんとなくで進める
それぞれの内容について、以下から詳しく解説します。
報酬設定額を相場より安く設定しすぎる
開業当初はとにかく仕事が欲しいため、安く自分を売ってしまいがちです。
しかし、後々自分の首を絞めることにつながります。
安く設定したがために、その後もその価格で業務を受けざるを得なくなってしまうもの。
したがって「仕事をしても仕事をしても赤字」といった状態になってしまいやすくなるのです。
開業したばかりだから安くするのは、「まず実績を作る」という観点からいえば良いですが、「限定10名さま」「1か月間期間限定」など、きちんと安くする期間や数を決めて行うようにしましょう。
また、安くやるかわりに「お客様の声をもらう」など、安くやったことが次の仕事につながっていくような工夫をしていくことが重要です。
取り扱う業務が限定的である
司法書士として、専門知識と強みがあること、それらをアピールすることは非常に重要ですが、完全に特化して取り扱う業務を限定的にしてしまうとデメリットのほうが大きくなってしまいます。
司法書士の対応する業務には関連性があることが多く、相続関連の業務を依頼した顧客が、のちに自身の遺言書作成を依頼するなどのようにリピートにつながることも多いです。
得意分野をアピールしつつも、取り扱う業務を幅広くしておき、顧客の獲得を目指しましょう。
幅広い業務に対応できるよう、独立開業する前にさまざまな業務経験を積んでおくのがおすすめです。
コミュニケーションスキルが不足している
司法書士として独立開業を成功させるには、コミュニケーションスキルが必要不可欠です。
司法書士に初めて業務を依頼する顧客のほとんどは不安を抱えていることが多いので、コミュニケーションを通して不安を軽減することが重要といえます。
顧客との信頼を築くうえで重視すべきコミュニケーションのポイントとして、下記が挙げられます。
- 相談しやすい環境や雰囲気を整える
- 知識や経験をもとに疑問を解消する
- 依頼内容に関する完結までの流れを伝える
- 進捗をこまめに報告する
信頼関係を築くことで、のちに別案件のリピートにつながったり、ほかの顧客を紹介してもらえたりなど、仕事の獲得にもつながるのでコミュニケーションは密に取るようにすることが重要です。
Web集客をなんとなくで進める
司法書士が独立開業を成功させるには、Web集客の活用が重要であることは先ほどもお伝えしましたが、Web集客をなんとなく進めても成果には結びつきません。
Web集客には正しい知識が必要であるのはもちろん、「実行・分析・改善」のステップを繰り返して、より精度や効率を上げていく工夫が必要です。
専門知識がない人が独立開業をする場合、最低でも立ち上げから一定の期間は、Web集客をプロに依頼することをおすすめします。
司法書士が独立を成功させるためのポイント

司法書士として独立開業することは、あくまでもスタートに過ぎません。
以下では、実際に司法書士として独立を成功するためのポイントを解説していきます。
- 顧客ターゲットを明確にする
- 強みを活かして初見のユーザーからの信頼を得る
- 人脈を築く
- 資金計画やランニングコスト管理を徹底する
- ブランディングを行う
- Web集客を活用する
各ポイントを詳しく見ていきましょう。
顧客ターゲットを明確にする
まず、司法書士事務所の顧客ターゲットを明確にしましょう。
顧客ターゲットをより具体的にするためには、「ペルソナ」を設定するのがおすすめです。
「ペルソナ」とは架空の顧客像のことで、自社サービスのターゲットとなる「実在しそうな一個人」を想定します。
司法書士事務所のペルソナ設定で想定すべき具体的な項目として、下記のような項目が挙げられます。
- 性別
- 年齢
- 職業
- 抱えている問題・依頼内容
上記の項目をもとに、「30代会社員で開業を考えている、登記手続きを依頼したい男性」のように、より具体的なターゲットを設定します。
顧客ターゲットを明確にイメージしたペルソナを設定することで、集客の方向性がブレてしまうリスクを減らすことができ、集客の成功につながります。
強みを活かして初見のユーザーからの信頼を得る
初見のユーザーは司法書士を探す際に「実績があるか」「相談したい内容の専門性が高いか」など、信頼できるかどうかを重要視しています。
たとえば、「不動産・相続なんでも対応!○○司法書士事務所」よりも、「相続に強み!○○司法書士事務所」の方が、相続を依頼したい人にとっては選ばれやすくなるといえます。
たとえ「開業したばかりで仕事を選んでいる場合ではないから、なんでも対応できるという風に見せたい」という場合でも、焦るべきではありません。
ある程度見せ方として「〜に強み」「〜に特化」「〜専門」という見せ方にしましょう。
あまりに全方位に対して貪欲な態度ではなく、専門性があり特化している、という見せ方をすることで、依頼しようと悩んでいる顧客に安心感を与えることにつながります。
人脈を築く
司法書士は地域密着性の高い業種です。
そのため、地域の関連事業者や同業者(特に税理士や弁護士)との連携を深めることで、案件の獲得が期待できます。
また、開業当初は「全く初めての人」からすぐに仕事が来る訳もなく、ある程度繋がりのある業者や知り合いの中から「紹介」という形で発生していくのが一般的です。
開業当初は地域の関連事業者の集まりに顔を出したり、コミュニティに参加したりしながら、自身のことを覚えてもらうように努めることが重要です。
資金計画やランニングコスト管理を徹底する
司法書士の独立開業を成功させるためには、案件を受ける力だけでなく、お金の流れを管理する経営の視点が必要です。
特に注意すべきは次の2点です。
| 注意点 |
内容 |
リスク例 |
|---|---|---|
| 開業資金の確保 | 事務所の賃料や設備費だけでなく、生活費や広告宣伝費などを含めた運転資金を半年から1年分は用意しておく | 資金が不足し、案件が増える前に廃業に追い込まれる危険 |
| ランニングコストの管理 | 家賃・人件費・通信費などの固定費を、独立当初は必要最低限に抑え、売上が安定してから拡大する | 毎月の支出が膨らみ、利益が残らない状態になる危険 |
「案件が増えているのに手元にお金が残らない」という事態を防ぐには、毎月の収支をしっかり管理することが重要です。
経理ソフトやクラウド会計を使って数字を見える化し、数字に基づいた経営判断を心がけましょう。
ブランディングを行う
司法書士はどの事務所も似た業務を取り扱うため、差別化のためのブランディングが欠かせません。
たとえば次のような工夫のしかたが考えられます。
| 工夫のポイント |
具体例 |
効果 |
|---|---|---|
| 専門分野を明確に打ち出す | 「相続に強い司法書士」 「不動産登記に特化」 |
得意分野が一目で伝わり、相談につながりやすくなる |
| 一貫性のある情報発信 | ホームページ・SNS・パンフレットなどを同じトーンやデザインで統一 | 事務所の信頼感と認知度が高まる |
| 顧客目線の発信 | 「難しい法律用語をわかりやすく説明」 「相談しやすい雰囲気を伝える」 |
顧客が安心して依頼できると感じやすくなる |
ブランディングを行うことで「どんな司法書士か」が一目で伝わり、顧客から選ばれやすくなります。
結果として、紹介や口コミにつながり、事務所の成長を長期的に支えることができるのです。
Web集客を活用する
司法書士が集客を成功させるうえで必要不可欠なのが、Web集客の活用です。
なぜなら、インターネットが普及した現代において、司法書士を探すユーザーのほとんどがはじめにとる行動がインターネット検索だからです。
Web集客の方法には、下記のような方法があります。
- HPの作成
- Web広告の掲載
- ブログの作成と記事の発信
- SNSでの情報発信
- ポータルサイトへの登録
各方法を組み合わせてWeb集客を活用することで、司法書士としての独立を成功に近づけやすくなります。
積極的に取り入れていきましょう。
司法書士の集客なら「繁盛司法書士プラン」がおすすめ!
独立したばかりの司法書士にとって、集客の仕組みを整えるのは簡単ではありません。
そんな時に役立つのが、司法書士に特化した集客支援サービス 「繁盛司法書士プラン」 です。
プランの特徴は次の通りです。
| 項目 |
内容 |
利点 |
|---|---|---|
| ホームページ制作 | 相続に特化した専用サイトを15ページ構成で作成。セキュリティ管理・サーバー維持・バックアップ込み | 初期費用0円で、50〜60万円相当のクオリティが手に入る |
| 広告運用 | Google広告などを使い、相続相談を探す人に直接アプローチ | 地域特性に合わせて最適化、短期間で効果を実感できる |
| Googleビジネスプロフィール | 営業時間や料金を検索結果や地図に反映 | 地元ユーザーに見つけてもらいやすくなる |
| 導入サポート | ・サイト制作・広告運用はほぼ丸投げでOK ・必要なのは写真と簡単な情報提供のみ |
ITが苦手でも安心して導入可能 |
| 契約条件 | ・初期費用ゼロ ・月額10万円(管理費・広告費込み) ・6か月で解約も可能 |
リスクを抑えて始められる |
実際に導入した事務所からは、以下のような声が寄せられています。
- 大阪府A司法書士事務所様:月17件の問い合わせ、成約8件。以前より明らかに問い合わせが増えた。広告費の増額も検討中
- 静岡県B司法書士事務所様:月9件の問い合わせ、成約4件。お任せで集客できるので満足。取引できる不動産業者が増えた
- 岡山県C司法書士事務所様:月12件の問い合わせ、成約5件。導入時に事務所の仕組みを変える必要がなく、報酬を考えれば十分に割が合うと実感
他社との比較でも「初期費用ゼロ」「月10万円で運用可能」という強みがあります。
たとえば、大手コンサル会社では初期費用50万円+毎月30万円以上が相場ですが、繁盛司法書士プランなら大幅にコストを抑えられます。
Web集客で顧客獲得に成功した事例

ホームページや広告を使った集客の仕組みを取り入れて、問い合わせが増えた事務所の例を紹介します。
- 集客を仕組み化して問い合わせ件数が1.5倍になった事例
- 紹介に頼らず安定的な集客が実現した事例
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
集客を仕組化して問い合わせ件数が1.5倍になった事例
ある司法書士法人では、以前は「専門的すぎて実際の仕事につながりにくい相談」が多く入っていました。
そこで発信する内容を「一般の方が知りたい相続の話」に変えたところ、相談の質が変わり、受任(仕事を正式に受けること)できる案件が増えました。
結果として、ホームページを見た方の数(PV数)が2倍、問い合わせ件数は1.5倍になりました。
事務所が行った工夫は次のとおりです。
- 相続に関する記事を専門家として分かりやすく発信
- 数千のキーワードの中から、相談につながりやすいものを選んで記事に反映
- サイトの力(ドメインパワー)を強くし、制作会社から改善点を毎月報告してもらう
以前は広告費に毎月30万円以上かけても成果が出ず、途中でやめたことがありました。
今回は月10万円で「相続サイト」を作り、広告まで回すように。
初期費用はゼロ円で、施策を始めて6日目に問い合わせが入りました。
さらに、20万円の遺言書作成の依頼から、遺産整理までつながり、1件の相談が数十万円の売上になったこともあります。
資金をかけても成果が出ない集客を続けると、費用だけが減っていきます。
数字をもとにした戦略へ切り替えたことが、成功の理由です。
紹介に頼らず安定的な集客が実現した事例
荒俣政吉司法書士行政書士事務所では、紹介に頼らずに集客したいと考えていました。
そこで月10万円の「繁盛司法書士パック」を導入し、新しいホームページと広告を活用しました。
結果として、毎月3件ほどの成約が安定して取れるようになり、多い月では5〜6件に増加。
今では仕事の半分以上がホームページから入ってきています。
広告からの成約率は約80%と高く、問い合わせがあればほとんど受任につながるとのこと。
荒俣政吉司法書士行政書士事務所が成果を出せた理由は次の通りです。
- 初期費用ゼロ円で、集客向けの専用サイトを作成
- 毎月の費用は10万円(広告費6万円、運営費4万円)とシンプル
- 広告運用や改善は全て任せられるので、事務所側は司法書士業に集中できる
以前は管理会社に月5万円を払っていましたが、修正対応が遅く、不具合も放置されていました。
そのため問い合わせは月に1件あるかないかで、集客につながりませんでした。
今ではホームページの更新や不具合対応も任せられるので、安心して本業に専念できています。
もし古い管理体制のまま改善を後回しにしていたら、問い合わせは増えず、広告費と時間だけが無駄になっていたはずです。
成果が出ている形に変えることが、少人数の事務所でも成功する近道といえます。
司法書士の独立に関するよくある質問

司法書士として独立することを考える人がよく気にする、次の質問について答えます。
- 司法書士の独立は厳しいって本当ですか?
- 司法書士は何年目で独立する人が多いですか?
- 自宅で開業することはできますか?
以下から、各質問の回答を詳しく見ていきましょう。
司法書士の独立は厳しいって本当ですか?
司法書士は資格があれば誰でも独立できます。
しかし、安定した収入を得るまでは簡単ではありません。
特に集客や経営の感覚が不足していると、案件が取れなかったり資金が尽きたりして苦しくなることがあります。
ただし、勤務時代に実務経験を積み、人脈や営業ルートを作り、さらにWeb集客の仕組みを取り入れれば成功するチャンスは十分にあります。
実際、司法書士の廃業率は他の業種より低いといわれているので、準備を整えれば安定した独立が可能です。
司法書士は何年目で独立する人が多いですか?
独立のタイミングは人によって違うものです。
多くの方は2年から5年ほど勤務してから独立しています。
勤務時代に経験を積み、仕事の流れやお客様対応を理解しておくと、独立後に安心して案件を受けられるようになります。
自宅で開業することはできますか?
はい、可能です。
特に開業したばかりの時期は、固定費を減らすために自宅を事務所にする司法書士も少なくありません。
自宅開業のメリットは次の通りです。
- 事務所の賃料がかからない
- すぐに始められる
一方で次のようにデメリットもあります。
- お客様を迎える場所が十分に確保できない
- 事務所としての信頼感で不利になることがある
そのため、最初は自宅やレンタルオフィスで始めて、顧客が増えた段階で専用の事務所を構える方も多いのです。
Web集客で独立開業を成功させよう

この記事では、司法書士の独立開業のメリット、開業手順と成功のポイントを解説してきました。
司法書士が独立開業を成功させるには、Web集客の活用が特に重要です。
しかし、一からHPを制作することや、効果的なWeb広告の掲載設定、コンテンツのSEO対策などは、専門知識が必要になることが多いので難易度はかなり高いのが実情です。
また、「実行・分析・改善」の流れを繰り返すことも、独立開業をしたばかりの多忙な司法書士にとってかなり困難といえます。
Web集客をプロに依頼したい司法書士の方は、ぜひドットアンドノードまでご相談ください。
ドットアンドノードは、類似の業務を取り扱う他社の相場に比べ、費用を抑えながらHP制作や運営をプロに丸投げできる点がおすすめのポイントです。
ドットアンドノードの「繁盛司法書士パック」のサービス内容は、下記のとおりです。
- HP制作
- Web広告の出稿作業
- 毎月のWeb広告運用
- 広告の分析・調整と最適化
- AIを活用した広告の洗練作業
- 地域特性に合わせた広告の調整
なお、ドットアンドノードの公式HPから事前に集客見込み診断が利用できるので、「独立開業するうえで、どれくらいの集客が見込めるのかわからない」という不安を抱えている方も安心です。
独立開業にあたってWeb集客を依頼したい方やWeb集客でわからないことがある方は、ドットアンドノードまでお気軽にご相談ください。