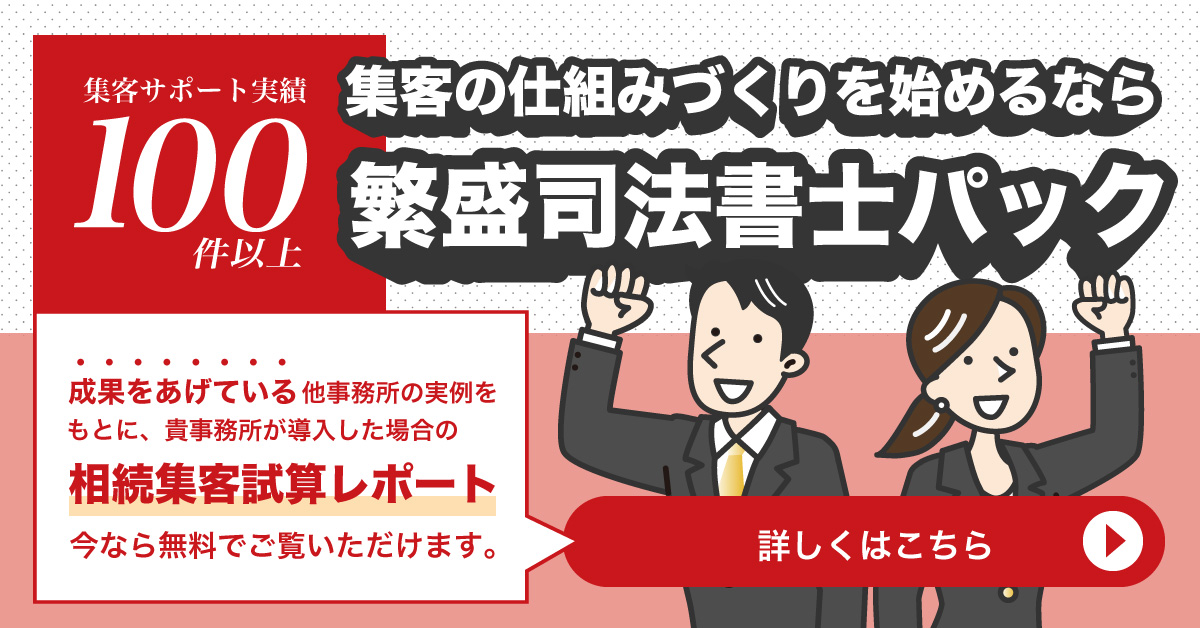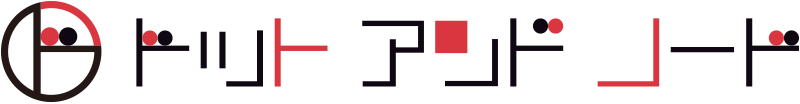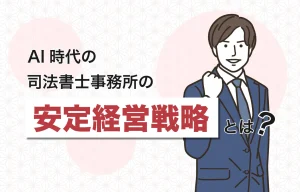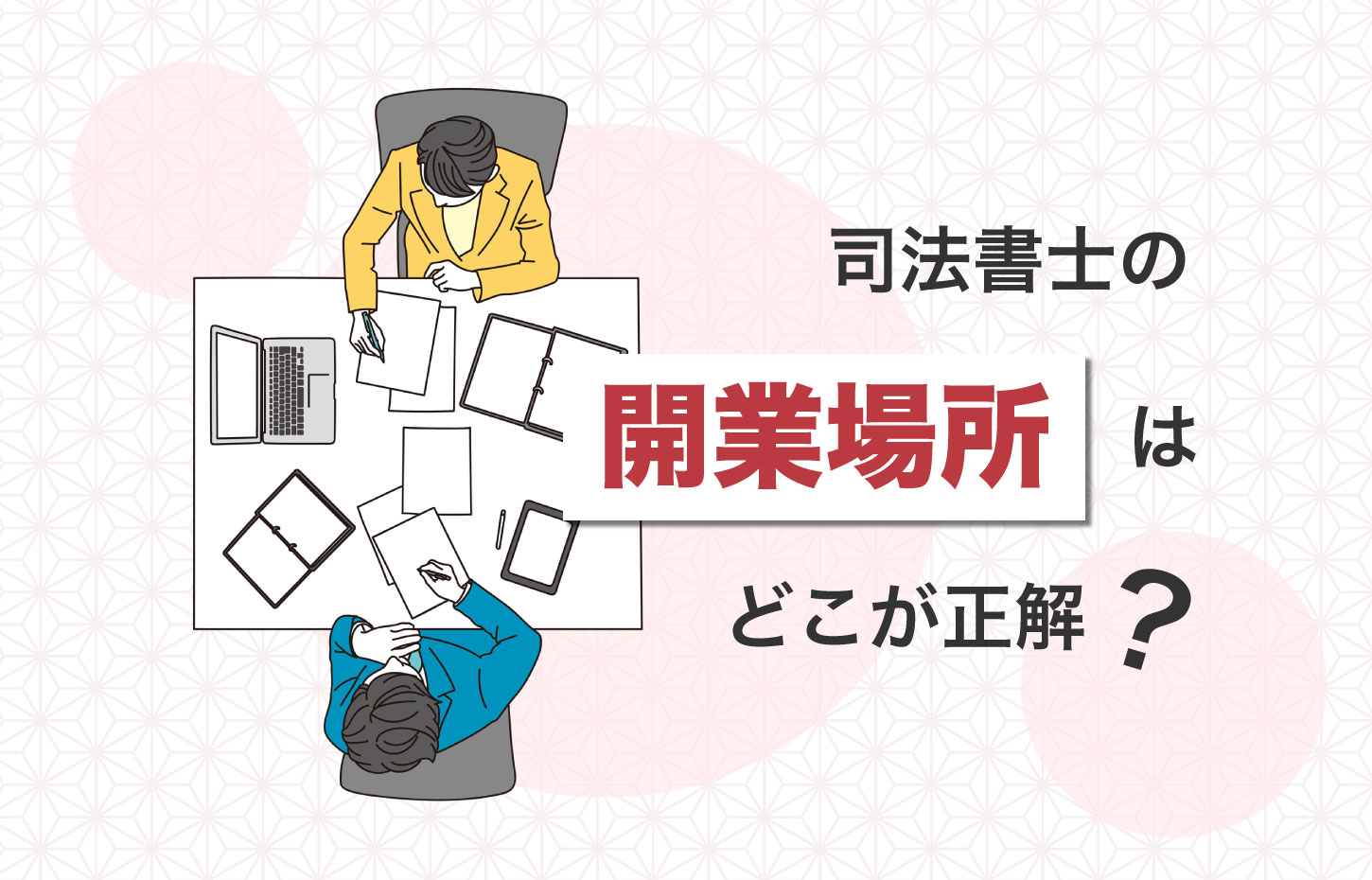
司法書士の開業場所どこが正解?ニーズ・集客性・資金面などを徹底比較
司法書士が独立開業する際、「どこなら集客できる?」「自宅で開業はあり?」「開業資金を安く抑えたい」など開業場所の選択に頭を悩ませることが多いのではないでしょうか。
結論からいえば、どんな分野の業務を優先的に受託したいか、どんな生活スタイルを望むかで開業場所の正解は異なります。
「都会なら仕事が多そう」と安易に決めてしまうと、思っていた状況と違ったと後悔するケースも珍しくありません。
本記事では集客性・市場ニーズ・資金面などの観点から、司法書士の開業場所の選び方で意識すべきポイントを徹底解説します。
開業場所で何が変わる?司法書士として後悔しないために意識すべき5つのポイント

開業場所で後悔しないためには、そもそも場所の選択で何が変わるのかを正しく理解しておくことが大切です。
開業場所を選択する前に知っておきたいこととして、以下のポイントが挙げられます。
- 場所によって市場ニーズは変わること
- 顧客目線で集客を考えるべきであること
- 開業資金やランニングコストを試算すること
- 競合は多いかを考慮すること
- 生活スタイルとのバランスを考慮すること
ここからは、5つのポイントについて詳しく解説していきます。
場所によって市場ニーズは変わること
開業場所を選ぶ際は、その地域にどのようなニーズがどれだけあるかを把握することが重要です。
地域ごとに求められる業務は異なり、自分の専門分野とマッチしない場所を選んでしまうと、思うように仕事が取れなくなるリスクがあります。
たとえば、都市部では企業が多いため、会社設立や商業登記といった法人向け業務のニーズが豊富です。
一方、地方や高齢化が進む地域では、相続・遺言関連の業務に対する需要が増えています。
どの地域に、どの業務分野のニーズがあるかを見極めることが、継続的に仕事を得るためには必要です。
自分の強みや受託したい業務が、地域のニーズと合っているかを事前に調べましょう。
顧客目線で集客を考えるべきであること
ターゲットとなる顧客にとって、アクセスしやすい開業場所を選びましょう。
せっかく専門性があっても、それを必要とする顧客にとってアクセスしづらい場所だと、集客につながりにくいからです。
たとえば、顧客の移動手段が車か公共交通かによっても場所の選択肢が変わってきます。
地方なら車移動が多いので幹線道路沿いにあるとアクセスしやすく、都市部なら公共交通での移動が多いので駅から近い方が有利です。
また、受託したい業務の顧客が個人か企業かによっても、住宅地が良いかオフィス街が良いかなどの判断ができます。
開業場所によって集客の効率は大きく変わってくるので、まずは顧客となるターゲット層の分析が重要です。
開業資金やランニングコストを試算すること
開業にかかる費用と継続的に発生するコストをしっかり見積もることが、事務所経営の安定につながります。
無理な初期投資や高額な家賃を背負うと、収入が不安定な時期に経営が苦しくなるリスクがあるからです。
駅近のテナントならば利便性は高まりますが、家賃が月に十万円を超えることも珍しくありません。
一方、郊外や自宅開業なら開業初期に必要な費用を安く抑えることができます。
ただし、安さだけで選ぶと信頼性や設備面でマイナスになる可能性もあるので、総合的な判断が必要です。
設備資金と運転資金のシミュレーションをしてみて、コストと集客性のバランスをとりましょう。
競合は多いかを考慮すること
周辺の競合状況を把握しておくことは、開業後の売上に直結します。
競合が多すぎると差別化が難しく、価格競争に巻き込まれたり、集客が伸び悩んだりするからです。
大型司法書士法人や歴史のある司法書士事務所が多く存在している場所で、開業直後の司法書士が新規案件を受託していくのは容易ではありません。
開業場所を決める際には、周辺の司法書士事務所の数や、どのような業務を専門とする事務所が多いかなどを調査しておくことが重要です。
競合が多すぎる場所よりも、自分の強みを活かして差別化できる環境を選ぶのも開業を有利に進めるポイントになります。
生活スタイルとのバランスを考慮すること
開業場所を選ぶ際には、私生活とのバランスがとれるかどうかも重要な判断基準です。
どんなに仕事が順調であっても、生活との両立ができなければ精神的にも肉体的にも疲弊して、事業を長く続けることが難しいからです。
たとえば、家庭に小さなお子さんがいる状況で、毎日1時間以上かけて通勤するような立地に開業した場合、家庭への負担や精神的なストレスが大きくなってしまいます。
日本司法書士会連合会が2020年に司法書士会員22,726名を対象に行った「第2回司法書士全国調査」によれば、事務所の所在地を決定する際に重要視したものは「居宅から近距離であること」が25.9%を占め、最も多い回答でした。
このことからも、多くの司法書士にとってワークライフバランスが重要視されていることが分かります。
開業司法書士は自由な働き方が可能だからこそ、生活や家族との調和も意識して開業場所を選ぶことが大切です。
地域により司法書士の開業場所には違いが生まれる

司法書士が開業する際、地域によって開業場所の選び方は変わってきます。
なぜなら、都市部と地方ではニーズ・集客性・資金面で大きな違いがあるからです。
- 都市
- 地方
以下からは、都市と地方それぞれの特徴を比較しながら、開業場所選びの要点を解説します。
都市
まずは都市での開業場所について、ニーズ・集客性・資金の面から検討してみましょう。
ニーズ
都市部では、司法書士へのニーズが全般的に高いことが特徴です。
不動産登記や商業・法人登記、相続関連業務など幅広い分野での需要が見込まれるので、開業場所としては魅力が大きいといえます。
なかでも、地方と比較して特筆すべき違いは、商業・法人登記のニーズの高さです。
2025年版司法書士白書によると、令和5年の東京法務局管内の会社の登記件数は680,160件であり、管内の司法書士数9,686人で割ると、1人あたり70.2件でした。
対して、高松法務局管内では司法書士1人あたりの登記件数が40.6件にとどまり、都市部での商業・法人登記の需要の高さがうかがえます。
不動産登記に関しては、都市部の登記件数は確かに多いものの、司法書士の数も多いため、東京法務局管内で司法書士1人あたり350.1件、高松法務局管内で338.8件と、ほぼ同等の結果です。
このことから、都市部での開業場所として、オフィス街や商業地域が候補として考えられます。
地域のニーズを把握するうえでは、単純な業務件数だけでなく、該当地域に在籍する司法書士数を加味して分析することが重要です。
集客性
都市部は人口が多く、潜在的な顧客数も多いため、集客の面では有利です。
商業・法人登記のニーズが高いので、オフィス街や商業地域が開業場所としては集客性が高いでしょう。
また、駅周辺や商業施設近くは相談に立ち寄りやすく、立地としては有利です。
しかし、都市部では競合となる司法書士事務所も多いため、開業場所を検討する際は周辺の競合状況を事前に把握する必要があります。
競合状況のほかに、開業予定地の周辺人口や人の流れを考えると、穴場となる開業場所が見つかるかもしれません。
資金
都市部では、家賃や人件費といった固定費が高いため、地方と比べて開業時の初期費用がかさみがちです。
特に、駅近や商業施設周辺などの集客に有利な立地は賃料が高いので、開業当初の経営が不安定な時期には負担が大きくなります。
想定される売上に対して、どこまで初期費用や固定費に投資できるかを慎重に見極めることが大切です。
都市部にはレンタルオフィスやシェアオフィスが充実しているので、それらを活用することで初期コストを抑えながら開業する方法もあります。
いきなり開業場所に高額な投資をするのではなく、事業が軌道に乗ってきたら、集客性のより良い場所に事務所移転することを検討してみても良いでしょう。
地方
次に、地方での開業場所について、ニーズ・集客性・資金の面から検討してみましょう。
ニーズ
「地方では仕事が少ない」と思われがちですが、司法書士業務に限っていえば、必ずしもそうとは言い切れません。
なぜなら、地方では人口は少ないものの、司法書士の数自体も少ないため、相対的に一人あたりが担う業務量は都市部と同等か、むしろ多い地域さえあるからです。
2025年版司法書士白書によると、関東ブロックでの司法書士1人あたりの人口は5,307人に対して、東北ブロックでは7,431人でした。
地方で開業する場合は競合が少ないというメリットがある一方で、相続や不動産登記、成年後見など幅広い業務に対応する必要があります。
つまり、「地域の法務相談窓口」としてのニーズが求められているのです。
このことから考えると、開業場所としては地域住民との自然な接点が持てる場所が理想的といえます。
住宅街近くや商店街の一角、地元密着型の複合施設内などは、認知度の向上や信頼関係の構築がしやすく、開業直後の集客にもつながりやすい開業場所です。
集客性
都市部に比べて人の流れは緩やかであり、通行量の多い駅前や商業施設に依存するような集客は難しいかもしれません。
一方で、地方では地域密着型の関係性が築きやすく、一度信頼を得ることができれば、口コミや紹介を通じた安定した集客が期待できます。
そのため、開業場所を選ぶ際には、地域住民との接点を持ちやすい立地を選ぶことが重要です。
また、地方特有の生活スタイルにも配慮しましょう。
車移動が主流となる地域では、幹線道路沿いであることや駐車スペースを確保することで、利便性が向上し来所のハードルを下げることができます。
地方においては、必ずしも駅近であることではなく、生活圏の動線上にあるかどうかが鍵です。
資金
地方は都市部に比べて家賃や物価が安く、開業にかかる初期費用やランニングコストを抑えることが可能です。
地方自治体によっては、移住政策の一環として開業支援に力を入れている自治体もあるので、それらの支援制度を活用することも検討してみましょう。
また、日本司法書士会連合会では、過疎地域において開業する司法書士等に対して、財政的支援を行う事業もあります。
日本司法書士会連合会は、司法へのアクセスが困難な地域において、司法サービスの提供に積極的に取り組む司法書士及び司法書士法人を支援します。具体的には、司法過疎対策の一環である司法過疎地開業支援事業により、一定の要件の下、当該地域において期間内に開業又は開業予定の司法書士等に対し、開業貸付金及び定着貸付金を貸与する等、財政的な支援を行います。
引用元:日本司法書士会連合会「令和6年度司法過疎地開業支援事業の実施について(お知らせ)」
開業資金が抑えやすく支援制度が充実しているので、地方での開業は資金面で言うと比較的ハードルが低いといえます。
司法書士が開業する場所(事務所)の形態ごとのメリット・デメリット

司法書士の開業場所については、事務所の形態も集客や経営に大きな影響があるので、重要な選択項目です。
事務所の形態としては、主に以下の形態が挙げられます。
- 自宅・SOHOマンション
- テナント(貸事務所)
- レンタルオフィス
ここからは、それぞれの事務所形態についてメリット・デメリットを解説していきます。
自宅・SOHOマンション
まず、自宅・SOHOマンションのメリットとデメリットを解説します。
なお、SOHOマンションとはSmall Office Home Officeの略で、自宅兼事務所として利用できるマンションのことです。
メリット
自宅やSOHOマンションを事務所とする最大のメリットは、初期費用やランニングコストを大幅に削減できるという点です。
事務所を別途で借りる必要がないため、敷金・礼金がかからず開業資金を最小限に抑えることができます。
毎月の賃料も不要なので、経営が不安定な開業初期には心強い選択肢といえるでしょう。
また、自宅であれば通勤の必要がなく、通勤時間や交通費の面でもコストを省くことが可能です。
さらに、業務の隙間時間に家事ができたり、急な業務にすぐ対応できるなど、生活と仕事の調整がしやすいというメリットもあります。
デメリット
デメリットとしては、事務所の住所として自宅情報を公開せざるを得ないため、個人情報の漏えいやプライバシーの問題が発生しやすいことです。
また、生活空間と業務空間をいかに切り離すか工夫が必要であり、家族がいる場合は理解と協力が求められます。
司法書士の業務では、顧客との打ち合わせや相談の来客が多いので、応接スペースを確保することも考えなければいけません。
新規顧客にとっては「オフィスらしい雰囲気がない」と感じられやすく、信頼感を与える空間作りが課題となります。
テナント(貸事務所)
次に、テナント(貸事務所)のメリットとデメリットを解説します。
メリット
司法書士の事務所形態として、最も一般的なのがテナントを借りるスタイルです。
独立した事務所空間を確保できるため、初めて訪れる顧客にも「しっかりした事務所」という印象を与えることができ、信頼感につながります。
また、応接スペースを設けやすく、来訪者が安心して相談できる環境が作りやすいのもメリットでしょう。
自宅とは完全に分離された業務空間であることから、仕事と私生活の切り替えもしやすく、業務に集中しやすい環境を整えることが可能です。
デメリット
テナントを借りる場合は、当然ながら家賃や光熱費のランニングコストが発生するうえに、敷金・礼金といった初期費用も必要となります。
開業初期で売上が安定していない時期には、資金繰りの面でプレッシャーを感じやすくなるため、事前の資金計画をしっかりと考えておきましょう。
また、事務所の立地によってはアクセス面での優劣が出るため、顧客層の動線を十分に考慮して場所を選定することが重要です。
レンタルオフィス
最後に、レンタルオフィスのメリットとデメリットを解説します。
メリット
テナントを借りる場合と比較して、安価な料金でビジネス用の住所や設備を利用できる点がメリットです。
敷金や礼金も必要ないので開業資金を抑えつつも、きちんとした事務所感を演出することができます。
1ヶ月単位から契約できるところも多く、椅子や机の基本的な設備も備わっているので、柔軟かつスムーズに開業準備を進めることが可能です。
なかには士業専門のレンタルオフィスもあるので、人脈づくりや業務範囲の広がりにもつながる可能性があります。
デメリット
レンタルオフィスのデメリットは、主に都市部を中心に展開されているため、地方では選択肢が限られるという点です。
また、共有スペースを活用するスタイルであることから、司法書士業務において重要となる「守秘義務」や「相談内容の機密性」において、顧客が不安を感じる可能性もあります。
第24条(秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
引用元:司法書士法第24条
そのため、レンタルオフィスを活用する際には、個室の有無や防音対策、プライバシー確保の体制などに十分な配慮が必要です。
司法書士が独立開業する場所として有利な立地

開業場所の立地は、業務効率や集客、生活の質につながるため、独立開業を成功させるための重要な要素です。
司法書士にとって開業に有利な立地としては、以下の条件が挙げられます。
- アクセスが良い
- 周辺環境に利便性がある
- 他士業との連携をとりやすい
- 私生活とのバランスがとりやすい
ここからは、それぞれの条件について詳しく解説していきます。
アクセスが良い
開業場所として重要な条件となるのは、まずアクセスの良さがあります。
最近はオンラインでの打ち合わせが増えていますが、やはり司法書士の業務には対面相談の機会が多く、顧客にとってアクセスしやすい立地かどうかは集客力に直結するからです。
顧客が司法書士に相談したいと考えた時、多くはネット検索で地域の司法書士事務所を探し、自宅や職場から行きやすい所を選ぶでしょう。
都市部では公共交通機関の利用が主流であるため、駅から徒歩圏内が好まれる傾向にあります。
一方、地方では車での移動が一般的なため、駐車場の有無や幹線道路沿いの立地かどうかが重要です。
移動手段に応じた立地選びが、来所のハードルを下げ、新規顧客の集客につながります。
周辺環境に利便性がある
司法書士事務所の周辺環境が便利かどうかも、立地を考えるうえで大切な要素の一つです。
日常的に立ち寄れるスーパーやコンビニがあれば、昼食や事務用品の購入などで便利ですが、特に注目したいのが「法務局」や「郵便局」が近くにあるかどうかという点です。
司法書士の業務では、不動産や会社・法人の登記申請のために、法務局を利用する機会が頻繁にあります。
近年では登記手続きのオンライン化が進んでおり、昔ほど法務局に行く機会はありませんが、それでも書面提出が必要な場面や、急ぎで書類を受け取りたいケースは少なくありません。
また、司法書士の業務では、登記完了後の書類送付や依頼者とのやり取りで書留・速達を利用することも多く、郵便局に行く頻度は意外と高いものです。
こうした業務に欠かせない機関が近くにあれば、移動時間や手間を削減できるため、結果的に業務効率の向上につながります。
日々の業務をスムーズにこなすためにも、最寄りの法務局や郵便局との距離は、しっかりと確認しておきたいポイントです。
他士業との連携をとりやすい
司法書士の業務は、税理士や行政書士、弁護士など、他士業と連携する場面が多々あります。
開業場所を検討する際には、周辺に他士業の事務所がどのくらいあるかも事前に調べてみましょう。
士業のネットワークが形成されているエリアや、士業専門のシェアオフィスなどの共同スペースに入居すれば、相互に顧客を紹介し合える体制が築きやすくなります。
また、士業同士でセミナーや相談会を開催することも可能になり、地域における信頼感の向上や事業のブランディングにもつながるでしょう。
私生活とのバランスがとりやすい
開業場所を検討する際には、仕事上の業務効率や集客性だけでなく、私生活との両立が可能かも大きな課題です。
仕事のことだけを考えて開業場所を選んでしまうと、私生活がないがしろになり、いずれ仕事にも悪影響がでてしまう可能性があります。
たとえば、自宅と事務所、子どもの通う学校やスーパーなどが比較的近いと、普段の生活が快適なだけでなく緊急時の対応もスムーズです。
それぞれの家族構成やライフステージに応じて、心地よく働ける環境を整えることで、長く安定した事務所運営を続けることができます。
なお、司法書士として正式に業務を行うためには、開業場所に事務所を設けたうえで、その所在地に基づいて名簿登録を行う必要があります。
第8条(司法書士名簿の登録)
一 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
引用元:司法書士法 | 第8条
総合的な判断で司法書士として正解となる開業場所を選ぼう!

今回は司法書士の開業場所について、ニーズ・集客性・資金面などを徹底比較しました。
司法書士が独立開業する際には、地域や事務所の形態、立地を考慮して開業場所を決める必要があります。
自分の理想とする働き方や地域の特性を見極めた開業場所を選択することが、独立開業を成功に導くことになるでしょう。
ただし、司法書士として正解となる開業場所を選べたとしても、それで完璧ではありません。
都市か地方か、自宅かテナントか…たとえどんな選択をしたとしても、共通して必要不可欠なのが、その後の集客につなげる営業活動です。
特に、インターネットによるWeb集客は開業場所に限らず効果的であり、これからますます必須な集客方法となります。
弊社ドットアンドノードでは、Web集客のプロが動線設計したホームページと営業支援により、開業後の直接集客をサポートする「繁盛司法書士プラン」をご用意しています。
「開業後の集客を戦略的にしたい」とお考えであれば、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。