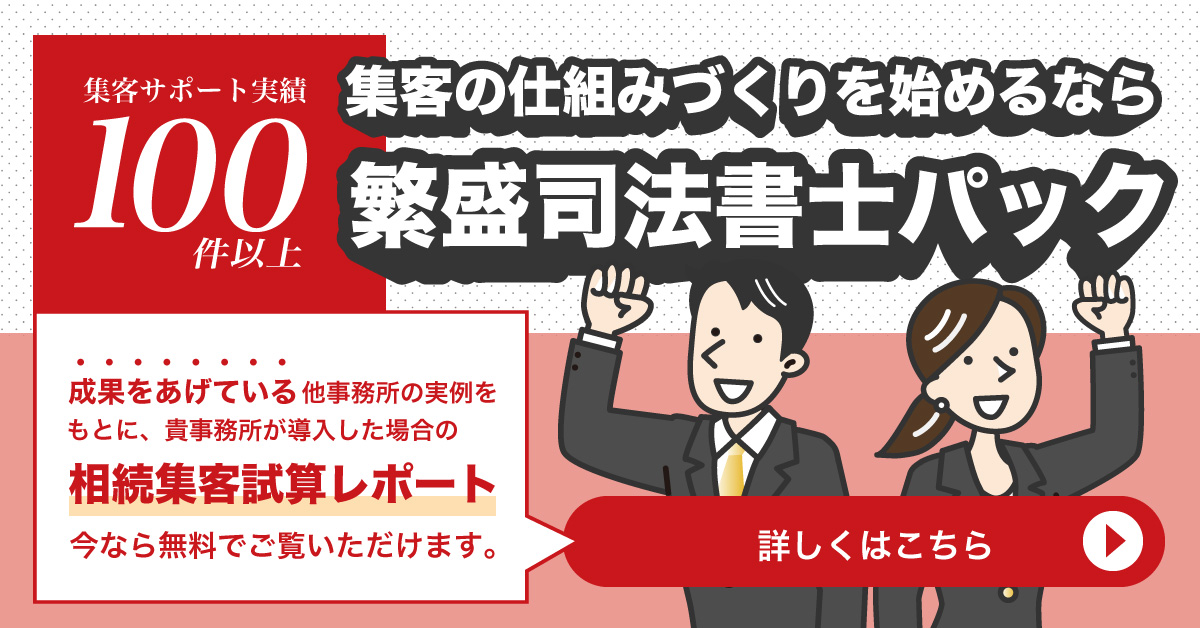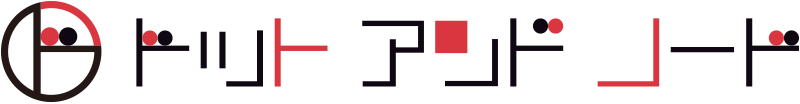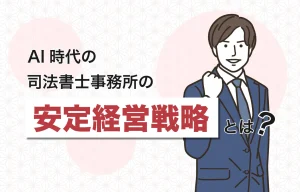司法書士は書籍を出版すべき!出版社の選び方や出版後の集客方法を解説
司法書士の中には、「自分の専門性を広く知ってもらいたい」「知名度を上げて集客につなげたい」「士業界での立ち位置を高めたい」など、戦略ツールとして書籍出版を視野に入れている方が少なからずいるでしょう。
しかし、いざ出版しようと思っても「どのように書籍のテーマを決めるの?」「本当に集客につながるの?」といった疑問や不安も多いはず。
この記事では、司法書士が書籍を出版する理由をはじめ、商業出版と自費出版のメリット・デメリットなどを解説します。
司法書士が書籍を出版するべき理由
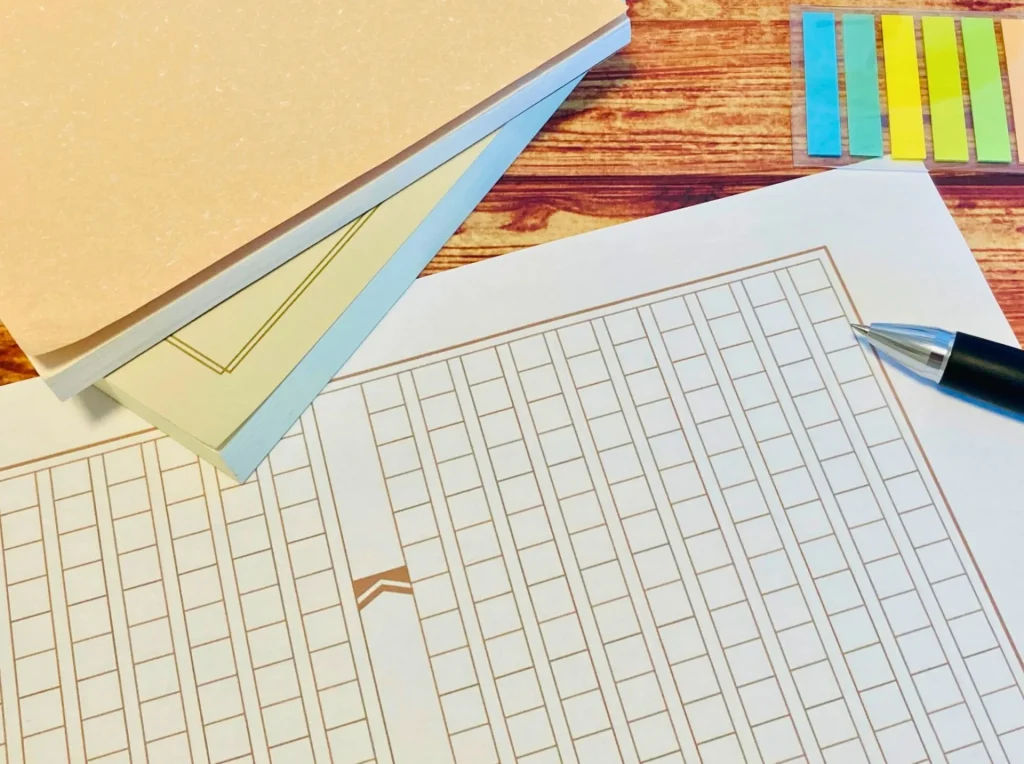
司法書士が書籍を出版することは、単なる自己表現に留まらず、講演依頼の増加や顧問契約の獲得といった具体的なキャリアの成長にもつながるので重要です。
司法書士が書籍を出版するべき理由は、次の通りです。
- 専門家としての地位を確立できる
- 社会貢献や後進育成につながる
- 講演やセミナー活動へ展開できる
ここからは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
専門家としての地位を確立できる
司法書士は不動産登記や会社登記など、専門的な知識を必要とする業務を扱います。
書籍を出版することで、その専門性を世に広め、特定の分野に特化していることを周知できるでしょう。
さらに、日々の業務における信頼獲得だけでなく、同業者や他の士業からの評価が向上し、司法書士としてのブランディングが確立できます。
社会貢献や後進育成につながる
一般の人々でも法律問題を正しく理解できるよう、司法書士が専門知識を分かりやすく伝えることは、国民の法的トラブルの予防につながり、司法アクセスの向上という点で社会貢献の一役を担えます。
たとえば、相続や成年後見人といった分野は、多くの人々にとって複雑で理解しにくいものです。
こうした内容を分かりやすい言葉で解説した書籍を作れば、読者の抱える不安や疑問を解消し、適切な法的手続きへと導けるでしょう。
また、自著を読んだ人が司法書士を目指したり、司法書士のロールモデルとして認識されたりすることで、後進の育成にもつながります。
講演やセミナー活動へ展開できる
本を出版したという実績は、各種団体からの講演依頼や、自主開催セミナーの集客にも役立ちます。
書籍という「形ある実績」があることで、各種団体・企業・教育機関からの講演依頼やセミナー講師の打診が増加することが期待できます。
また、書籍の内容をベースにした講演は、参加者にとって理解しやすいうえに、自身のメッセージをより深く伝えられるでしょう。
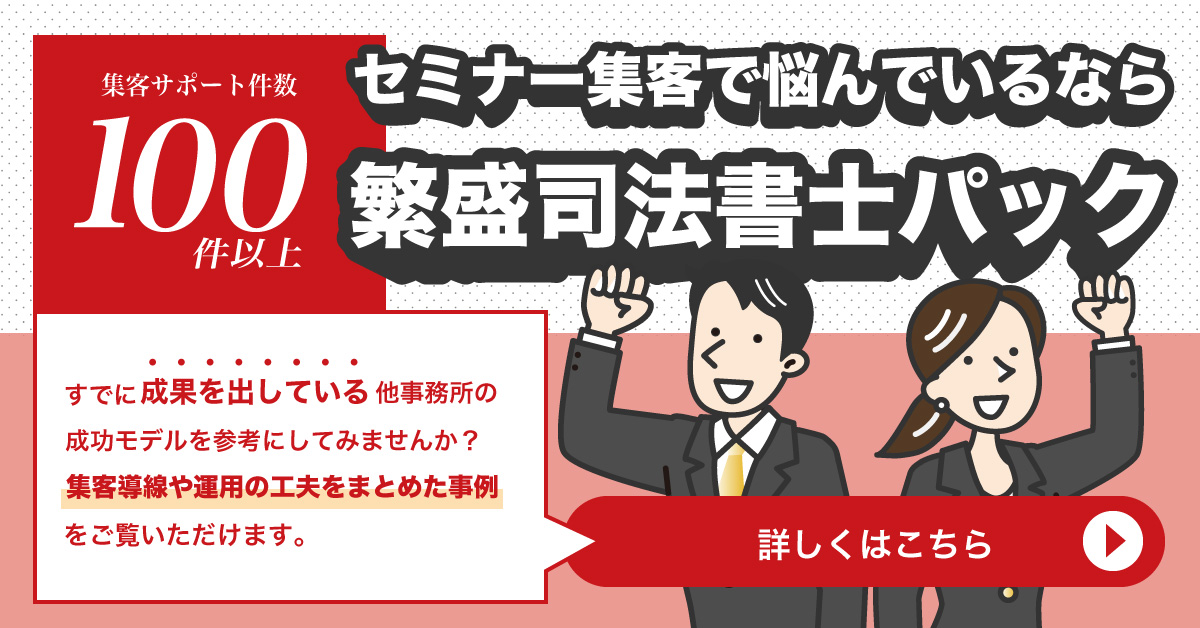
司法書士が出版する書籍テーマ決めの流れ
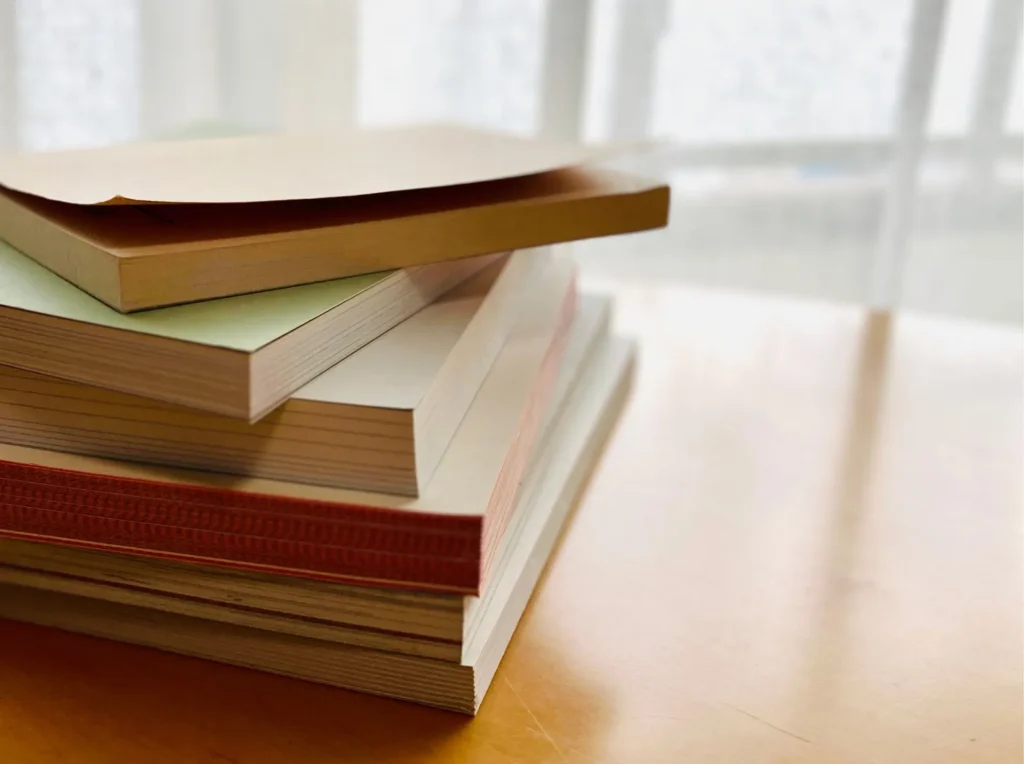
いざ司法書士が書籍を出版しようと思い立っても、テーマをどのように決めればよいか悩むでしょう。
読者の心に響き、かつ司法書士の専門性を最大限に活かすテーマを見つけるためのプロセスは、次の通りです。
- 自身の強み・専門性の棚卸し
- 読者ターゲットの設定
- 読者ニーズの研究
- 書籍タイトル・副題のネーミング
ここからは、書籍テーマ決めの流れを解説するので、詳しく見ていきましょう。
1.自身の強み・専門性の棚卸し
相続・不動産・商業登記など得意分野を明確にし、どのようなジャンルに特化した書籍にするか検討しましょう。
また、特殊な案件や解決が困難だった事例など、自身が経験した内容を盛り込むと、他の司法書士が出版した書籍と差別化できます。
たとえば、相続手続きの中でも「複雑な家族関係での遺産分割の対処法」や「中小企業の事業承継で大変だったこと」といった具体的な問題を掲載すると、書籍に独自性を生み出せるのでおすすめです。
2.読者ターゲットの設定
自分の強みや専門性を棚卸しできたら、どのような人に向けて出版するのかターゲットを決めます。
「成年後見人について悩んでいる個人」や「会社登記や債務整理が分からない事業者」など、具体的に挙げましょう。
具体的な読者ターゲットを想定することで、書籍の内容・表現方法・詳しさなどを調整できます。
3.読者ニーズの研究
日常の業務で受ける質問や相談を分析し、読者は「どのようなことが知りたいのか」「疑問を解決するために何を述べるべきか」を研究しましょう。
実務経験者だからこそ伝えられる価値を明文化して、分かりやすく解説できる内容をピックアップします。
どうしても思いつかない場合は、インターネット検索で多く見られるキーワードや、SNSでの話題などを参考にしてみてください。
4.書籍タイトル・副題のネーミング
タイトルと副題の付け方は、読者の第一印象を左右するだけでなく、検索結果での表示やSNSでの拡散にも影響するため、書籍の売上に直結する重要な要素です。
司法書士の書籍であれば、「相続 登記」「会社設立 手続き」など、読者が検索に使いそうなキーワードをタイトルに含めることで、検索エンジンでもヒットしやすくなります。
一方で、副題には、「忙しい人でも5日でわかる」「事例付きでやさしく解説」など、読者の悩みやベネフィット(利点)に寄り添った表現を盛り込むと、クリック率が上がりやすくなります。
たとえば、次のように「検索に強いキーワード」と「感情に響く訴求」の両方を組み合わせることが理想的です。
- 『相続登記の教科書』+副題「家族が揉めないために司法書士が書いた手続き完全ガイド」
- 『会社設立・運営ガイド』+副題「小さな会社の大きな落とし穴とその回避法」
ただし、商業出版では出版社の編集者がタイトルや副題に介入するケースがほとんどです。
そのため、自分の意図したタイトルが必ずしもそのまま採用されるとは限りません。
出版社が市場調査をもとに、より売れやすい表現にリライトすることもあります。
また、タイトルに「司法書士」「代表司法書士」「司法書士法人代表」などの肩書きを活用すると、専門家としての信頼感やブランディング効果を高めることもできます。
肩書きは本文ではなく表紙や著者プロフィールにも反映されるため、事前に出版社側とよく相談しておきましょう。
司法書士が商業出版するメリット

司法書士が商業出版するメリットは、編集者・デザイナー・マーケターなど専門職が関わることで、構成や校閲の精度、装丁デザイン、販売戦略など各段階の質が高くなり、読者の満足度も高い書籍に仕上がる点です。
さらに、大手出版社から書籍が出版できれば、司法書士としての専門性や信頼性を高められ、確固たるブランディングにもつながるでしょう。
全国規模でチェーン展開されている書店やオンラインストアに流通するため、多くの方に書籍が届く可能性があります。
ただし、出版社によっては全国書店に並ばず、オンラインストア限定となるケースもあるため、流通ルートや取次契約の有無も確認しておきましょう。
たとえば、一般向けの実用書やビジネス書ジャンルでは、初版3,000〜5,000部で全国販売されるケースも見られます(※内容や出版社によって大きく異なります)。
オンライン書店(Amazon・楽天ブックス)との併売により、地方の読者にも届く可能性が高まるでしょう。
司法書士が商業出版するデメリット
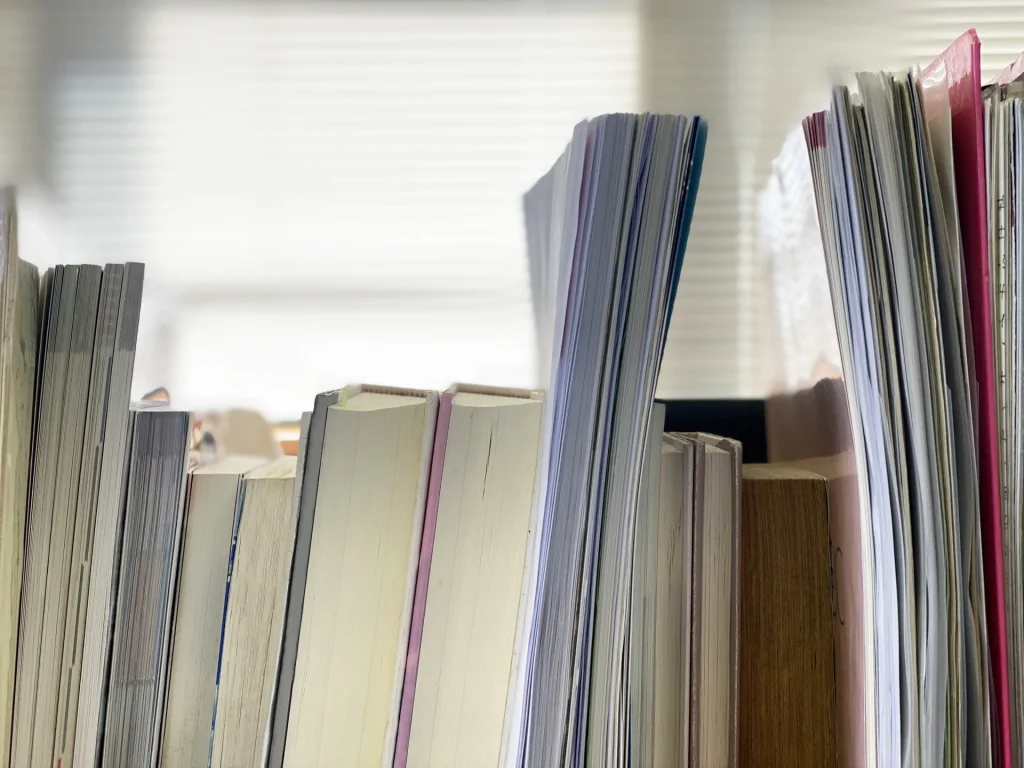
司法書士が商業出版するデメリットは、出版社の意向や市場のニーズに合わせて内容を調整する必要があるため、司法書士自身の意見がすべて通るとは限らないことです。
加えて、企画の採用競争率が高く、出版までに長い時間がかかることがある点も考慮しなければなりません。
出版社のスケジュールに合わせる必要があり、自身のペースで執筆したり、出版するタイミングを決めたりすることもできません。
また、国内で発行された出版物については、国立国会図書館法第25条に基づき、発行後30日以内に1部を国立国会図書館へ納本する義務があります。
前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
引用元:国立国会図書館法 第25条
納本は、国立国会図書館に直接持参するか、郵送または宅配便で送付する必要があり、面倒に感じられるでしょう。
ただし、納本は完全なデメリットとは言い切れません。
「国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)」「CiNii Books」「Webcat Plus」などの情報インデックスにも連動して登録されるため、インターネットで検索した際に自著がヒットする可能性が高まります。
国立国会図書館法という法律によって義務付けられているとはいえ、少なからずメリットがあるため、必ず納本しましょう。
司法書士が自費出版するメリット
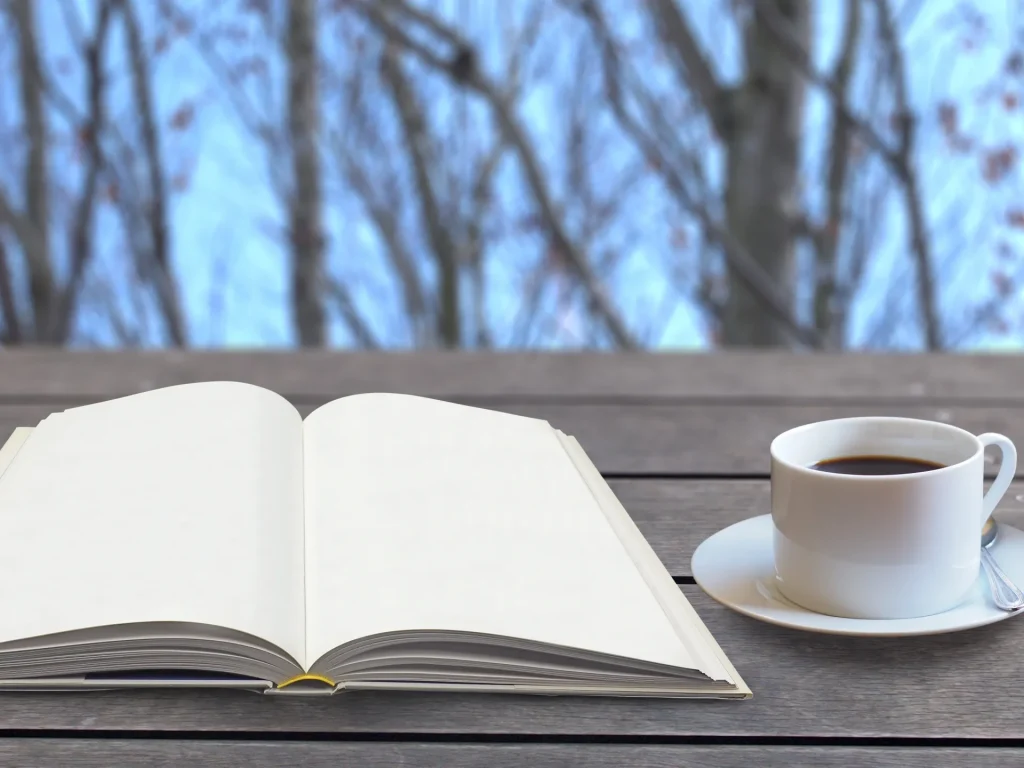
司法書士が自費出版するメリットは、費用を捻出できるのであれば、基本的に誰でも出版できる点です。
たとえば、POD(オンデマンド出版)であれば数十万円程度から始められるため、初めての出版にも適しています。
伝えたい内容や表現方法を自分で自由に決められるので、ニッチなテーマや専門性の高い内容でも出版しやすいでしょう。
さらに、自身の都合に合わせて出版のタイミングを決められるため、日々の司法書士業務と並行して進めやすいことも魅力です。
司法書士が自費出版するデメリット
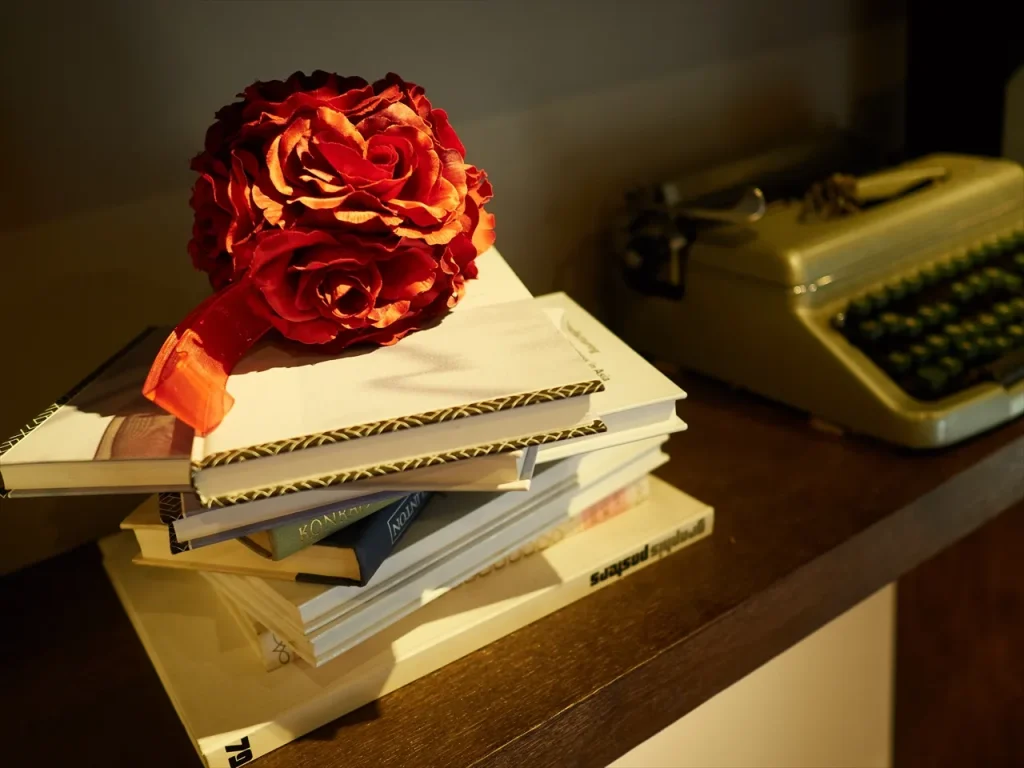
司法書士が自費出版するデメリットは、企画・編集・制作・宣伝・流通にかかる費用をすべて司法書士自身が負担するため、数百万円単位の費用がかかることがある点です。
たとえば、原稿執筆・編集・校正・デザイン・印刷・流通・広告宣伝などをすべて外注すると、総額で200〜300万円を超えるケースもあります。
また、万が一トラブルが起こった場合、出版社の後ろ盾がないので、すべて自分で対応しなければなりません。
書店への流通や宣伝活動も司法書士自身が行う必要があるため、多くの読者に届けることが難しいでしょう。
目的や希望によって司法書士におすすめの出版方法は異なる
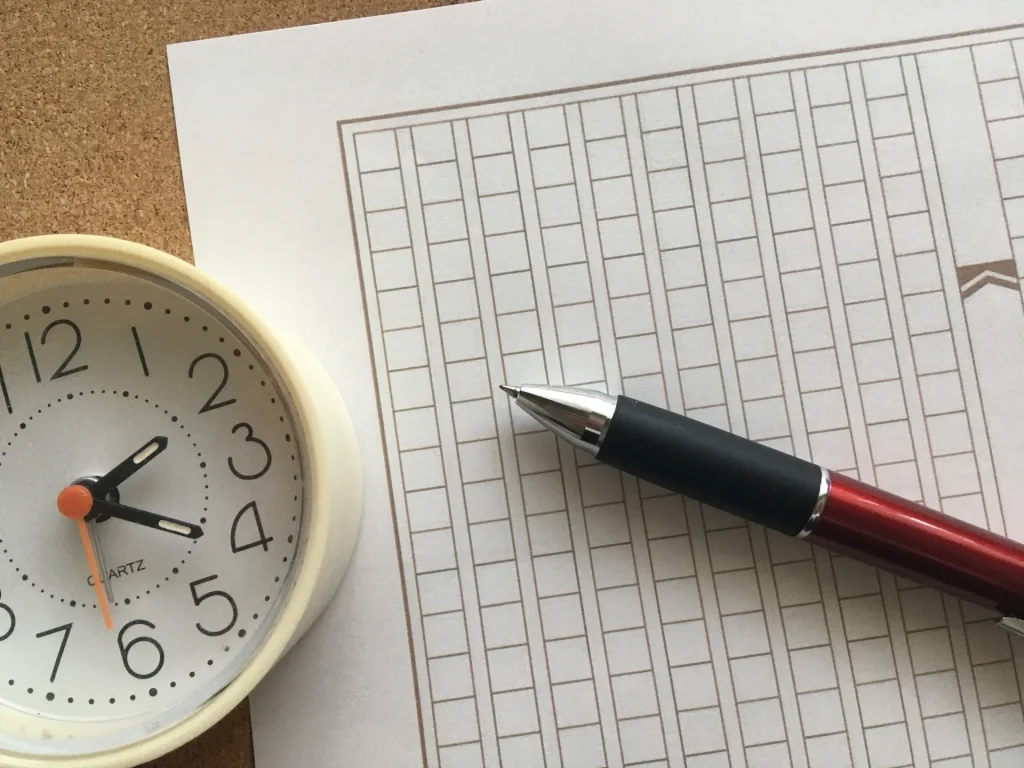
司法書士が書籍出版を検討する際、商業出版と自費出版のどちらが最適かは、目的と希望によって異なります。
たとえば「費用を抑えて信頼性を重視するなら商業出版」「自由度と専門性を優先するなら自費出版」など、出版目的に応じた選び方の基準を明確にすることが大切です。
もし「知名度を上げたい」「大手出版社のブランド力を借りて信頼性を高めたい」「費用をかけずにプロのサポートを受けたい」と考えるのであれば、商業出版が適しています。
内容や表現の自由度は低くなりますが、出版社が有する流通網と販促力によって、より多くの読者にリーチできる可能性が高いです。
一方で「特定のニッチな分野に特化した書籍を出したい」「内容やデザインを完全に自分の思い通りにしたい」「なるべく多くの印税収入を得たい」と考えるのであれば、自費出版がおすすめです。
費用の負担は大きいものの、制作の全工程において自分で意思決定ができ、スピーディーに書籍を出版できます。
それぞれのメリット・デメリットを十分に比較検討し、出版目的・予算・書籍に求める自由度などを考慮して、最適な出版方法を選択することが重要です。
【司法書士向け】出版社の適切な選び方
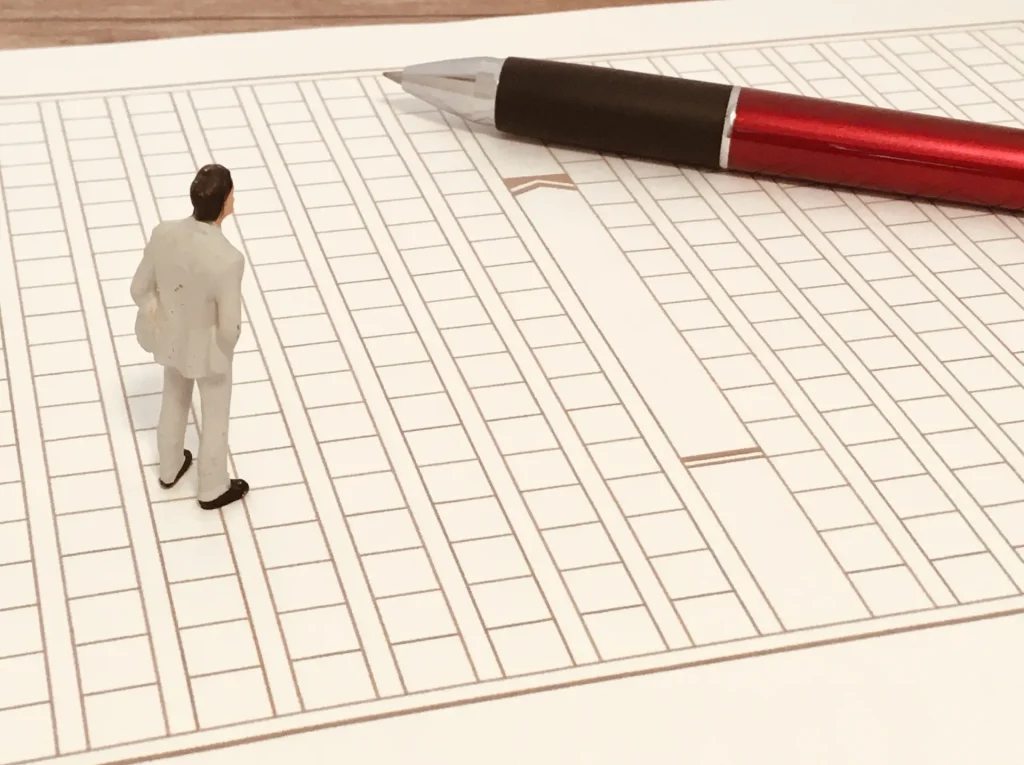
商業出版にしろ自費出版にしろ、スムーズな書籍を制作したり販売ルールを確保したりするためにも、出版社選びはとても大切です。
司法書士は以下の点を考慮して、慎重に出版社を選定しましょう。
- サポート体制が充分かどうか
- 司法書士に特化した書籍を出版した実績があるか
- 予算内で出版できそうか
ここからは、出版社の適切な選び方について紹介します。
サポート体制が充分かどうか
出版社のサポート体制は、ターゲットや本の帯のキャッチコピーなどを担当する「編集サポート」と、メディアや広告への出稿やPRの全体設計から施策などを担当する「販促サポート」に分かれます。
どちらも書籍の出版においては重要なので、サポート体制が充分かどうか見極めましょう。
司法書士に特化した書籍を出版した実績があるか
法律に関する専門性の高い内容を取り扱うため、司法書士に関する書籍を実際に出版した経験がある出版社を選んでください。
編集サポートでは内容を適切に校閲してもらえ、販促サポートでは士業に特化した販売ルートを使ってもらえる可能性が高いです。
さらに、司法書士書籍を扱った実績のある出版社であれば、取次・Amazon・直販・セミナー配布など販路ごとの扱いや、ISBN(書籍を特定するための世界共通の番号)やPOD出版(注文に応じて必要な数だけ書籍を印刷・製本する出版方式)の取得要否といった違いを的確に理解していることが多いです。
ISBN(書籍を特定するための世界共通の番号)は商業出版では必須です。
しかし、自費出版やPOD出版では販売方法によっては未取得でも出版可能です。
ただし、書店流通を希望する場合は取得が推奨されます。
こうした知識の有無が、書籍が「正式な出版物」として認知されるかどうかを左右するため、出版社選びの判断軸として検討しましょう。
予算内で出版できそうか
発行部数を多めに設定したり、デザインに凝ったりすると、莫大な費用がかかってしまいます。
前もって予算を決めておいて、その中で希望通りの内容で出版できるかチェックしましょう。
なお、商業出版の場合は、印税率や支払い条件について事前に明確にして、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
出版後が勝負!司法書士が書籍を集客・信頼獲得に活かす方法

書籍は出版するまでの道のりが長いですが、集客や信頼獲得に活かすためには出版した後の考え方やアクションこそが重要です。
- 続編やシリーズ化を狙う
- 書籍を活用して事業拡大する
- 業界内での地位向上に活用する
ここからは、司法書士が出版した書籍を最大限に活用するための戦略を解説します。
続編やシリーズ化を狙う
読者の反応に基づいて新たに企画を立てると、書籍の続編の発売やシリーズ化ができるでしょう。
続編やシリーズ化は、司法書士の専門性をより深く掘り下げてアピールできるだけでなく、読者のリピート購入を促して問い合わせにつながる効果も期待できます。
たとえば、続編を刊行することで、出版後に月間問い合わせ件数が2倍になる、といったケースが考えられます。
書籍を活用して事業拡大する
司法書士自身の影響力が書籍だけに留まらず、著者としての講演や研修が依頼へ発展する可能性があります。
企業の顧問契約の獲得や、メディアへの出演機会の増加といった展開が期待できるため、書籍を足がかりにした事業拡大は十分に現実的です。
業界内での地位向上に活用する
書籍は司法書士の知識と経験が体系的にまとめられた「名刺」のようなものなので、同業者や他士業の専門家に対し、自身の専門性を明確に伝えるツールとして活用できます。
そのため、学会・研究会で発表する機会が得られたり、後進指導・教育に携われたりする可能性も秘めているでしょう。
書籍の売上や出版数が評価され、業界内での知名度や信頼性が向上した結果として、業界団体での役職に就任するケースもあります。
ただし、書籍出版はあくまで複数ある評価要素の一つとされています。
司法書士が書籍出版後の導線作りに悩んだらドットアンドノードへご相談ください

今回は、司法書士の書籍の出版について解説しました。
書籍出版は、専門家としての地位を確立し、社会貢献を果たすうえで極めて有効な手段です。
また、講演やセミナー活動への展開、ひいては事務所の集客力向上や事業拡大にも役立ちます。
商業出版と自費出版にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、自身の目的や希望に応じて最適な方法を選択することが重要です。
もし「集客を目的として書籍を出版したい」「もっと自分の知名度を上げたい」という場合は、ぜひドットアンドノードにご相談ください。
弊社では司法書士に特化したホームページ制作をはじめ、広告の分析と最適化、地域特性に合わせた広告の調整といったサービスを展開しております。
Web集客でお悩みの司法書士の方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。