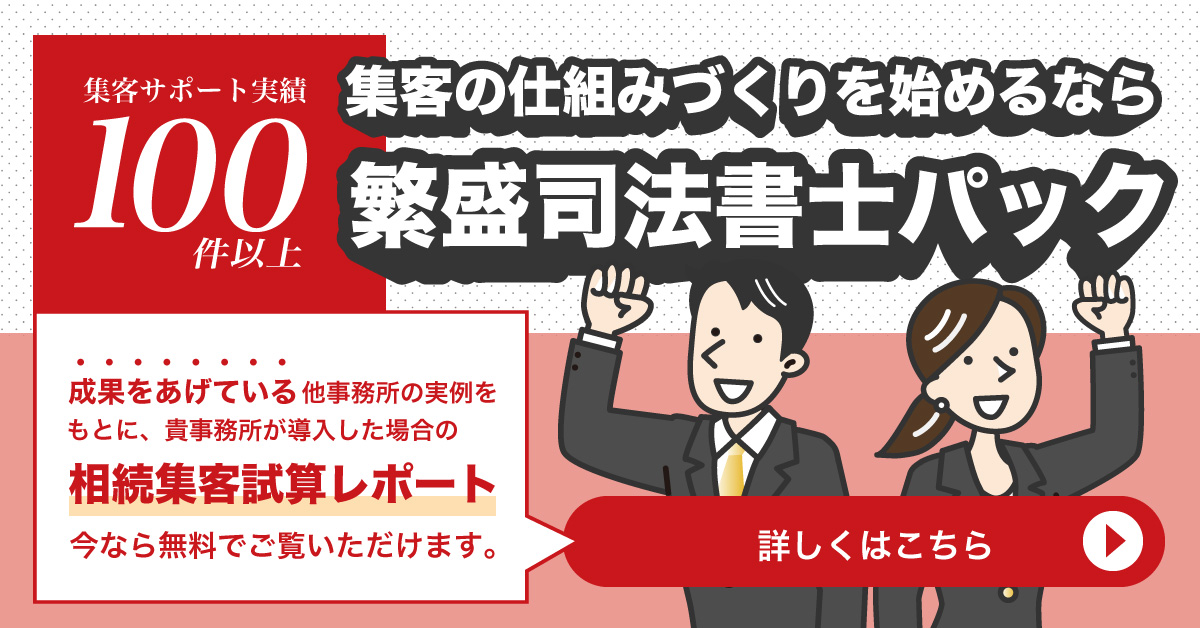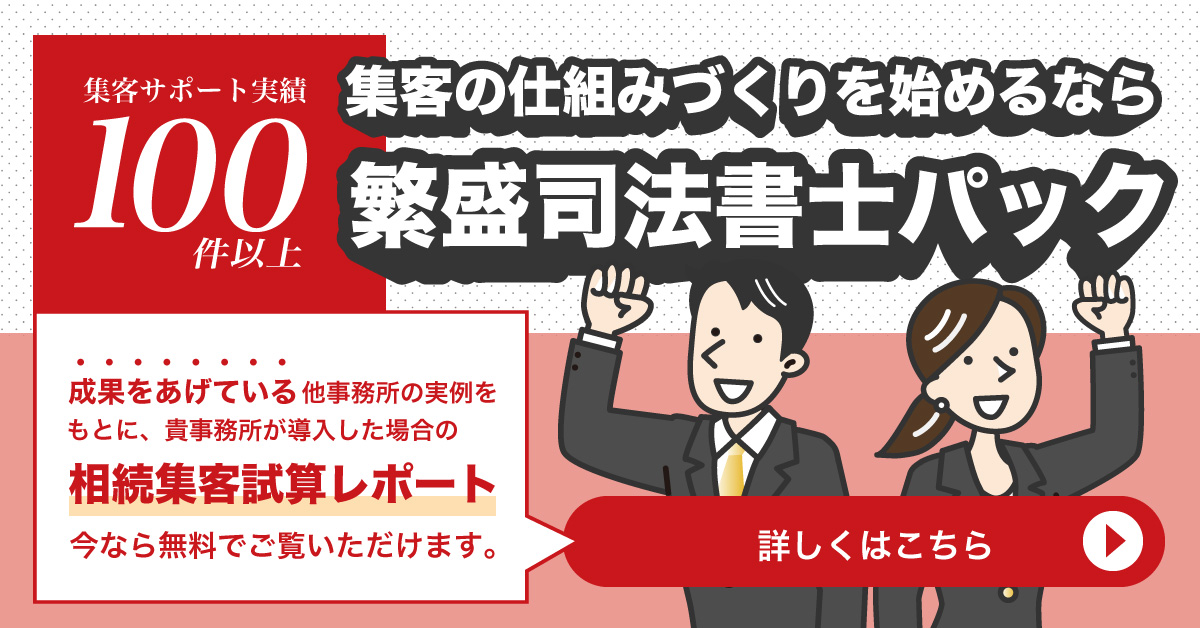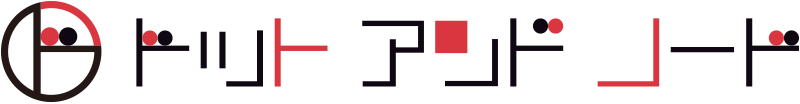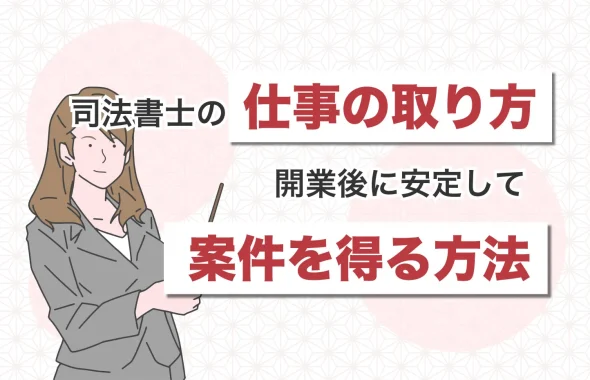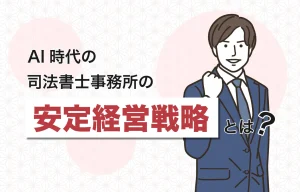司法書士として独立開業を考えている方のなかには、資金面で不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そのような資金面での課題を解消するためにできるのが、補助金の活用です。
補助金を活用することで、司法書士事務所の開業を円滑に進められ、司法書士事務所の運営を軌道に乗せやすくなります。
この記事では、司法書士が開業時に活用できる補助金を紹介するとともに、補助金の申請方法や申請時の注意点について解説します。
司法書士の開業に必要な初期費用
前提知識として、司法書士の開業に必要な初期費用について解説します。
司法書士の開業に必要な初期費用の内訳は、以下のとおりです。
- 司法書士登録料
- 事務所の物件費用
- 事務所の内装・設備
- 備品・消耗品
- 通信費や光熱費
- ホームページやソフトウェア
それぞれの項目に対してかかる大まかな費用は下記の表をご覧ください。
| 項目
|
概算費用
|
| 司法書士登録料・登録免許税等 |
10万円前後(年会費別途) |
| 事務所の物件関連費用 |
30万円〜 |
| 事務所の内装・設備 |
15万円〜 |
| 備品・消耗品 |
3万円〜 |
| 通信費や光熱費の初期費用 |
5万円〜 |
| ホームページやソフトウェア導入費 |
10万円〜 |
なお、いずれの項目に関しても、事務所の開業地域による相場の差や選ぶ物件や設備の種類やランクによって金額は異なります。
また、上記に記載している初期費用の項目は、必ずかかるものや金額が大きくなりがちなものです。
表に記載している以外にも、広告費や保険代、営業活動費など、さまざまな費用が発生する可能性があります。
上の表内の金額だけでも合計金額は73万円からなので、そのほかの費用も合わせると、最低でも100万円程度は初期費用が必要になると考えて準備を進めましょう。
司法書士は開業時に補助金をもらえる?
結論からいうと、司法書士は開業時に補助金をもらえる可能性があります。
ただし、補助金をもらうためには、各補助金の支給条件を満たしており、なおかつ審査に通過する必要があります。
申請さえすれば、全ての司法書士が補助金をもらえるというわけではない点には注意が必要です。
これらの前提を頭に入れたうえで、下記のステップで補助金を活用すると良いでしょう。
- 対象となる補助金を調べる
- 申請の必要書類を確認・準備する
- 期限までに申請書類等を提出する
申請できそうな補助金がわかったら、条件と期限をよく確認して、書類などの準備を早めに進めていくのがおすすめです。
補助金と助成金の違い
「補助金」と「助成金」は似ているため、どのような違いがあるのかわかりづらいですが、一般的に下記のような違いがあります。
| 項目
|
補助金
|
助成金
|
| 支給条件
|
条件を満たした上で、審査に通過した場合 |
条件を満たせば原則支給 |
| 競争性
|
あり |
なし |
| 使途制限
|
厳しい |
比較的自由 |
| 申請難易度
|
高い |
低い |
| 支給時期
|
後払いが多い |
申請後にすぐ支給されることも多い |
特に、補助金には基本的に審査があるため、必然的に競争性が高くなります。
そのため、申請書類に不備がないかという基本的なことはもちろん、事業計画に無理はないかなどを客観的な視点で確認することが重要です。
司法書士が活用できる主な補助金
司法書士が活用できる主な補助金は、以下のとおりです。
- 小規模事業者持続化補助金
- 創業補助金
- IT導入補助金
補助金ごとに支給の対象となる費用や補助率が異なるので、概要と申請条件などを順に見ていきましょう。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」とは、商工会議所や商工会が支援を行う補助金制度で、小規模事業者が行う事業拡大や販路開拓を支援するためのものです。
補助率と上限は下の表をご覧ください。
| 補助率
|
対象経費の2/3
|
| 上限額 |
50万円(条件によってはそれ以上の場合もあり) |
主な補助対象は、下記のとおりです。
- 広告宣伝費
- ウェブサイト制作費用
- 販路開拓または業務効率化のためのシステム導入費
小規模事業者持続化補助金の申請と利用には、事業報告書の作成と支給後の事業報告が必要です。
支給後も報告が必要であることも頭に入れて、補助金の申請を行いましょう。
創業補助金
「創業補助金」とは、新規開業者の支援を目的とし、主に地方自治体が実施している場合が多い補助金です。
補助金の支給内容や申請条件などは、地域や年度によって異なるので、自治体および中小企業庁のホームページなどで最新情報をチェックするようにしましょう。
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、経済産業省が主体として中小企業や小規模事業者を支援する補助金で、ITツールの導入により業務効率や売上の向上を図ることを目的としています。
補助金額の目安は下の表にまとめています。
| 補助率
|
1/2〜2/3 |
| 補助額(導入内容による) |
5〜450万円(導入内容による) |
また、主な補助対象は、下記のとおりです。
- 業務効率化ツール導入
- 販売促進・集客ツール導入
- セキュリティ対策
なお、小規模事業者持続化補助金と同様、支給決定以降、事業実施効果報告を行う必要があります。
司法書士の補助金申請方法
補助金に関する審査を通過するためには、申請方法を正しく理解して、不備なく必要書類の申請を完了させることが重要です。
今回お伝えする補助金の申請方法を確認することに加え、ホームページに掲載されている詳細を確認し、常に最新情報を元に準備しましょう。
以下からは、司法書士が活用できる3つの補助金について、具体的な申請方法を解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化給付金の申請手順は、下記のとおりです。
- 経営計画書・補助事業計画書の作成
- 管轄の商工会議所へ「事業支援計画書」の交付を依頼
- 事務局へ申請書類を送付
申請の際に、商工会議所や商工会が発行する「事業支援計画書」が必要となるので、事前に作成支援や助言を受けるようにしましょう。
申請書、申請様式や申請窓口などの詳しい内容は、小規模事業者持続化補助金の公式ホームページから確認できます。
なお、申請書類に不備や不足があると審査の対象外となってしまうので、申請手続き前によく確認してから送付しましょう。
創業補助金
創業補助金は、それぞれの自治体などが提供している補助金のため、申請方法はその補助金を提供する機関や年度によって異なります。
一般的な申請手順は大まかに下記のとおりです。
申請書類の際、一般的に求められる書類として、以下のものが挙げられます。
詳しい内容は、実際に補助金を取り扱っている自治体などのホームページや担当窓口でご確認ください。
IT導入補助金
IT導入補助金の申請手順は、下記のとおりです。
- GビズIDの取得
- 「SECURITY ACTION」宣言実施
- IT事業者の選定・ITツールの選定
- 交付申請
交付申請の要件に、GビズIDの発行が含まれていますが、発行までに約2週間ほどかかるので、早めに発行手続きをする必要があります。
また、GビズIDの発行とともに、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言をすることも要件の一つです。
「SECURITY ACTION」とは、中小企業および小規模事業者が、情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言する制度で、宣言完了から宣言済みアカウントとして反映されるまでさらに2〜3日かかります。
いずれも即時反映ではなく時間がかかることを考え、IT導入補助金を申請する際は、可能な限り早めに準備するように心がけましょう。
司法書士が補助金の申請・活用をする際の注意点
司法書士が補助金の申請・活用する際に注意すべき点は、下記のとおりです。
- 補助金は後払いになる
- 事業実施期間外の経費は補助対象にならない
- 事務手続きが不十分だと補助金の受給ができない場合がある
- 会計検査院の調査対象となる場合がある
それぞれの内容を順に見ていきましょう。
補助金は後払いになる
ほとんどの補助金は後払いになることに注意が必要です。
たとえば、対象経費300万円のうち2/3の補助金が出る場合、一度300万円の支払いを自社で行ってから、後で200万円が支給されることになります。
差額の100万円だけを用意すれば良いというわけではないので、問題なく資金繰りができるように事業計画と資金計画を立てることが重要です。
もしも、自己資金に余裕がない場合は、銀行などからの融資を利用して一度費用を立て替えられるように資金を工面するというのも一つの手です。
いずれの場合も、資金計画に無理がないか、資金を投じる先は開業準備として適正であるか、慎重に検討するよう心がけましょう。
事業実施期間外の経費は補助対象にならない
補助金は支給の対象となる期間が定められていることが一般的です。
そのため、対象となる支給期間内でない事業実施期間外の経費は補助対象にならない点に注意しましょう。
事業期間は年度末までではなく、少し早めの日程で締められることが多いので、事前に事業実施期間の対象を確認しておくことが重要です。
事務手続きが不十分だと補助金の受給ができない場合がある
補助金制度を利用する場合、支給決定後にも注意しなければならないことがあります。
まず、支給対象となる事業期間終了後、期限内に報告書や金額の証明書などの必要書類を提出しなければならない補助金がほとんどです。
必要な書類を提出しなかったり、経費の取り扱いが雑で目的外の用途に使っていたりという場合、補助金の支給が拒否される可能性があります。
司法書士の開業時に補助金の支給を問題なく受けられるかどうかは、その後の事務所経営に大きな影響を与えるのでくれぐれも注意しましょう。
なお、補助金の多くは、申請の段階で事業計画書を提出したうえで、用途が限定されて補助金の支給決定が下されます。
補助金の支給要件に沿った支出であるか、事前によく確認して経費を投入することはもちろん、報告書などの書類作成で不備や不足がないように注意することが重要です。
会計検査院の調査対象となる場合がある
補助金の支給を受けた企業や事業主は、会計検査院の調査対象となる場合があります。
当然、正当な目的で費用を支出および記録し、事務処理をきちんと行っていれば、何も問題はありません。
雑に処理したり、正当な理由以外で費用を支出していたり、何らかの問題があると、調査が入った際に指摘を受ける可能性があります。
会計検査院の調査が入る可能性があることを念頭におきながら、しっかりと事務処理を行うことが重要です。
補助金を活用することで開業費用を抑えられるという大きなメリットがあるのはもちろんですが、事務的な処理が増えて時間が取られてしまうというデメリットも少なからず存在します。
とはいえ、補助金を活用することは、司法書士事務所開業を円滑に進めるために役立ちます。
メリットを最大限に活かすためにも、時間的な余裕を持って補助金申請の準備や事務処理を進めることを心がけましょう。
司法書士が補助金を活用してできること
司法書士が開業時に補助金を活用する最大のメリットは、開業費用を削減できるということです。
司法書士事務所を開業・運営していくうえで、一般的にもっともお金がかかる時期は開業時です。
補助金の対象となる経費は基本的に限定されているので、補助金を充てられる支出とそうでない支出の分類をしながら計画的に資金繰りを行うことが重要です。
開業時に補助金を使って自己資金の支出を抑えることで、浮いたお金をほかの部分に回すことも可能になります。
では、具体的に司法書士が補助金を活用することでできることを順に見ていきましょう。
事務所の設備投資
司法書士が補助金を活用してできることの一つが、事務所の設備投資です。
司法書士が開業をするのにかかる費用のうち、事務所設備を整えるためにかかる費用の割合は高くなる傾向にあります。
事務所設備投資自体に適用できる補助金は少ないので、まずは補助金が直接的に適用可能なものから利用し、浮いた自己資金を設備投資に回せるようにしましょう。
事務所運営を円滑にするシステムの導入
顧客獲得・マーケティング強化のためのシステム導入は、補助金の対象となることが多いので、特に積極的に補助金を活用したいところです。
近年、デジタル化が進んでいることで、顧客の多くはインターネットを通じて情報収集や案件依頼をすることが多くなっています。
そのため、競合に勝ち、新規顧客を獲得し続けていくためにもIT関連のシステムを整備しておくことが重要です。
顧客獲得やマーケティング強化に加え、事務所運営そのものを円滑にするためのシステムも合わせて検討しましょう。
具体的には、下記のようなシステムの導入がおすすめです。
- 集客関連ツール(ホームページやSNS連携)
- 業務管理システム
- 会計・経理管理システム
- 顧客管理関連システム
- 書類管理システム(クラウド等)
当然、開業時に全てを完璧に整備する必要はないので、費用対効果なども加味しながら必要なシステムを精査して導入しましょう。
司法書士の開業は補助金を活用しよう
この記事では、司法書士が開業時に活用できる補助金について解説してきました。
補助金をうまく活用し、初期費用の自己資金比率を抑えることで、開業後の事務所運営をより円滑に進めることができます。
司法書士の開業後、最初の課題となる新規顧客の獲得、集客を成功させるにはWeb集客の活用は必要不可欠ですが、Web集客には最低限の知識が必要です。
開業してしばらくの間は、どうしても事務所の運営業務そのものに時間を取られてしまうので、Web集客まで自力で行うことは困難であるのが現実です。
そのため、補助金を活用して抑えた費用を元に、Web集客はプロに依頼するのがおすすめです。
ドットアンドノードでは、司法書士向けのWeb集客をサポートするプランを提供しています。
ホームページ制作をはじめ、Web広告の掲載やSEO対策など、Web集客に関するサービスを幅広く手がけています。
Web集客で困ったときはもちろん、そもそもWeb集客で何から手をつければよいかわからないという場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
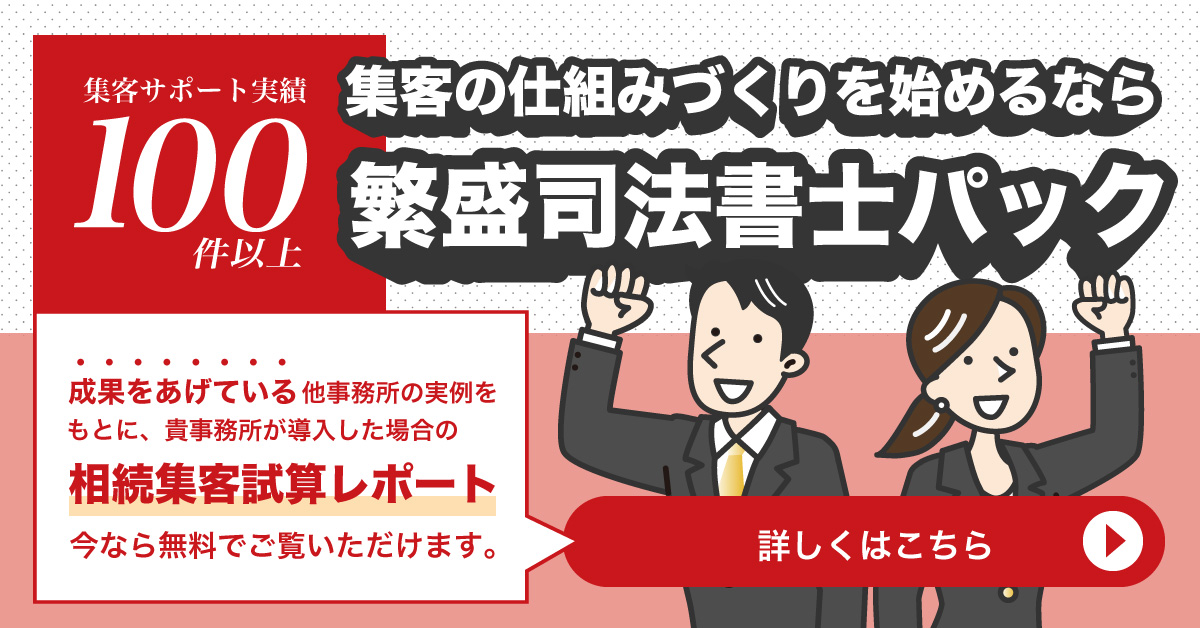
著者:稲垣 達也(いながき たつや)
ドットアンドノード株式会社 代表取締役/士業専門Web集客コンサルタント/マーケティング戦略家
横浜国立大学経済学部卒。商社、不動産業界を経て2018年よりウェブマーケティングに取り組む。司法書士・行政書士・弁護士などの士業向けに、出版を起点としたブランディング・Web集客支援を行っている。
「士業の専門性を、もっと多くの人に伝えたい」との想いから、書籍×Web×広告を融合した戦略設計を提案。支援事例の中では、問い合わせ30倍、クラウドファンディングで1070万円達成など多数の実績を持つ。
東洋経済オンライン、朝日新聞デジタル、@DIMEなど掲載メディアは60社以上。講演・研修登壇実績も豊富。
司法書士さんの独立や集客のご相談はこちらから