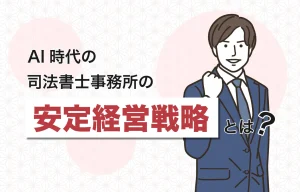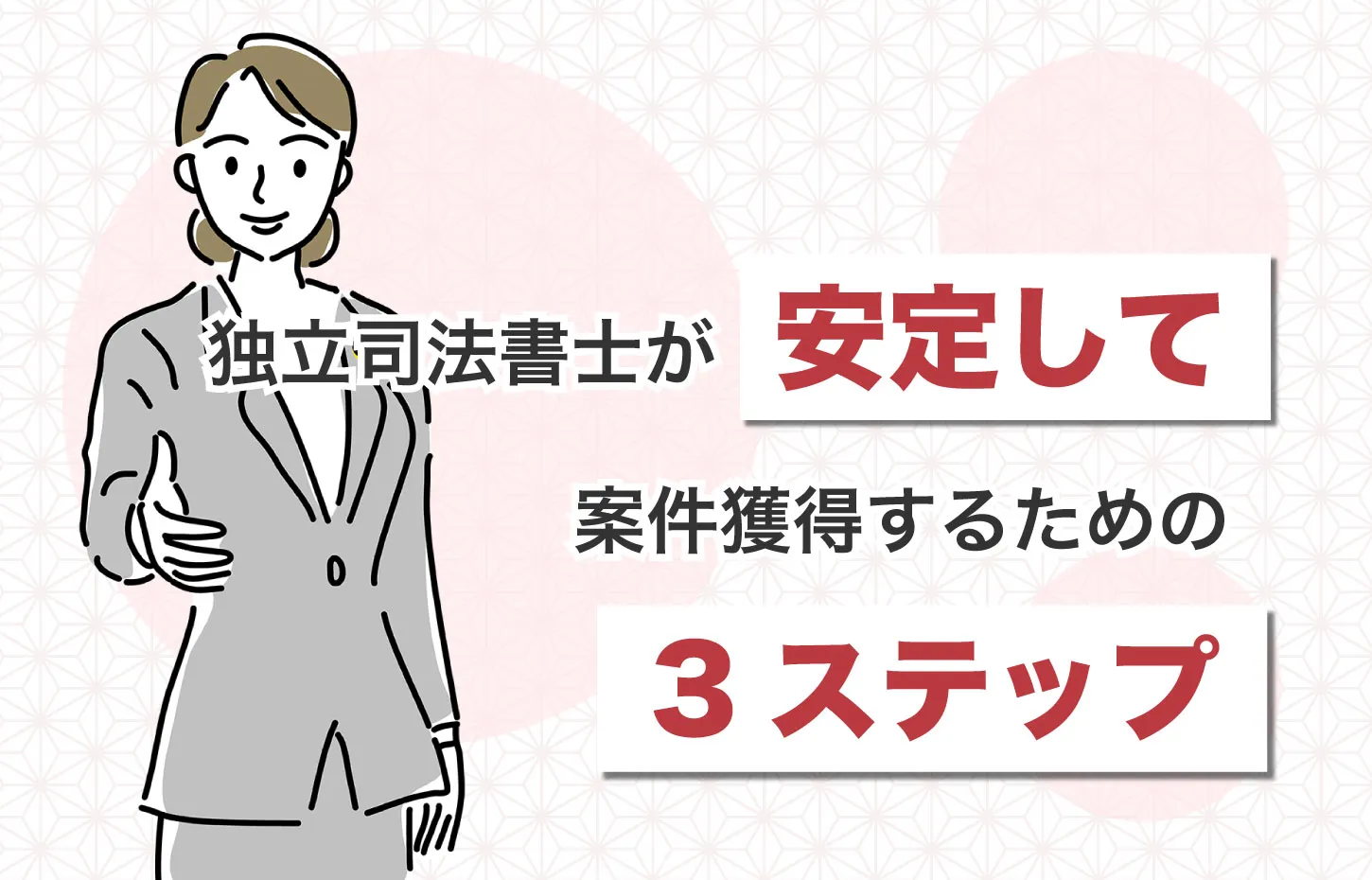
独立司法書士が安定して案件獲得するための3ステップ
独立開業した司法書士や、これから独立を目指す方にとって、安定して案件を獲得し続けることは大きな課題です。
「独立したけれど毎月の収入が安定しない」「独立に憧れはあるが継続的に仕事を取れるか不安」とお悩みではありませんか?
また、受任を増やしたいと思っているのに、日々の業務に追われて新規案件の営業まで手が回らないという声も少なくありません。
この記事では、安定して案件を獲得するための方法を3ステップで順序立ててご紹介します。
効率的に案件を獲得したい方や、営業が苦手だと感じる方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ステップ1:自分に合った案件を見極め、司法書士としての専門分野を明確にする

まず取り組むべきなのは、自分がどんな案件に向いているのかを見極めて、専門分野をはっきりさせること。
目指す方向が定まらないと、依頼された業務をその場しのぎでこなすことになり、業務内容や収入に偏りが生じてしまいます。
当ステップで知っておきたいこととして、次の項目が挙げられます。
- 何でも対応すると長期的に逆効果なことがある
- 専門分野に特化するメリットがある
- 自分に合った案件を見極める
ここからは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
何でも対応すると長期的に逆効果なことがある
開業当初は、「どんな案件でも良いから受けたい」「仕事があるだけ有難い」という心理になる方も多いのではないでしょうか?
収入や経験不足の不安から、目の前の依頼を全て受けたくなるのは当然のことです。
しかし、「何でも屋」のままであり続けることは、長期的な視点で見ると大きなリスクになり得ます。
希望する案件を選ぶことができないと、案件単価の低い仕事が続いたり、自分に合っていない業務で疲弊する恐れがあるからです。
焦りや不安な気持ちは分かりますが、まずは一度立ち止まり、事業のブランディングや方向性をしっかりと定めましょう。
専門分野に特化するとメリットがある
司法書士として専門分野を明確にすることは、競合他社との差別化を図り、効率的な集客を可能にします。
「誰に、どのような価値を提供できるのか」が明らかになるので、広告や営業の軸に一貫性を持たせられ、顧客の信頼を得やすくなるからです。
たとえば、相続登記に特化した場合、顧客は個人で年齢層が高めと予想されるので、無料相談会を地域で開くなどターゲットに適した営業活動が行えます。
また、顧客としても幅広い業務を謳う司法書士より、自分の相談内容に特化した司法書士の方を選びたいと思うでしょう。
専門分野を明確にすることは、営業の土台となります。
自分に合った案件を見極める
自分の特性や市場との相性を見極めるうえで、ヒントとなる視点は以下の通りです。
- 得意な業務から考える
- 過去の経験や実績から考える
- 案件単価や業務負荷、ニーズから考える
順に詳しく見てみましょう。
得意な業務から考える
自分が「得意」または「スムーズに進められる」と感じる業務を基準に考えてみましょう。
苦手意識がないだけでも対応スピードやミスの少なさに直結し、顧客満足度の向上につながります。
説明力に自信がある方であれば、相談対応が多くなる相続手続きや成年後見などの分野が向いているかもしれません。
逆に、地道な書類作成やルールに忠実な作業が得意な方は、不動産登記や商業登記で力を発揮できる可能性があります。
得意な業務を専門分野にすることは、仕事に対するモチベーション維持にも効果的です。
過去の経験や実績から考える
過去に経験した業務で、「顧客からの反応が良かった」「トラブルが起きなかった」と感じる案件もあなたに合っている可能性があります。
また、開業前に勤務していた事務所で多く扱っていた業務や、受任から完了までの流れを一通り経験している分野があれば、それも大きな強みとなります。
特に独立したばかりの頃は、慣れている業務かどうかといった実務的な観点も、大切な判断材料です。
自分ではあまり意識していない業務についても、過去の周りの反応や実績件数がどれくらいあるかを振り返ってみましょう。
案件単価や業務負荷、ニーズから考える
事業を継続するうえで、かかる時間や手間に見合った利益(時間単価)が確保できるか、継続して依頼が見込めるかという視点も非常に重要です。
一見すると高単価の案件であっても、業務負荷が著しく高いと実質的な収益性は低くなってしまいます。
たとえば、相続関連の業務は戸籍収集や関係者の調整が必要となり、業務負荷が高くなる傾向にあります。
また、需要が一時的なものであれば、安定した収益にはつながらないので注意しましょう。
たとえば、不動産登記は個人がオンライン申請を行うケースが増えていますが、企業と顧問契約が結べれば安定した受注が見込めるでしょう。
以下の表には、主な業務ごとの単価の変動要素や業務負荷、需要の傾向をまとめました。
専門分野を考える際の参考にしてみてください。
| 単価の変動要素 |
業務負荷 |
継続的な需要 |
|
|---|---|---|---|
| 不動産登記 |
不動産の評価額、登記内容 | 低~中 | 顧問化すると継続性が高い |
| 商業登記 |
資本金額、会社形態、登記内容 | 低~中 | 顧問化すると継続性が高い |
| 相続関連 |
財産総額、相続人数 | 高 | ニーズは増える、一件完結型だが定期的な営業が有効 |
| 遺言・成年後見 |
財産総額、相続人数、内容 | 高 | ニーズは増えるし、継続性が高い |
| 債務整理 |
借金総額、債権者数 | 中~高 | 安定したニーズがあるが、一件完結型 |
| 簡裁訴訟代理等 |
訴額、書類作成数、難易度 | 中~高 | 安定したニーズがあるが、一件完結型 |
ステップ2:司法書士として獲得したい案件に適した営業活動をする

自分に合った案件が明確化できたら、その案件に適した営業活動を行いましょう。
司法書士の営業方法としては、業務別に次のように分類できます。
- 不動産登記の営業方法
- 商業・法人登記の営業方法
- 相続関連業務の営業方法
- 遺言・成年後見の営業方法
- 債務整理・過払い金請求の営業方法
- 簡易訴訟代理等関係業務の営業方法
以下からは、それぞれの営業方法について詳しく解説していきます。
不動産登記の営業方法
不動産登記は、住宅購入者や不動産関係の事業者が主な依頼者となります。
個人からの直接依頼もありますが、継続的な業務量を確保するためには、不動産関係の事業者をターゲットに絞った方が良いでしょう。
そのためには、地元の不動産関係の事業者と信頼関係を構築することが重要です。
挨拶回りや不動産関係の事業者交流会に参加するなど、認知度を高めることから始めてみましょう。
商業・法人登記の営業方法
商業・法人登記では、会社を設立しようとしている起業家、中小企業経営者、NPO法人の代表者が主な依頼者です。
地元の商工会議所のイベントに積極的に参加し、経営者との接点を多く持つことが営業の第一歩となります。
創業セミナーや起業イベントなどで登記に関する相談窓口を設けるのも効果的でしょう。
また、税理士や行政書士と連携して、ワンストップでの起業支援体制を整えると、紹介による案件を獲得しやすくなります。
相続関連業務の営業方法
相続関連業務の依頼者は、60代以上の高齢者とその子ども世代が中心です。
令和6年4月から相続登記を義務化する法律が施行され、相続から3年以内に登記をしないと過料が科される可能性があります。
そのため、何から手を付ければ良いか分からないという依頼者も多く、啓発セミナーや無料相談会を開催すると効果的です。
また、タウン誌や地域新聞に記事や広告を掲載し、信頼性の高い専門家として地域での認知度を高めるのも効果的な方法です。
遺言・成年後見の営業方法
遺言書の作成や成年後見制度の活用を検討するのは、将来に不安を抱える高齢者や、障がいを持つ子の親などです。
遺言・成年後見の分野では、依頼者が「誰に相談すればいいか分からない」という不安を抱えている場合が多いもの。
したがって、不安を解消してあげる情報発信が効果的になります。
医療機関や介護施設と連携して無料相談会を行ったり、制度の分かりやすい解説を小冊子にして提供することで、案件を獲得しやすくなるでしょう。
債務整理・過払い金請求の営業方法
債務整理や過払い金請求は、借金に悩む一般消費者が依頼者になります。
検索からの流入が多いため、ホームページやブログで「司法書士と弁護士の違い」「返済が苦しいときの対処法」といったコンテンツを発信するのが集客に効果的です。
債務整理・過払い金請求の分野は競合が多いため、実績件数や口コミの高さをアピールしたり、強みを明確にすることが重要になるでしょう。
簡裁訴訟代理等関係業務の営業方法
簡裁訴訟代理等関係業務では、家賃滞納に悩む大家や、140万以下の売掛金回収に困っている中小企業経営者が主な依頼者になります。
しかし、司法書士が訴訟手続きにも対応できることは一般にあまり知られていないため、まずは認知の拡大が重要です。
不動産管理会社向けに滞納対策セミナーを開いたり、中小企業向けに訴訟制度の解説資料を提供したりするなど、啓発活動を営業に結びつけましょう。
市民相談会や法テラスでの対応を通じて、地道に信頼と実績を積み重ねると長期的に見て集客につながります。
ステップ3:効率的に案件を獲得する仕組みを作る

独立後の限られた時間やリソースの中で安定した受注を得るためには、日々の営業活動だけでなく効率的に案件を獲得する仕組み作りが必要です。
案件獲得の仕組み作りに向けては、次のような切り口での準備が挙げられます。
- 継続して案件依頼されるように仕組み化
- 対面営業なしでの案件獲得を仕組み化
ここからは、それぞれの仕組み化について詳しく見ていきましょう。
継続して案件依頼されるように仕組み化
単発で終わる案件ばかりでは、毎月の受任件数がゼロスタートとなることが多く、精神的にも経済的にも不安定になってしまいます。
そこで、継続的に案件が依頼される仕組みを意識することにより、集客コストや労力を抑えながら効率的に稼働を維持することが重要です。
継続受任につながりやすい取り組みとしては、次のような対策方法が挙げられます。
- 顧問化が狙える業務を扱う
- 定期受任を前提とした事務所運営を整備する
- 単発案件を次の相談につなげる導線をつくる
ここからは、それぞれの対策方法について詳しく解説します。
顧問化が狙える業務を扱う
継続受任につながりやすい取り組みとして、まず考えられるのが顧問化を狙える業務を扱うことです。
ここでの「顧問化」とは、単発ではなく継続的に業務を依頼してもらえる状態のことを指します。
たとえば、不動産業者の顧問として不動産登記を継続的に請け負ったり、成年後見人として生活のサポートをするなどの業務が挙げられます。
上記のような案件は、初期対応で顧客との信頼関係を築くことが受任につながるので、丁寧で誠実な対応を心がけましょう。
また、法人登記や契約書のチェックといった企業支援などの業務を定額制で提案するなど、顧問化のハードルを下げると受任につながりやすくなります。
定期受任を前提とした事務所運営を整備する
継続受任につながりやすい取り組みとして、定期受任を前提とした事務所運営を整備することも大切です。
たとえば、商業登記では年1回の役員変更登記や、相続関係では定期相談などのニーズが発生します。
こうした案件を取りこぼさず対応するためには、顧客情報や期限を管理する仕組みが必要です。
Excelや顧客管理ツールで、定期案内のハガキを郵送する期日を顧客ごとに管理するなどの方法もあります。
忘れずにリーチできる仕組みは、顧客の信頼を高めるだけでなく、効率的な営業にもつながるでしょう。
単発案件を次の相談につなげる動線をつくる
継続受任につながりやすい取り組みとして、単発案件を次の相談につなげる導線をつくることも忘れてはいけません。
案件を1件こなして終わりにするのではなく、完了後のフォローを通じて次の相談につながる関係性を顧客と築くことが大切です。
不動産登記が終わったタイミングで「相続対策として遺言書作成を検討されてはどうですか?」などの提案をしてみるのも良いでしょう。
ここで重要なのは、単なる営業としてではなく「今後も安心して相談できる専門家」として誠実に対応することです。
将来を見据えた提案が、次回の依頼につながる大きな一手になります。
対面営業なしでの案件獲得を仕組み化
リソースに制限がある独立司法書士にとって、非対面で集客する仕組みづくりをすることは、営業コストの削減や効率化などメリットが多いです。
対面営業なしで案件を獲得する方法としては、次のような方法が挙げられます。
- Webサイトで集客する
- Googleビジネスプロフィールで集客する
- SNSで集客する
- 士業マッチングサービスを活用する
以下、こうした方法を詳しく見てみましょう。
Webサイトで集客する
調べ事はWeb検索で行うのが普通になっている現代で、自身のWebサイトを持つことは効果的な集客方法と言えます。
専門とする業務内容や対応地域、過去の事例、相談の流れなどを明示することにより、顧客からの信頼度が高まるでしょう。
また、FAQやブログを通じて専門性や実績をアピールすることも効果的です。
しかし、競合他社も同様にWebサイトを運営していることが当たり前の時代。
ぜひ、検索エンジンで上位表示されやすいようにSEO対策をしっかりと行うなどの対策をしましょう。
Googleビジネスプロフィールで集客する
Googleビジネスプロフィールとは、Google検索やGoogleマップでビジネス情報を表示できる無料ツールです。
司法書士は地域密着型の特性があるので、案件獲得のための強力なツールとなるでしょう。
登録するだけで地図や営業時間、連絡先が表示されるため、Webサイトを持たない場合でも効果があります。
口コミ欄に実際の相談者の声が集まれば、信頼性が一層高まるでしょう。
ただし、Googleビジネスプロフィールを利用する場合も検索上位となるように、定期的に情報更新したり、写真や投稿を充実させるなどの対策が重要となります。
SNSで集客する
SNSは幅広い層への認知を高めるのに効果的です。
X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどを使って、専門分野の知識や相談対応の一場面を発信することで、潜在的なニーズを掘り起こすことが可能となります。
たとえば、「プロが教える相続の困ったを解決」など専門家としての立場を示しつつ、分かりやすく知識を発信すると、将来的に相続を控える子世代にリーチすることができるでしょう。
また、コメントやDMでの相談受付などもスムーズな集客の導線になります。
士業マッチングサービスを活用する
近年では、士業向けのマッチングサイトも増えており、そこに登録することで非対面でも案件獲得のチャンスを得られます。
利用者は「特定の分野に強い専門家を探している」ケースが多いため、得意分野や対応地域、料金体系などをわかりやすく記載することが成約率を上げるポイントです。
プロフィール欄を丁寧に作り込み、写真や自己紹介動画などで信頼性を高めると、問い合わせのハードルが下がります。
登録料金が発生するものや、案件が成立した場合に費用が発生するものなど様々なサービスがあるので、自分にあったサービスを利用するようにしましょう。
司法書士が安定的かつ効率的に案件を獲得するにはWeb活用が鍵!

今回は、安定して案件を獲得するための方法を3ステップで紹介しました。
司法書士として安定的に案件を獲得するには、自分に合った専門分野を見極め、適切な営業活動と効率的な案件獲得の仕組みづくりを行うことが重要です。
特にリソースの限られる独立司法書士にとっては、効率性の高いWebを活用した集客が鍵となります。
Webを活用することで、ターゲットとなる顧客へ24時間365日アプローチでき、営業効率と収益の安定化を同時に実現できます。
「Web集客に挑戦したいけれど独立したてで余裕がない」とお悩みであれば、まずはドットアンドノードにご相談ください。
ドットアンドノードでは、すでに成果の出ている司法書士さまのWeb集客ノウハウを、まるごと移植できる繁盛司法書士パックがあります。
Web集客のプロと一緒に、安定した案件獲得を目指しましょう。
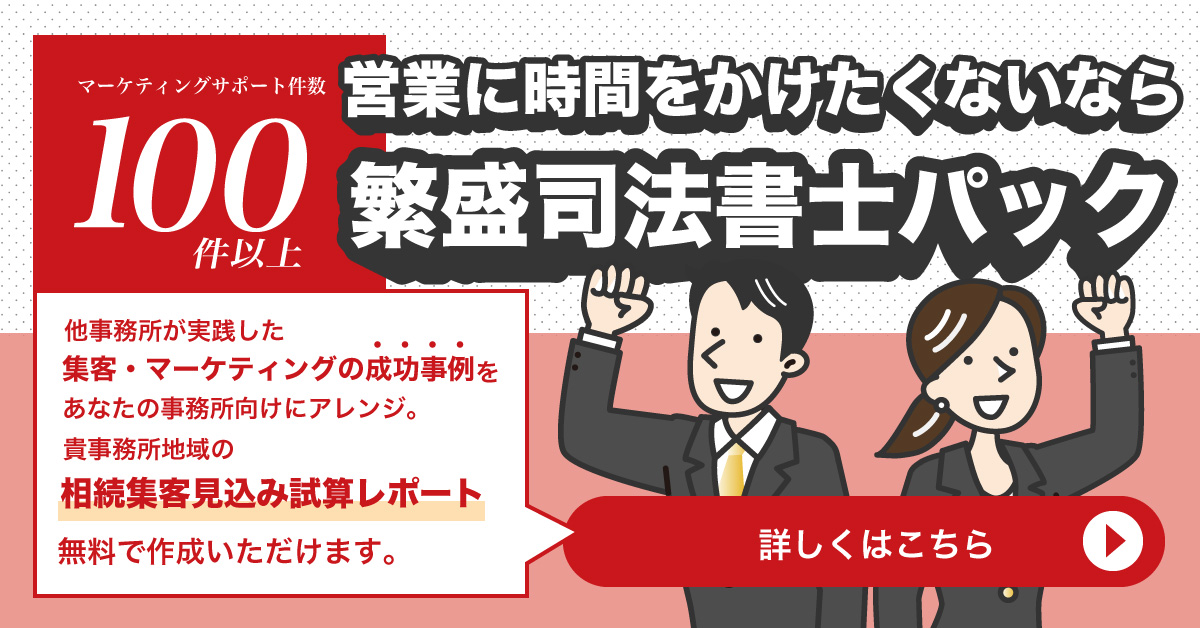
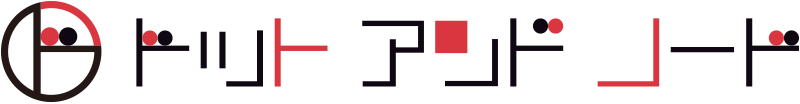

で集客するには?効果的な活用方法とWeb集客成功のポイントを解説-590x380.jpg)