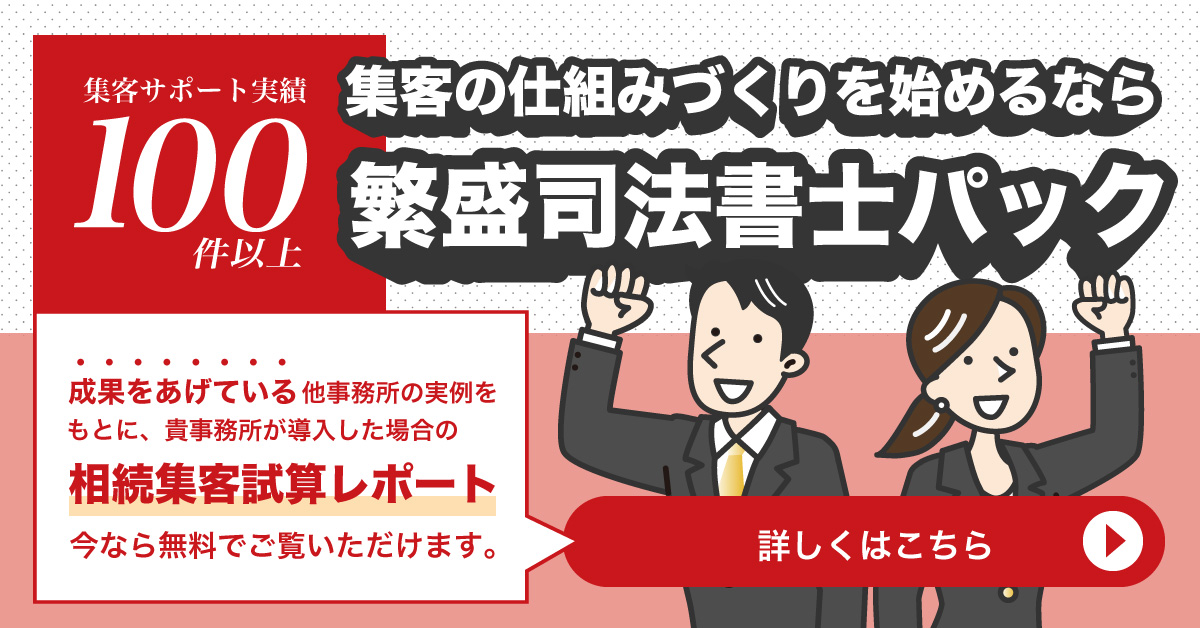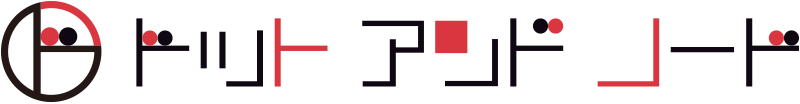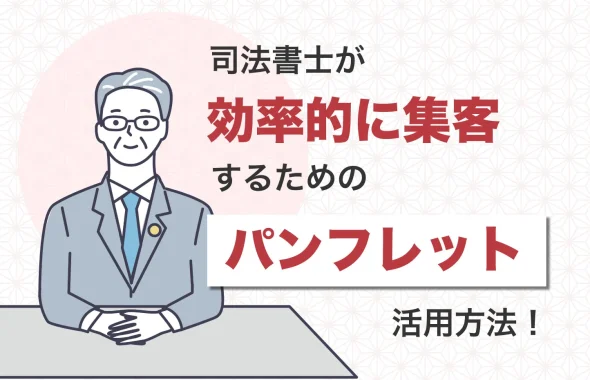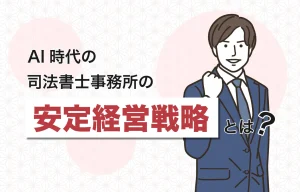司法書士でもDXを活用すべき!DXでの業務効率化から顧客満足向上まで徹底解説
司法書士事務所では、登記や契約書の作成、顧客対応など幅広い業務を限られた人員で行うことが多いものです。
日々の作業に追われて、新しい取り組みが後回しになりがちです。
しかし近年、こうした状況を変える手段として注目されているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
DXを取り入れることで、書類作成の効率化やミスの削減、顧客対応のスピードアップなど、事務所の生産性を高めることが可能になりました。
実際、司法書士業務のIT化・DX化は着実に進んでおり、乗り遅れると顧客離れにつながる可能性も。
紙ベースの作業は非効率で、情報漏えいや紛失のリスクも高いため、業務のデジタル化は今後必須とされているのです。
本記事では、司法書士がDXを活用して業務改善を実現するために押さえるべきポイントや導入ステップ、注意点をわかりやすく解説します。
司法書士がDXを導入するメリット

司法書士がDXを取り入れるメリットは、次のとおりです。
- 作業の効率化
- ヒューマンエラー削減
- 顧客の利便性向上
- コスト削減
- 利益率の向上
- スタッフの働きやすさ改善
- ペーパーレス化
以下からは、それぞれについて詳しく解説します。
作業の効率化
DXを導入すると、書類作成やデータ入力といった定型業務を効率よく進められます。
たとえばクラウドツールを使い、紙やExcelで行っていた事務作業をオンラインで処理、スタッフの負担を減らせるなど。
スタッフが入力フォームをあらかじめテンプレート化しておけば、必要な情報を素早く正確に記入できます。
自動入力機能を活用すれば、スタッフは繰り返しの入力作業を省けます。
さらにRPA(ソフトウェアロボット)を導入すれば、スタッフが手作業で行っていた処理を自動化でき、短時間で終えられるのです。
また生成AIを使えば、スタッフは契約書のひな形や登記書類の下書きを短時間で作成でき、効率よくドラフトを準備できます。
こうして日々の事務処理が速くなれば、スタッフは依頼者対応や経営改善といった付加価値の高い業務に集中可能。
削減した時間を顧客対応に充てることで、顧客満足度の向上にもつながります。
ヒューマンエラー削減
DX導入により、ミスの削減も期待できます。
自動チェック機能や電子申請システムを導入することで、書類の記載漏れや誤記入を未然に防ぐことが可能です。
実際、不動産登記のオンライン申請では、法務局への持参や郵送の手間を省くだけでなく、申請書様式に沿って入力するだけで手続きが完了するなど、ミスや抜け漏れの防止につながっています。
また、各種手続きをマニュアル化できるクラウドツールを使えば、提出書類の種類や手順を漏れなく管理できます。
たとえば不動産登記で必要な住民票や印鑑証明書の収集手順をテンプレート化しておけば、重要な書類の提出漏れを防げるのです。
このようにDXは、ヒューマンエラーによるやり直しやトラブルを減らし、業務の正確性と迅速性を同時に向上させます。
顧客の利便性向上
DXは顧客体験も向上させます。
Web予約システムを導入すれば、依頼者は来所せずにオンライン上で簡単に相談の予約を取ることができます。
自動送信される確認メールやリマインドにより、日程調整もスムーズです。
オンライン面談ツールを使えば遠方の顧客でも移動の負担なく相談でき、忙しい依頼者にとって大きな利便性となります。
顧客は便利さを実感し、安心して手続きを任せられる環境が整います。
実際に、オンライン相談やクラウド管理を組み合わせて「依頼者にとってアクセスしやすい司法書士事務所」になることは、選ばれる上で大切な理由。
私たちドットアンドノードでは、このようなオンラインでの円滑な顧客体験を活かした集客施策(SEOやWeb広告運用)も支援しており、新規顧客の獲得とリピート率向上の両立をお手伝いしています。
顧客との信頼関係の強化
DXは顧客との信頼関係を強化します。
たとえば進捗管理ツールを導入すれば、依頼者は「手続きがどこまで進んでいるか」をリアルタイムで確認できます。
案件のタスクや進行状況を可視化・共有することで、依頼者は「自分の案件が確実に進んでいる」という安心感を得られるもの。
透明性の高い対応は信頼感につながり、事務所への信頼を強めるのです。
適切な進捗管理ができれば、納期遅延やトラブルを防ぎ、企業の信頼性を高められるわけです。
情報共有が徹底された体制であれば、担当者が交代しても履歴を確認するだけで状況を把握でき、対応の連続性が確保されます。
こうしたDXによる情報共有や進捗の可視化は、顧客に「任せて安心」という印象を持ってもらいやすくもなるのです。
結果として、リピート利用や新たな紹介にも発展する要因となります。
コスト削減
DXの推進はコスト面でもメリットをもたらします。
ペーパーレス化やオンライン化によって、印刷代・郵送費・書類保管庫の賃料といった経費削減に直結します。
たとえば紙の定款を電子定款に切り替えることで、一件あたり4万円の収入印紙代を節約できる上、郵送や来所の手間も省きやすい状態に。
また、登記申請などをオンラインで行えば、紙で行うよりも手数料が割安になる手続きもあります。
作業時間の短縮による、人件費の効率化も見逃せません。
AIの進化により、これまで手作業だった書類作成が自動化しやすくなりました。
つまり、時間のかかる仕事を減らせるため、業務負担が軽減され人件費削減にもつながるのです。
さらに、電話対応を外部の電話代行に委託してチャットで伝言を共有する仕組みにすれば、広い事務所スペースや多数の受付人員を確保しなくても済み、家賃や人件費の経費削減ができます。
このように、DXは無駄なコストを省き、事務所運営の収支改善も実現するのです。
利益率の向上
DXの導入によって生まれたコスト削減効果や余剰時間は、顧客フォローや新サービス開発に充てることができます。
つまりDXは、単なる経費節減にとどまらず、浮いたリソースを成長のための投資に回せる点が利点なのです。
たとえば書類作成の時間短縮や問い合わせ対応の迅速化で生まれた余裕を使い、今まで対応が難しかった顧客への丁寧なフォローや、新たな相続コンサルティングサービスに挑戦することも可能となります。
顧客単価の上昇やリピート率の改善によって、利益率アップが期待できるのです。
さらに削減したコストをWeb集客に再投資すれば、新規顧客を安定的に獲得でき、売上増加にも直結します。
実際、DXによって削減した時間を依頼者対応や経営改善に振り向ければ、司法書士の存在感は以前にも増して高まると指摘されています。
効率化で生まれた時間をどの分野に再配分するかによって、DXは事務所の成長を支えるエンジンとなるのです。
私たちドットアンドノードでは、集客戦略の立案からSEO・広告運用まで一貫して支援し、効率的なリソース活用による利益率向上を後押しいたします。
スタッフの働きやすさ改善
DXは、事務所スタッフの働きやすさ向上にもつながります。
たとえばクラウド型の業務システムを導入すれば、自宅や外出先からでも案件処理が可能となり、在宅勤務やモバイルワークが現実的な選択肢となります。
子育て中のスタッフや時短勤務の職員も場所に縛られずに活躍でき、柔軟な働き方の実現へと結びつきます。
ある司法書士事務所では、スタッフの多くが子育て中。
常時オフィスにいるのは4名程度という体制です。
フレックス勤務や在宅勤務を組み合わせることで、スタッフが無理なく働ける環境を整えています。
結果として働きやすさが確保され、人材採用が難しい時代にあっても優秀な人材を確保しやすくなり、定着率の改善にもつながっています。
ペーパーレス化
DX化のわかりやすいメリットは、ペーパーレス化です。
ペーパーレス化によって紙の書類を探し回る手間がなくなり、煩雑なファイリング作業によるストレスも減ります。
紙書類をデジタル化すれば、山積みの資料から必要な書類を探す時間が削減され、スタッフは本来の専門業務に集中できるようになります。
働きやすさの改善はスタッフの定着率を高め、事務所の安定した運営につながるというわけです。
ペーパーレス化は、働きやすさを左右する要素です。
電子化された文書があれば、必要なときに即座に検索・閲覧でき、情報共有もスムーズになります。
紙の紛失リスクも解消され、情報管理の安全性が確保されるのです。
実際に、紙中心からデジタル中心へ移行した事務所では、業務効率が飛躍的に改善した事例もみられます。
司法書士に効果的なDXの方法

司法書士事務所がDXを進めるにあたっては、次のように導入効果の高い領域から着手することが成功のカギです。
- 書類業務・申請手続きの効率化
- 顧客対応・サービスのデジタル化
- 業務プロセスのデジタル化
- 経営管理・マーケティングのDX
以下からはそれぞれについて、具体的に解説します。
書類業務・申請手続きの効率化
まずは次のような司法書士の本業である書類作成・申請手続きの分野についてDX化をすべきです。
- 書類作成・管理のクラウド化
- AIによる契約書レビュー・文書作成支援
- 登記・供託オンライン申請の徹底活用
- 電子公証サービスの活用
以下からは、それぞれのDX化方法を詳しく紹介します。
書類作成・管理のクラウド化
登記申請書や契約書類をクラウド化すれば、業務効率が向上します。
クラウド上にひな形(テンプレート)を用意し、必要な項目を入力するだけで登記申請書のドラフトを作成できる仕組みを整えれば、毎回ゼロから書類を作成する負担を省けます。
作成した書類をクラウドストレージに保管しておけば、事務所内の誰でも必要なときにアクセス可能です。
場所や時間を問わず利用できる、こうしたクラウドの仕組みは、司法書士事務所においても導入が進んでいます。
たとえば社内文書を一括で管理できるドキュメント管理ツールを使えば、自宅からでも必要書類を閲覧・利用できます。
紙の書類が残っている場合はOCR(光学文字認識)ソフトを活用してデータ化するのがおすすめです。
OCRを導入すれば、書類や伝票をスキャンするだけで自動的にテキストデータ化され、文書作成にかかっていた時間を削減できます。
クラウド化の活用によって、書類作成や管理の手間とミスを減らし、いつでもどこでも安全に文書へアクセスできる環境が整うのです。
AIによる契約書レビュー・文書作成支援
近年では、生成AIや文書解析AIを契約書のレビューや文書作成支援に活用する取り組みが広がっています。
AIは、大量のテキスト処理や定型文の生成を得意とするため、司法書士業務の一部を効率化できるのです。
具体例として、契約書の誤字脱字の確認や法令・条文の参照漏れのチェックを自動で行う仕組みが挙げられます。
自然言語処理を応用し、契約書の内容を解析してリスクになり得る表現をハイライトし、修正案を提示するツールも登場しました。
登記申請書類の下書きをAIで作成し、人間が最終確認を行う使い方もおすすめです。
必要事項を入力すれば、不動産登記申請書や相続関係説明図、会社の定款などを自動作成できるアプリも登場しており、官公庁提出書類の作成も容易になっています。
日本語に対応した生成AIを用いれば、依頼者への説明文や議事録の案を瞬時に作成することも可能です。
AIが定型業務を担うことで、司法書士は依頼者への丁寧な説明や複雑案件の判断といった人間にしかできない業務へ時間を振り向けられます。
もっとも、AIの提案を無条件に受け入れるのではなく、最終判断と責任は司法書士自身が担う必要があります。
AIは有力な補助役である一方、誤った情報を出力する危険もあるため、必ず人間によるレビュー体制を確立することが重要です。
登記・供託オンライン申請の徹底活用
登記・供託手続きをインターネット経由で行える「登記・供託オンライン申請システム」を活用すれば、申請業務の効率と迅速性が高まります。
オンライン申請を利用すれば、登記所の窓口へ出向く必要がなく、自宅や事務所から手続き可能。
たとえば21時頃まで申請可能な場合もあるため、日中の忙しい時間を避けて作業するといった対応もできます。
一部の手続きは、紙申請よりオンライン申請の方が手数料等が低く設定されており、費用面でも有利です。
法人設立登記のオンライン申請では電子署名用の証明書が不要となり、手軽に申請できます。
法務局が閉庁した後でも申請データを送信でき、処理は一層スピーディーです。
システムを利用すると、申請書の作成から添付書類の送信まで一元管理でき、処理状況もオンライン上で確認可能です。
登記完了のお知らせも電子的に受け取れるため、郵送を待つ従来の方法に比べて処理が早まります。
オンライン申請に慣れていない場合でも、法務省が提供する「かんたん証明書請求」ブラウザ方式や専用ソフト経由の方法が用意されています。
このように登記・供託オンライン申請を積極的に活用すれば、時間短縮と正確性の両立が可能です。
電子公証サービスの活用
定款認証などの公証手続きも、電子公証サービスを活用して効率化できます。
従来、会社設立時の定款認証は公証役場で紙の定款に認証を受け、4万円の収入印紙を貼付する必要がありました。
しかし、電子定款を利用すれば、PDFで作成した定款に電子署名してオンラインで認証を受けることが可能です。
電子定款は課税文書に当たらないため、収入印紙代4万円が不要となり、郵送や来所の手間も省けます。
現在では全国すべての公証役場がテレビ会議による本人確認に対応し、オンラインで定款認証を完了できる体制が整っています。
つまり、会社設立時の定款認証手続きは原則オンラインで行える時代になっているのです。
電子公証のメリットは、定款に限りません。
将来的には、公正証書遺言の作成もオンライン化される予定で、2025年には公証人法改正により自宅から公正証書遺言を作れる仕組みが導入される見込みです。
このように電子公証サービスを積極活用することで、定款認証や公証人役場での各種手続きをデジタル完結させ、移動時間や印紙税といったコストを削減できます。
司法書士としても、電子証明書の取得や「登記・供託オンライン申請システム」での電子公証手続きを覚えておき、依頼者に迅速なサービスを提供できるようにしましょう。
顧客対応・サービスのデジタル化
依頼者への対応やサービス提供の場面でDXを進める方法として、次があります。
- 顧客対応のオンライン化
- 顧客ポータルサイトの導入
- AIチャットによる一次相談対応
- マイナンバーカード連携サービスの活用
- 相続・不動産シミュレーションツールの導入
それぞれの方法について、以下から詳しく見ていきましょう。
顧客対応のオンライン化
顧客とのコミュニケーションをオンライン化すれば、利便性と対応スピードが向上します。
具体例としては、Web予約システムを導入して面談予約をオンラインで受け付けることや、ZoomやTeamsなどのビデオ会議システムを活用して相談を行えるようにする取り組みです。
依頼者は事務所に足を運ばずに相談できるため、遠方に住む方や忙しい方でも利用しやすい環境となります。
オンライン相談はコロナ禍をきっかけに一般化し、高齢者でもスマホを使ってビデオ通話やチャットを利用する事例が増えました。
司法書士事務所でも、初回の信頼構築など対面が必要な場面を除き、オンライン対応へ切り替える流れが広がっています。
また、CRM(顧客関係管理)システムと連携した問い合わせフォームをホームページに設置し、自動返信メールで受付確認や必要書類の案内を送る仕組みもおすすめです。
問い合わせから初動対応までを自動化できるため、依頼者を待たせることがありません。
オンライン対応を充実させることは「アクセスのしやすさ」という点で事務所の強みとなり、依頼者が司法書士事務所を選ぶ理由になるのです。
ドットアンドノードでも、Web予約フォームの設置やオンライン面談環境の整備を支援しています。
加えて、事務所の強みを活かした広告やSEOによる集客まで一貫してサポートしています。
顧客ポータルサイトの導入
依頼者専用のポータルサイトを導入し、進捗確認や書類のやり取りをオンラインで完結させることは、DXの取り組みとしておすすめです。
ポータルサイトとは、依頼者がログインして案件の進捗を確認したり、必要書類をアップロードしたりできるウェブページ。
司法書士事務所向けの案件管理システムには、依頼者と進捗を共有できる機能を備えたものも登場しています。
こうした仕組みを整えれば、依頼者は自分の依頼がどの段階にあるかを一目で把握でき、次に取るべき行動もはっきりします。
たとえば「戸籍収集中」「登記申請中」「完了書類発送済み」といったステータスをリアルタイムで更新すれば、「今どうなっていますか」という問い合わせが減り、事務所の対応負担も軽くなるのです。
さらにポータル上で依頼者が直接書類をアップロードできるようにすれば、メール添付や郵送に比べて確実で安全です。
アップロード時に自動通知が送られる仕組みを整えておけば、書類受領漏れを防止できます。
通知機能も大切です。
進捗が更新されるたびにメールやアプリで依頼者へ知らせが届けば、頻繁にログインしなくても状況を把握できます。
透明性の高い情報共有は依頼者の安心感につながり、事務所への信頼性向上にも結びつきます。
担当者が交代しても履歴がポータルに残るため、引き継ぎも円滑に進むわけです。
顧客ポータルの導入は、顧客満足度と業務効率の双方に効果をもたらすDX施策です。
AIチャットによる一次相談対応
AIチャットボットを活用して、よくある問い合わせへの一次対応を自動化することもおすすめです。
司法書士事務所には相続手続きの必要書類や登記費用の概算、相談予約方法など、定型的な質問が多く寄せられがち。
多数の質問に対し、ホームページ上でAIチャットボットが24時間対応できれば、依頼者は疑問をすぐ解決でき、事務所側も営業時間外の対応負担が減ります。
たとえば「相続登記に必要な書類は?」「費用はいくらか?」といった質問に対して、あらかじめ用意した回答やFAQをAIが即座に返答。
最近はChatGPTのような高度な生成AIを組み込んだチャットボットも登場しており、ユーザーの質問のニュアンスを理解して適切な回答を生成してくれます。
また、チャットで対話しながら必要事項をヒアリングし、内容に応じて「まずは戸籍謄本をご用意ください」「〇〇のケースでは弊所でお手伝いできます。面談をご希望の場合はこちらからご予約を…」といった次のアクションを案内することも可能です。
依頼者は、来所前からある程度の状況整理ができ、初回面談をスムーズに始められます。
AIチャットボットの導入で、「電話が繋がらずに機会損失…」といったリスクも減少可能。
もちろん、専門的な判断が必要な内容は最終的に人間が対応する必要があります。
一次相談対応を自動化することで業務負荷を減らしつつ、依頼者には「すぐ答えがもらえる」という満足感を提供できるのです。
マイナンバーカード連携サービスの活用
依頼者の本人確認や電子署名にマイナンバーカードを活用すれば、来所や書類のやり取りを削減できます。
たとえば、不動産売買や相続手続きでは依頼者本人の確認が必須。
これまでは対面で身分証を提示してもらい、その写しを保管するといった手間がありました。
近年、オンラインで本人確認を完結できるeKYC(オンライン本人確認)サービスが登場し、司法書士向けにも提供されています。
具体的には、依頼者にスマホアプリを通じてマイナンバーカードを読み取ってもらい(カードのICチップ情報をNFC対応スマホでスキャン)、デジタル署名により本人確認を実施する仕組みです。
司法書士側はオンライン上で認証結果を受け取り、確認が完了したら通常の郵便で書類を送付できます。
従来は本人限定受取郵便などで対面に近い確認を行う必要があり、依頼者も郵便を受け取るため在宅していなければならない不便がありました。
しかしマイナンバーカードを用いたeKYCなら、不便さが解消されます。
また、マイナンバーカードの公的個人認証機能を使って電子署名を行えば、紙の書類への押印の代わりにオンラインで契約・同意を得ることも可能です。
たとえば相続関係説明図への相続人全員の同意をマイナンバーカードで電子署名してもらえば、全員が集まって実印証明をやり取りする手間を省けます。
今後、公証業務や銀行手続でもマイナンバーカード活用が進む見込みであり、来所や郵送を削減して手続きを完結できる場面が増えていくはずです。
司法書士事務所としてもこうしたサービスに対応し、依頼者の負担軽減と迅速な手続き完了を実現していきましょう。
相続・不動産シミュレーションツールの導入
相続や不動産に関する計算・シミュレーションを自動化するツールを活用することもおすすめです。
相続分の算定や相続税額の試算、不動産の名義変更に伴う登録免許税の計算などは、専門知識が必要な一方で、パターン化された計算作業。
こうしたツールで自動計算できれば、手計算より正確でスピーディーです。
たとえば、相続税のシミュレーションツールに家族構成と財産額を入力するだけで、相続税額の概算が即座に算出されます。
実際に税理士法人や銀行が提供する無料シミュレーションでは、遺産総額や相続人の数を入力すると税額の目安が示され、二次相続の場合の配分最適化効果なども確認できるなど利点はさまざま。
司法書士事務所でも、相続登記の相談時にこうしたツールを使って「もし〇〇万円の不動産を相続する場合、相続税はこのくらいです」と即答できれば、依頼者の安心感が違います。
不動産に関しても、たとえば贈与と相続どちらが有利かを試算するツールや、ローン返済シミュレーションなどを活用すれば、依頼者へのアドバイス精度が上がります。
なお、シミュレーション結果はあくまで概算で、条件によって変動する旨を伝えた上で活用するようにしましょう。
こうしたツール導入により、煩雑な計算業務に割く時間を減らしつつ、依頼者には分かりやすい根拠数字を提示できるため、サービス品質と効率の両面でメリットがあります。
業務プロセスのデジタル化
次のような、事務所内の業務プロセス全般にDXを適用し、働き方そのものを変革する取り組みです。
- リモートワーク体制の整備
- RPAによる定型業務の自動化
- 音声入力・文字起こしツールの導入
- API連携によるシステム統合
- チームコラボレーションツールの活用
- ナレッジ共有・所内教育のDX
以下からは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
リモートワーク体制の整備
DXの基盤として、いつでもどこでも働けるリモートワーク体制を整備しましょう。
電子署名サービスやクラウド電話、オンライン会議システムを導入することで、自宅や外出先からでもオフィスと同様に業務が行えます。
電子署名サービス(例:CloudSignやDocuSign)を使えば、紙の契約書や稟議書のために出社・対面する必要がなくなります。
クラウド電話システムを導入すれば、事務所の固定電話への着信をスマホやPCで受けて応対可能です。
また、チャットツールやビデオ会議を使えば、所内打合せや顧客面談もオンライン化できます。
こうした環境整備により、テレワークや在宅勤務にスムーズに移行できます。
人材不足の時代において、働きやすい勤務体制の整備は必須であり、事務所のデジタル化は避けて通れない経営課題です。
実際、とある司法書士事務所ではノートPCとクラウドシステムを全員に用意し、曜日ごとに在宅と出社をシフトするフレックス勤務を導入。
その結果、人材採用難の中でも育児中の優秀な人材を確保でき、事務所運営が安定したとのことです。
DX化によりリモートワーク体制が整備できれば、働き方改革と事務所の持続的成長を実現できるようになるのです。
RPAによる定型業務の自動化
RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上の定型作業をソフトウェアロボットで自動化する技術です。
司法書士事務所でも、決まりきった事務処理はRPAに任せることで時間短縮が可能です。
たとえば、法務局の登記事項証明書を大量に取得する作業では、RPAが申請用総合ソフトを操作してリスト上の複数物件の証明書請求を自動で繰り返し行えます。
また、案件ごとの期限管理(登記申請期限や書類提出期限のチェック)をRPAにさせ、期限が近づいた案件には自動でメール通知を送る、といった運用も考えられます。
進捗連絡も、自動化していきましょう。
依頼者への「登記申請が完了しました」などの連絡メールを、登記情報取得と連動して自動送信するようにすれば、事務方の手間が省けます。
さらに、Excel台帳へのデータ転記や、会計ソフトへの仕訳入力など、ルールが決まっている繰り返し作業もRPAの得意分野です。
一度フローを教え込めば、深夜でも土日でもミスなく動いてくれます。
たとえば行政書士業界では、数百件に及ぶ役所提出書類のステータスチェックをRPAで自動化し、年間何百時間もの省力化を実現しています。
司法書士事務所でも、業務手順が定まっているルーティンがあれば積極的にRPA化を検討しましょう。
ただし、RPAは動作環境の変更に弱いため、導入後のメンテナンスも見据えて計画することが大切です。
音声入力・文字起こしツールの導入
音声認識技術を活用して、業務の効率化を図る方法です。
具体的には、dictation(音声入力)や自動文字起こしツールを導入し、文章作成や会議録の作成を効率化します。
たとえば、依頼者との面談内容を録音しておき、後でAI文字起こしサービスにかけるといったやり方。
発言内容が自動でテキスト化されます。
つまり、面談記録や議事録を作成する時間が短縮されるのです。
最近の音声認識技術(Google音声入力やAmiVoiceなど)は日本語でも精度が高く、専門用語が多い法律相談でもかなり正確にテキスト化できます。
また、司法書士が書類を作成する際も、キーボード入力ではなく「マイクに向かって喋ることでテキスト化する音声入力」を使えば、タイピング速度より速く文章を作成できる場合があります。
特に、長文の報告書や議事録などは、口述の方が思考の流れで一気に書けるといった利点も。
さらに、電話問い合わせの対応中に要点をメモする代わりに通話録音+AI文字起こしを併用すれば、聞き漏らしを防ぎつつ後から内容確認も簡単にできます。
音声入力・文字起こしツールの活用により、「書く」作業を「話す」作業に置き換えることで、疲労感も軽減しながら生産性を向上させることができます。
導入の際は音声データのセキュリティに留意し、信頼できるサービスを選ぶようにしましょう。
API連携によるシステム統合
複数の業務システム間でデータを連携し、シームレスに情報共有することもDX化の一環です。
司法書士事務所では、案件管理システム・会計ソフト・顧客管理(CRM)・登記オンライン申請システムなど、さまざまなソフトウェアを使うことがあります。
こうしたソフトがバラバラに動いていると、同じデータを何度も入力したり、手作業でデータ移行したりといった非効率が起こりがち。
そこで、API(アプリケーション間の通信インターフェース)連携を活用してシステム統合を図りましょう。
具体的には、案件管理システムのデータを会計ソフトに自動連携して売上計上を自動化したり、顧客管理システムの情報を登記オンライン申請システムに送って申請書を自動生成したりするイメージです。
法務省の登記・供託オンライン申請システムでも、民間事業者が開発したソフトからAPIを使って申請データを連携する仕組みが進められています。
実際、司法書士向け業務ソフト「司法くん」などでは、案件情報からオンライン申請データを自動作成する機能が提供されています。
また、会計ソフト「freee」や「弥生会計」と銀行口座の連携で自動入出金仕訳を行うなど、他分野のツール連携も目立つようになりました。
システム統合により、二重入力のミスや漏れを防ぎ、リアルタイムにデータが同期されることで経営状況の把握もしやすくなります。
DX導入時には、API連携の対応状況も意識してツール選定しましょう。
チームコラボレーションツールの活用
事務所内のコミュニケーションを円滑にするために、SlackやMicrosoftTeamsといったコラボレーションツールを導入する方法です。
メールや電話に代わる現代的な業務連絡手段として、多くの企業で導入が進んでいます。
司法書士事務所でも、司法書士と補助スタッフとの間で日々多くのやり取りがあるもの。
しかし、メールでは埋もれやすく、LINEではプライベート利用との切り分けやセキュリティ面で課題が残りがち。
コラボレーションツールを使えば、案件ごと・依頼人ごとにチャンネル(スレッド)を分けてメッセージをやり取りできるため、話題が混在せず目的の情報をすぐ見つけられます。
また、ファイル共有も簡単。
登記申請書のドラフトや決裁書類のPDFなどをチャットに添付して関係者に共有できます。
既読未読も一目でわかり、誰が対応中かもステータス表示で把握できるため、「メールを送ったが見てもらえているか不明」といった不安も軽減します。
さらに、SlackやTeamsにはビデオ会議機能やタスク管理の連携機能もあります。
小規模事務所であれば、十分プロジェクト管理まで可能です。
進捗管理や情報共有がチーム全体で徹底されれば、業務効率化だけでなく属人化の防止にもつながります。
誰か一人に業務や情報が偏ることなく、互いに状況を把握しフォローし合える文化ができれば、事務所全体の生産性とサービス品質が向上します。
このようにコラボレーションツールは単なるチャット以上の効果をもたらすため、ぜひ活用を検討してください。
ナレッジ共有・所内教育のDX
DXを活用して事務所内のナレッジ(知識)共有やスタッフ教育を充実させる方法があります。
具体的には、クラウド上に事例データベースや業務マニュアルを蓄積し、AI検索によって必要な情報に素早くアクセスできる仕組みを整えるなど。
たとえば過去の事例や文書ひな形、業務Q&Aをまとめた社内Wikiをクラウド上に構築しておけば便利です。
新人スタッフが疑問を抱いた際には、キーワード検索を行うだけで先輩が残した回答や事例にたどり着き、自己解決が可能となります。
最近では社内ナレッジに特化したAI検索ツールも登場しています。
大量の社内文書を読み込ませておき、「〇〇の場合の手続き手順は?」と質問すると、該当箇所を抜き出して回答する仕組みです。
こうしたツールを導入すれば、膨大なマニュアルから必要な部分を探す手間が省け、ベテランの知見を新人がすぐ活用できるようになります。
さらに所内研修をオンライン化することもおすすめです。
動画会議システムを使って定期勉強会を開いたり、eラーニング教材を導入していつでも学べる環境を整備したりできます。
DXによるナレッジ共有は、属人化しやすい専門知識を組織全体の共有財産へと変えます。
スタッフ全員が一定水準のサービスを提供できる体制となり、事務所全体のレベル向上につながるのです。
また「誰かが休んでも他の人が対応できる」状態が実現し、業務継続性(BCP)の面でも有益です。
教育のDX化とナレッジ共有の推進は、長期的な人材育成とサービス品質の維持に欠かせない取り組みです。
経営管理・マーケティングのDX
DXは内部業務だけでなく、次のように経営管理やマーケティングの領域にも効果を発揮します。
- データ分析による業務改善
- 電子決済・オンライン請求システムの導入
- 電子契約プラットフォームの活用
- 集客の仕組み構築
- インサイドセールスの仕組み構築
それぞれについて、DXを活用するポイントを解説します。
データ分析による業務改善
事務所内の業務データや顧客データを分析すれば、的確な業務改善策を導き出せます。
たとえば案件種別ごとの処理時間や利益率、顧客の属性(年齢層や地域など)と受注率の関係をデータで可視化する、など。
分析の結果、「相続案件に時間がかかりすぎている」「不動産登記は利益率が低いため効率化が必要」といった課題が浮かび上がります。
各スタッフの業務量を数値で把握し、偏りを是正する施策に役立てることも可能です。
実際、ある司法書士法人ではDX化によって業務量の偏りが見える化され、負担が集中したスタッフを皆で支援する文化が生まれました。
できる人と苦手な人の課題をチームで共有し、改善策を試行することで、互いにフォローし合う体制が自然に醸成された事例です。
データに基づく分析ができれば、感覚では把握しきれなかった問題点を明らかにし、客観的な改善の話し合いも可能に。
売上や費用の推移、広告施策ごとの問い合わせ件数を定期的に追跡すれば、経営判断が検証できるようになるのです。
たとえば「SNS経由の問い合わせが少ないためリソース配分を見直す」「相続登記義務化の影響で相続案件が増加したので体制を強化する」といったデータドリブンな(数字に裏づけられた)意思決定が行えるようになります。
DXを通じてデータ分析の文化を根付かせ、PDCAサイクルを継続的に回すことが業務改善につながります。
電子決済・オンライン請求システムの導入
報酬の請求から入金確認までをオンラインで完結できる電子決済システムを導入すれば、経理業務の効率化と顧客利便性の向上が図れます。
具体的には、クラウド請求書サービスや決済代行サービスを利用して、請求書の発行・送付、オンライン入金を可能にするなど。
たとえば、依頼者にメールで請求書を送信し、リンク先でクレジットカード決済や銀行振込(ペイジー、ネットバンキング)を選べるようにすると、依頼者は紙の請求書や現金書留を扱う手間が省けます。
入金通知もシステムから自動受信でき、誰がいつ支払ったか一目瞭然です。
さらに、決済システムと会計ソフトを連携すれば、入金情報が自動仕訳されるため経理処理も簡素化されます。
印紙代が不要な電子請求書でコスト削減にもなりますし、未収金の督促もシステム上で自動リマインドメールを送るなど対応可能です。
顧客にとっても、オンライン決済は24時間いつでも支払いができ、領収証も電子発行されるため嬉しいものです。
近年は司法書士事務所でもSquareやStripeなどの決済サービスを導入し、相続登記や契約書作成代行の費用をクレジット決済で受け付ける例も増えています。
オンライン請求・決済システムの導入は、事務所のキャッシュフローを安定させ、経理の手間を削減し、依頼者にも喜ばれるWin-WinのDX施策です。
電子契約プラットフォームの活用
契約書や委任状の取り交わしに電子契約プラットフォームを活用することで、契約手続きのペーパーレス化と印紙税コストの削減が可能です。
司法書士業務では依頼者との間で各種契約書や委任状を取り交わす場面があります。
しかし、こうした「紙」でやり取りすると、郵送の手間や収入印紙代がかかります。
電子契約サービス(例:クラウドサイン、GMOサインなど)を利用すれば、オンライン上で契約締結が完了し、印紙税も不要です。
たとえば相続手続きの委任契約書を電子契約にすれば、依頼者はスマホやPCで内容を確認・電子署名するだけで契約締結できます。
紙の契約書のように収入印紙を貼る必要がないため、一件あたり数百円~数千円のコスト削減も可能。
また、契約締結までのスピードも飛躍的に上がります。
郵送なら往復で1週間以上かかるやり取りが、電子契約なら最短数時間で完了することもあります。
副次的なメリットとして、契約書の保管もクラウド上でできることが挙げられます。
クラウド上なら、過去の契約書を探すのもワンクリックです。
紙のファイルを棚から引っ張り出す必要はありません。
電子契約は今や大企業のみならず士業事務所でも広がっており、特にコロナ禍以降で導入が加速しました。
法律上も、電子署名法により紙と同等の法的効力が認められているため安心です。
司法書士事務所でも積極的に電子契約を活用し、契約関連業務の効率化とコスト削減を実現しましょう。
集客の仕組み構築
DXは集客・マーケティング分野でも威力を発揮します。
司法書士が本業に100%注力できるように、Webから自動的に集客する仕組みを構築することが理想です。
そのためには、ホームページやGoogleビジネスプロフィール(MEO対策)、Web広告、SEO、SNSといったオンライン集客チャネルを整備・最適化したいところ。
具体例としては、地域名+業務内容で検索された際にホームページが上位表示されるようSEOを強化するなど。
ほかにも、相続登記や会社設立支援に関する有益なコラムを定期発信してアクセスを集める方法があります。
また、GoogleやFacebookの広告を利用して「相続相談受付中」「司法書士オンライン相談できます」といった広告をターゲット層に配信し、興味を持ったユーザーをホームページの問い合わせフォームに誘導する施策も効果的です。
SNS運用も活用しましょう。
TwitterやFacebookで「事務所の日常」や「業務豆知識」を発信しファンを増やせば、何かあったとき真っ先に相談してもらえる関係づくりに役立ちます。
こうした集客チャネルの構築・運用は専門知識と手間が必要なため、外注化やツール活用も検討しましょう。
たとえばSEO記事の作成を専門業者に任せたり、SNS投稿文をAIで自動生成して負担を減らすといった工夫です。
ドットアンドノードでは、司法書士の先生方が本業に専念できるようにWeb集客の仕組み構築を支援する「繁盛司法書士パック」を提供しています。
実際に当社サービスを導入した事例では、「集客にムラがあった状態から毎月安定して問い合わせが来るようになり助かっている」との声もいただいています。
DXを活用して集客が仕組み化できれば、紹介だけに頼らない安定経営ができるのです。
インサイドセールスの仕組み構築
インサイドセールスとは、問い合わせや見込み客に対し、事務所内もしくは委託先で継続的にフォローを行い成約につなげる営業手法です。
司法書士事務所でも、相談フォームからの問い合わせや資料請求者に対し、適切にフォローアップすることで受任率を高められます。
インサイドセールスの仕組み化として、問い合わせ後の自動メール配信や、一定期間返答がない見込み客へのフォローメール送信、さらには電話(テレアポ)の外注化などが考えられます。
たとえば、問い合わせフォームから相談希望が来たら即座にお礼メールと面談日時調整リンクを送るなど。
さらに、その後も当日の案内やフォローアップメールを自動で送る仕組みを用意するといった方法も考えられます。
また、一定期間連絡が途絶えた見込み客リストに対して、外部の電話代行会社がフォローコールをするケースもあります。
電話代行サービスを利用すると、事務所スタッフが常時電話に追われることなく必要な電話だけ折り返せるようになることが強みに。
業務効率が格段に上がります。
ある事例では、電話代行会社を導入して1週間運用したところ、電話対応での顧客クレームは一切なく、むしろ伝言内容が全て可視化され、問い合わせ内容の傾向や時間帯が分析できるようになったといいます。
さらに、電話代行を使うことで休日の電話にも対応でき、取りこぼしの機会損失を防げるというメリットも。
このように、フォームからのアプローチやテレアポ等の営業プロセスを自動化・外注化することで、司法書士は本来の専門業務に集中しつつ案件獲得を最大化できます。
当社ドットアンドノードでも、フォーム経由のアプローチ設計や営業電話の仕組みづくりなど、司法書士事務所の営業支援を行っています。
DXを駆使したインサイドセールス体制の構築によって、安定した案件獲得と売上向上を実現しましょう。
司法書士が失敗せずにDX化を成功させるには?

DXの効果を最大限に得るためには、闇雲に最新ツールを導入するのではなく、次のような事前準備と段階的な導入が重要です。
- STEP1:現状分析
- STEP2:課題の洗い出し
- STEP3:小さなところからDXを始める
- STEP4:段階的にDX対象を拡大する
以下からは、DX成功のための理想的かつ現実的な4つのステップを順に解説します。
STEP1:現状分析
DXを始める前に、まず事務所全体の業務プロセスを見直すことが重要です。
現在行っている書類作成、登記申請、顧客対応、経理処理など各工程について、どこに時間がかかっているのか、どの作業でミスが多いのかを洗い出しましょう。
現状の問題点を正確に把握することで、DX導入によって何を改善すべきかが明確になります。
たとえば、「紙のファイル検索に毎日1時間費やしている」「電話対応で業務が中断され効率が悪い」「月末の請求処理で残業が発生している」など具体的な課題をリストアップ。
その際、スタッフの声も積極的にヒアリングしましょう。
現場の不満点や「本当はこうしたい」という要望を知ることが、DXの方向性を定めるヒントになります。
加えて、既存システムの問題点も整理しましょう。
どのツールが使いにくいか、連携が取れていないかなどを確認してみてください。
士業のDX成功のポイントとして、「従来の方法でどこが問題か、より効率よくするには何を導入すべきかをしっかり分析すること」がよく挙げられます。
まさに、「現状分析」がDX成功の道筋に当たります。
現状分析を疎かにせず、時間をかけて行うことで、後のステップで無駄のないDX投資ができるのです。
STEP2:課題の洗い出し
現状を整理したうえで、次に業務上の課題を洗い出します。
STEP1で明らかになった問題点に対し、解決するにはどんな手段があるか考えましょう。
そして、洗い出した課題に優先順位を付けることが大切です。
「まずどこから改善するのか」をはっきりさせ、DX導入の焦点を定めます。
たとえば、複数見つかった課題が「紙資料検索の非効率」「電話対応の負担」「スケジュール調整の手間」だったとします。
最も業務に支障をきたしているのが電話対応なら、まずは電話対応改革に着手すると決めるわけです。
そして、改善効果の大きさと実現難易度を軸に優先度を判断してみましょう。
難易度が低く効果が高いもの(いわゆる「ロー・ハンギング・フルーツ」)から着手するのが成功しやすいパターンです。
また、課題と解決策を整理することで、DX導入計画が社員全員で共有しやすくなります。
「我が事務所では○○が問題なので△△を導入する」という共通認識が持てれば、DXへの協力体制も得やすくなるもの。
士業のDX推進ポイントとして、「既存のシステム(現状)の刷新」がまず必要だといわれます。
つまり既存手法の問題点を明らかにし、改善策を練ることがDX成功のスタートラインなのです。
STEP2で改善の方向性と優先度を全員で共有し、次のステップに備えましょう。
STEP3:小さなところからDXを始める
DXは一度に全体を変革するのではなく、小さな領域から導入するのが効果的です。
大掛かりなシステムを一気に入れ替えると現場が対応しきれず失敗しがちなため、まずは部分的なDXで成功体験を積むことが大切です。
たとえば、最初の改善テーマに挙がった「電話対応の負担軽減」から着手すると決めた場合、電話代行サービスの試験導入を1ヶ月だけ行ってみる、といった具合。
実際、多くの士業事務所では毎日行っている電話対応の効率化からDXに取り組むケースが多いとされています。
電話を専門業者に委託しチャットで伝言を受け取る仕組みを試した事務所では、たった1週間で顧客からの苦情もなくスムーズに運用できた例があります。
このように、まずは影響範囲の小さいところでDX施策を試し、成果を数値で測定しましょう。
問い合わせ件数がどう変化したか、スタッフの残業時間が減ったかなど、できるだけ定量的に効果検証してみてください。
小規模なPoC(概念実証)から始めることは、DX導入の最初の一歩としておすすめです。
当社ドットアンドノードでも、司法書士とは事業自体が異なるものの、社内で積極的にDXを導入する際は、小さなテストから開始し、成果を分析した上で段階的に拡大するようにしています。
たとえばWeb集客施策でも、いきなり大予算を投下するのではなく、まずは少額の広告出稿で反応を見てチューニングし、成果が出たら本格展開するという手法です。
このようにリスクを抑えながら着実に効果を確認していくことで、DX施策の社内受け入れもスムーズになります。
STEP4:段階的にDX対象を拡大する
小さく始めて得られた成功体験を基に、DXの対象領域を徐々に広げていきます。
STEP3で「電話対応DX」が上手くいったなら、次は「文書管理DX」や「RPA導入」に着手するといった具合に、段階的に拡大していきましょう。
一度に全領域を変えようとするとコストも負担も大きくなりがち。
しかしながら、順次拡大なら現場が混乱せずに済みます。
たとえば、電話対応に続いて予約受付のオンライン化に挑戦。
予約オンライン化も成功したら次は契約書の電子化へ…というようにロードマップを描きます。
段階的な拡大には、コストを平準化できる利点もあります。
最初からフルスペックのDXシステムを導入すると初期投資が莫大です。
しかし、小規模ツールから始めて徐々に投資することで、費用対効果を確認しながら進められるのです。
また、現場スタッフのスキル習熟も段階的についていきます。
最初のDXでITツールへの抵抗感が薄れれば、次のDXにも前向きに取り組んでもらいやすくなります。
「まずは無料または低コストのツールでリスクの少ない領域から試し、徐々に活用範囲を広げる」という導入ステップが現実的。
まさにこのSTEP4に相当します。
段階的に取り入れていけば、DXは無理なく事務所全体に広がり、気付いたときには業務のあらゆる場面でデジタル化のメリットを得られるようになります。
司法書士がDX化において注意しておくべきポイント
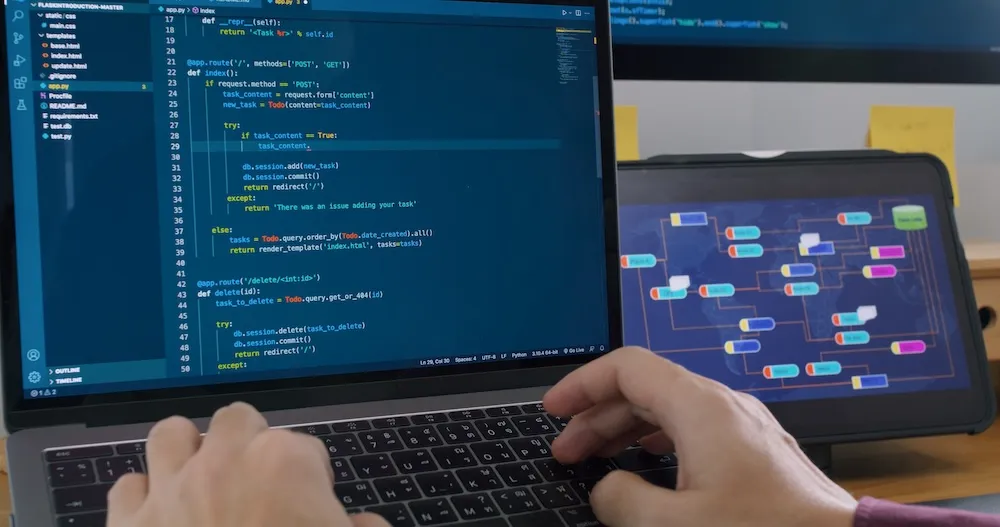
司法書士事務所でDXを進める際には、単に便利なツールを導入するだけでは不十分です。
次のように、事前に押さえておくべき注意点があります。
- セキュリティ対策
- 法改正や制度変更への対応
- DX施策の定着サポート
ここからは、DX推進時に気をつけたいポイントについて、詳しく解説します。
セキュリティ対策
司法書士業務では依頼者の個人情報や機密情報を多く扱うため、DXを進める上でも情報漏えいを防ぐ体制づくりが必須です。
まず、スタッフ全員に対して情報セキュリティ研修を行い、日常業務の中で「情報を守る意識」を浸透させましょう。
どんなに便利なクラウドサービスも、使い方次第でリスクになり得ます。
特にクラウド上にデータを預ける際は、サービスのセキュリティ機能を確認することが重要です。
通信の暗号化(SSL/TLS)やアクセス権限の細かな設定、二要素認証ログインなどの機能が備わっているサービスを選びましょう。
無料の汎用クラウドストレージなどは便利ですが、機密性の高い書類を預けるなら法人向けの堅牢なサービスを利用すべきです。
また、生成AIツールを使う場合も注意が必要です。
たとえばChatGPTなど外部のAIサービスに依頼者情報をそのまま入力するのは避けなければなりません。
実際、「機密情報を安易に外部サービスへ入力しないこと、セキュリティが確保されたAIツールを選ぶこと」が重要だと専門家も指摘しています。
DX導入時はこうしたポリシーを明文化し、スタッフに徹底しましょう。
さらに、万一に備え定期的なデータバックアップも欠かせません。
クラウドに上げたから安心ではなく、バックアップ先も分散させることでリスクヘッジします。
DXは利便性と表裏一体でセキュリティリスクを伴うため、「まず情報を守る仕組みを確立すること」が出発点といえます。
法改正や制度変更への対応
司法書士業務は、法改正や制度変更の影響を大きく受けます。
DXを活用すれば、改正情報の自動収集やチェックリストのオンライン更新、eラーニングによる研修などで対応負担を軽減できます。
しかし、最終的には司法書士自身が最新情報をキャッチアップし続けることが必要です。
たとえば、相続登記の義務化(2024年施行)のような大きな法改正があれば、改正に対応する業務フローを早急に整備しなければなりません。
DXツールとしては、官公庁や日司連からの通知を自動収集して社内掲示板に掲載する仕組みや、新しい法律の条文をAIで平易に解説させるサービスなどが考えられます。
実際、DXを活用すれば改正の概要を素早く共有したり、オンライン研修で全スタッフに周知徹底したりできます。
しかし、法律の解釈や適用判断はAI任せにはできません。
AIは条文データから概要を教えてくれますが、「このケースでどう適用されるか」といった判断には専門家の目が必要です。
したがって、DXはあくまで情報収集補助と考え、「最終的には司法書士自身が自主的に学び続ける」という姿勢が不可欠です。
DXで効率化し浮いた時間を、新制度の勉強や研修参加に充てることが理想的な活用法。
法改正への対応は事務所の信用にも直結します。
DXを賢く使って最新情報に常にアンテナを張りつつ、専門家としての知識研鑽を怠らないことが肝要です。
DX施策の定着サポート
DXは導入して終わりではなく、現場に定着させて初めて効果を発揮します。
そのためには、導入後のフォロー体制をしっかり構築することが大切です。
具体的には、DX施策ごとに運用責任者(社内のIT担当など)を置き、定期的に「使い勝手はどうか」「問題点はないか」をヒアリング・改善する仕組みを作りましょう。
スタッフからのフィードバックを反映しながらアップデートを重ねることで、システムがあるという事実に満足するだけでなく、長く活用できるようになります。
新しいツールの導入には、不安を抱くスタッフも少なくありません。
したがって、まずは簡単な操作から任せ、成功体験を積んでもらうことが大切です。
たとえば電子署名ツールなら、最初は内部稟議書の承認で試してもらい、慣れたら顧客契約に使う、と段階を踏むと抵抗感が薄れます。
また、操作マニュアルの整備や社内勉強会の開催もおすすめです。
人によってITスキルには差があるため、つまずくポイントを丁寧にサポートしましょう。
ある司法書士法人の事例では、新システム(キントーン)導入後2年間は思うように運用が定着せず、「やらされ感」が強かったそうです。
しかし、その間もスタッフに繰り返し指導し、自分たちのためになるものだと理解してもらう努力を惜しまず続けた結果、皆がシステムを受け入れ活用するようになったといいます。
このことからも、教育とフォローアップがDX定着の重要な鍵だと分かります。
DX施策を導入したら、必ず「人」に焦点を当てたサポート計画もセットで用意しましょう。
そうすれば、新しい技術が事務所に根付き、長期にわたって成果を上げ続ける土壌が育まれるはずです。
司法書士のDX成功事例

実際にDXや集客の仕組み化によって成果を上げた、次の司法書士事務所の事例をご紹介します。
- 集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍になった事例
- ホームページからの成約が増え集客が安定した事例
- 着手できていなかった集客の仕組み化が実行できた事例
各事例について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍になった事例
杠グループ様(相続専門の司法書士法人)では、Web集客の仕組み化により問い合わせ件数が1.5倍に増加しました。
元々紹介や口コミに頼っていたとのことで、新たにホームページとWeb広告を活用した「集客パッケージ」を導入した結果、オンラインから安定的に相談依頼が入るようになりました。
導入前と比べて問い合わせ数は150%にアップし、特に相続登記や家族信託に関する新規相談が顕著に増えています。
担当の岡田司法書士は「Web上に仕組みを作れば、休眠客にも自動でアプローチでき、継続的に問い合わせが来る体制が構築できた」と話しています。
この事例は、DXによるマーケティング強化が受任件数の底上げにつながった好例といえます。
ドットアンドノード株式会社導入事例「Web集客の仕組み化で問い合わせ件数が1.5倍に」
ホームページからの成約が増え集客が安定した事例
荒俣政吉司法書士行政書士事務所様では、ホームページ集客の強化により集客が安定し、成約件数が増加しました。
同事務所の荒俣先生は独立当初からHP経由での集客に取り組んでいましたが、旧ホームページでは月に問い合わせが1件あるかないかという状況でした。
そこで当社の「繁盛司法書士パック」を導入し、ホームページを全面刷新するとともにGoogle広告を運用したところ、現在では仕事の半分以上がホームページ経由で来るまでに発展。
問い合わせから成約に至る率も約80%と高く、問い合わせさえ来ればほとんど受任につながる状況です。
具体的には、導入後は毎月3件以上の成約がコンスタントに生まれており、多い月には5〜6件の問い合わせが来るようになったとのことです。
荒俣先生は「HPのおかげで安定的に集客でき助かっています。稲垣さん(当社担当)にお任せで、こちらは時々内容チェックするくらいで良い」とおっしゃっています。
ドットアンドノード株式会社導入事例「案件の半分以上がホームページから成約するようになりました」
着手できていなかった集客の仕組み化が実行できた事例
静岡鉄道相続サポートセンター様では、以前から「相続事業を軌道に乗せたい」という構想はあったものの、具体的な集客の仕組み化には手が回っていませんでした。
そこで当社の支援により、新規事業立ち上げ時からWeb集客パッケージを導入。
専門サイトの構築とリスティング広告運用、問い合わせフォーム最適化まで一貫してサポートしました。
すると、毎月4〜5件の問い合わせがコンスタントに入り、商談が1〜2件発生するようになりました。
商談化したお客様からはほぼ100%契約をいただいているとのことで、「集客~受任まで」の流れが確立できています。
実際、同センターでは新規事業開始から5年連続で黒字を達成し、広告費を増額した後には単発で3億円の売上を生む大型案件も獲得できました。
担当の笠原部長は「事業構想段階で稲垣さんに具体的なスキームを提示してもらい、『これはやるべきだ!』と感じた。おかげさまで順調に立ち上がり、広告から毎月安定的に契約を獲得できている」と語っています。
ドットアンドノード株式会社導入事例「安定的に業績が伸びるスキームができました」
DXを司法書士事務所の成長戦略として実践しよう!

DXは司法書士事務所の生産性向上や顧客満足度向上をもたらすだけでなく、将来の安定経営を支える基盤にもなります。
重要なのは、いたずらに最新技術を導入することではなく、自事務所の課題を整理すること。
そして、まずは小さく始め、段階的に拡大していくという戦略的な姿勢です。
むやみにツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。
むしろ「成果が実感しやすい身近な業務から導入し、生産性向上を実感したら他の業務へ広げる」というステップを踏むことが成功のカギです。
そして、DX推進にあたってはセキュリティ対策や個人情報保護への配慮を怠らず、スタッフのITスキル格差にも目を配り、丁寧に教育・フォローすることが不可欠です。
そうすれば、新しい仕組みも現場に定着し、長く活用できます。
DXは一過性の流行ではなく、長期的な事務所成長を支える戦略として位置づけましょう。
ITツールは司法書士の仕事を奪う脅威ではなく、むしろ専門性を最大化する強力なパートナーです。
ぜひDXを前向きに捉え、自事務所ならではの活用方法を模索してみてください。
もし「何から始めればいいか分からない」「社内にITに強い人材がいないので不安」という場合は、中小企業の成長支援に強みを持つドットアンドノード株式会社までぜひご相談ください。
弊社では司法書士事務所向けにDX導入やWeb集客施策をトータルで支援する「繁盛司法書士パック」をご用意しております。
ヒアリングのうえ最適なプランをご提案できるため、DXの力で事務所経営を次のステージへ押し上げていきましょう!