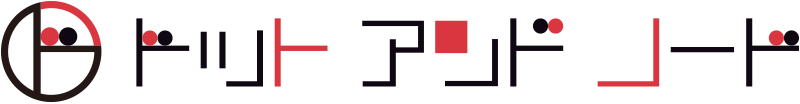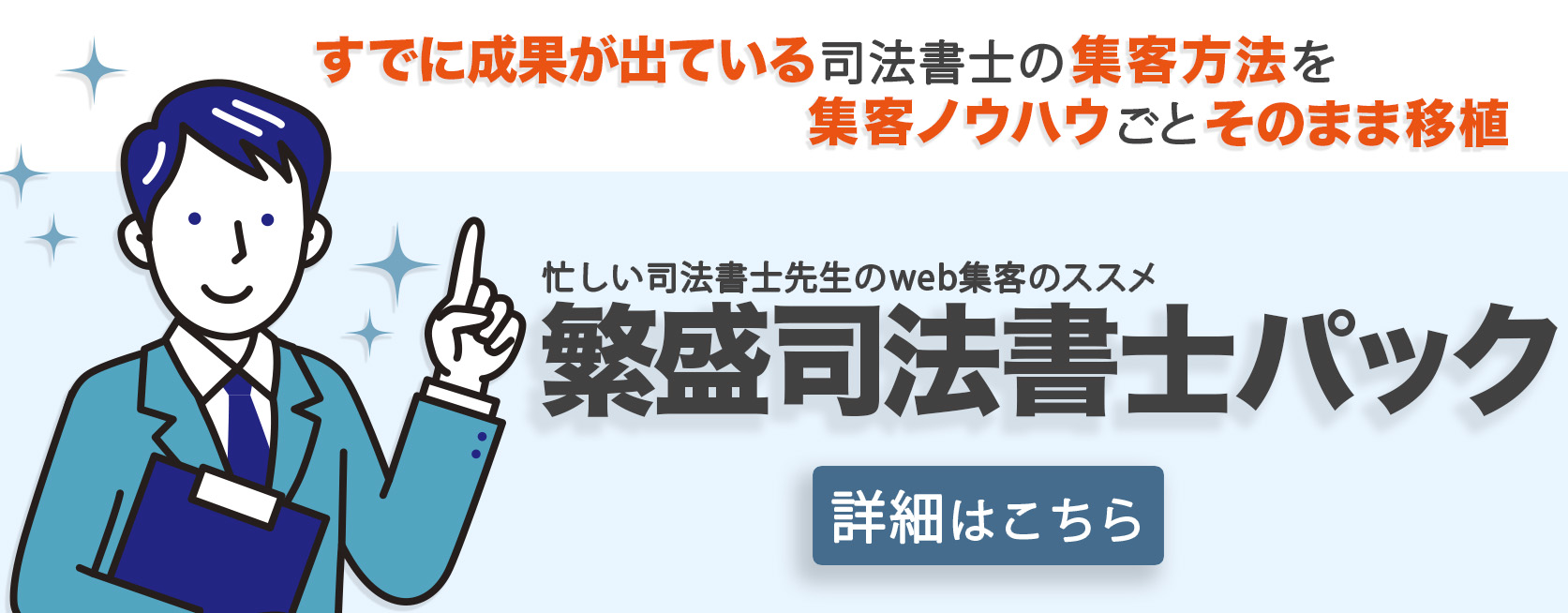電子書籍を販売したい司法書士は必見!メリットや流れ、注意点まとめ
近年、自身の実績や専門分野を伝えるだけでなく、読者から「この先生なら安心して任せられそう」と信頼を得るきっかけにもなることから、「本を出版してみたい」と思う司法書士が増えています。
出版といっても、今の時代は紙の本ではなく、Amazon Kindleなどの電子書籍として販売が可能なので、本に関する専門知識がなくても気軽に発信できます。
ただし、出版にあたっては原稿を電子書籍用の形式に整える必要があり、EPUBやPDFなどのファイル変換、出版プラットフォームへの登録作業などが必要になります。
慣れていない方にとっては多少の手間を感じるかもしれません。
しかし、近年はテンプレートや変換ツールも整備されてきており、充分対応可能です。
とはいえ、いざ取り組もうとすると「何を書けばいいのか」「どんな流れで販売するのか」といった疑問が尽きないでしょう。
この記事では、司法書士として電子書籍を出版するメリットから、テーマ選びや販売するまでの進め方などを、分かりやすく解説します。
司法書士が電子書籍を販売するメリット
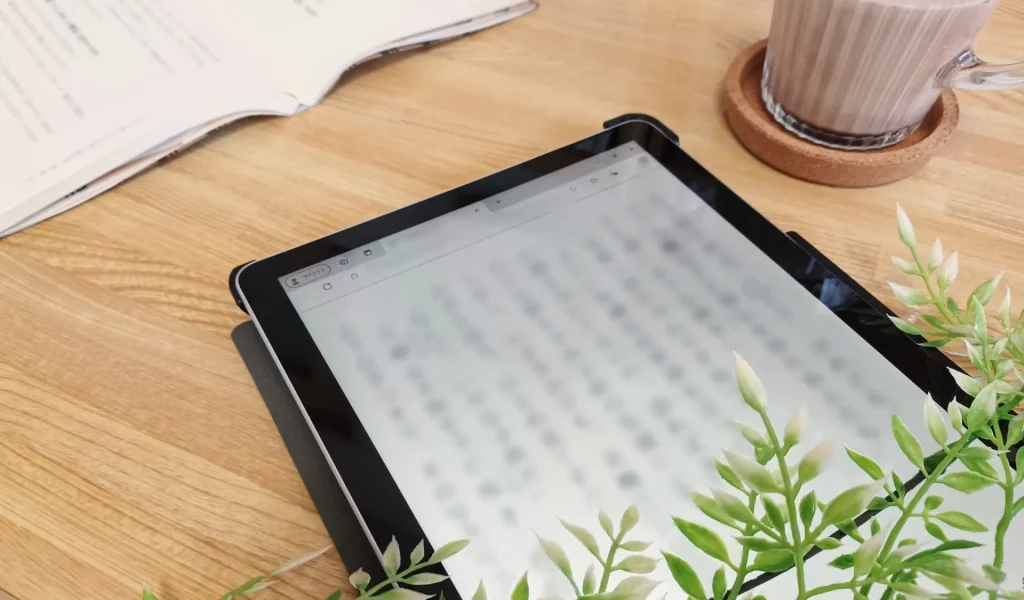
現代では誰もが気軽に電子書籍を出版できるようになりましたが、司法書士も取り組むべきなのでしょうか?
司法書士が電子書籍を販売するメリットは、次の通りです。
- 知名度アップや新規顧客の獲得に役立つ
- 新たな収入源を確保できる
- 専門性をアピールしてブランディングできる
以下では、電子書籍を出すことによる具体的な利点について解説します。
知名度アップや新規顧客の獲得に役立つ
電子書籍を出版することで、司法書士自身の知名度を、飛躍的に向上させることが可能です。
インターネットを通じて不特定多数の読者にアプローチできるため、特定の地域や年代などに限定されずに幅広い層の目に留まるでしょう。
また、読者が抱える具体的な悩みに応える内容の書籍を制作すれば、潜在的な顧客が司法書士へ信頼感を抱くきっかけとなります。
たとえば「遺産分割の具体的な手順がわからない」「成年後見制度の申立方法が難しい」など、実務上よく寄せられる悩みに応える内容であれば、読者にとって実用的な書籍となりやすいのです。
電子書籍が多くの人に読まれることで「集客の入り口」となり、知名度アップや新規の顧客獲得へとつながる可能性が高まります。
新たな収入源を確保できる
電子書籍の販売は、司法書士業務とは異なる新たな収入源を確保できます。
一度出版すれば、継続的に印税収入を得られる可能性があるので、時間や場所に縛られることなく収益を上げられます。
また、多く売れれば売れるほど印税が入るため、万が一、本業の司法書士としての売上が伸び悩んでも食いつなげるでしょう。
業務の繁忙期・閑散期に左右されずに、司法書士業務以外の収益の柱を持ちたい場合、電子書籍の出版は意味のある選択肢といえます。
専門性をアピールしてブランディングできる
電子書籍は、司法書士の専門性を明確にアピールし、他士業との差別化を図れる強力なブランディングツールとなります。
相続・登記・成年後見人など、自身の得意分野に特化した内容の書籍を出版することで、その分野の専門家としての地位を確立できます。
電子書籍の内容が分かりやすくて質が高ければ、司法書士の知識や経験の深さを読者に伝えられるため、「この分野ならこの先生」という強い信頼性を得られるかもしれません。
その結果、ブランディングが確立されて報酬の高い案件の受注や、特定の分野での講演依頼などにもつながることが期待できるでしょう。
司法書士が電子書籍を出版するまでの流れ
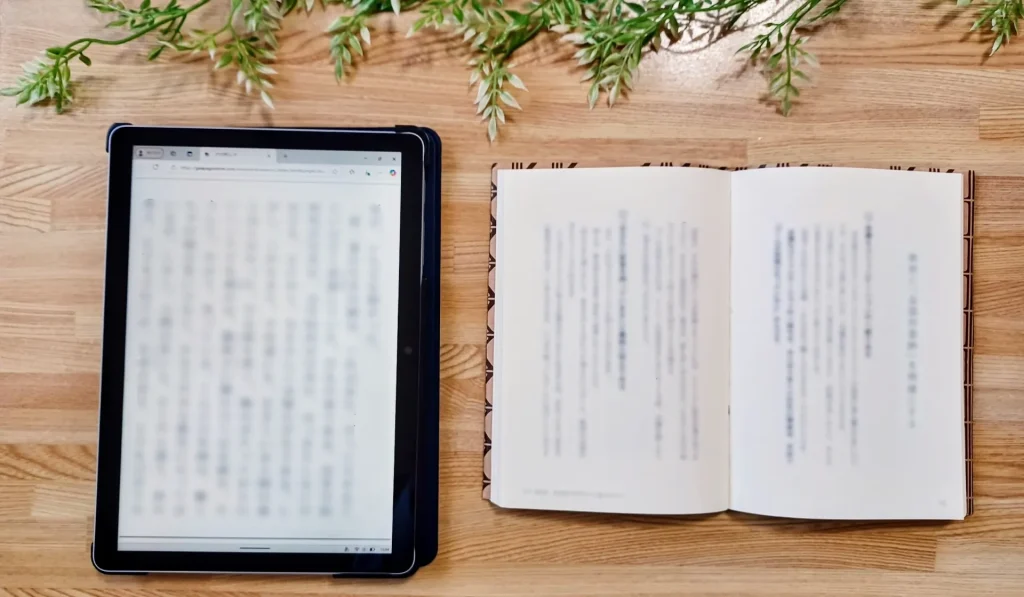
いざ司法書士が電子書籍を出版しようと思っても、どのような流れになるのかイメージが湧かない方は少なくないでしょう。
電子書籍を出版するまでの流れは、以下の通りです。
- 企画の立案
- 執筆
- 表紙やレイアウトのデザイン
- 出版プラットフォームの選定
- 価格設定
- 販売・プロモーション
ここからは、それぞれの手順について具体的に解説するので、詳しく見ていきましょう。
1.企画の立案
「個人向けか、事業者向けか」「どんな悩みを解決したいか」など、具体的なターゲット読者を設定します。
司法書士自身の得意分野や需要のある分野など、書籍のテーマや題材を選定しましょう。
司法書士に向いているテーマとして、次のような例が挙げられます。
- 相続手続きの流れと準備(戸籍や預金の扱い方など)
- 不動産登記の基本とよくある質問
- 成年後見制度のしくみと使い方
- 借金問題の解決方法(任意整理や自己破産)
- 会社設立時の登記と必要書類
- 離婚にともなう財産分与の手続き など
こうしたテーマは、日常的に依頼件数の多い業務領域でもあります。
Google検索でも「相続手続き 流れ」「不動産 登記」などのキーワードで月間1,000回以上検索されているなど、読者からの関心も高い分野です。
企画の段階で書籍の骨子や目次を作成したり、読者が行動に移せるためのゴールを設計したりするなど、全体の構成を明確にしておくと、その後の執筆作業が円滑に進められます。
2.執筆
企画が固まったら、次に執筆作業に入ります。
読者ターゲットに合わせて、専門用語の解説を加えたり、具体的な事例を盛り込んだりして、分かりやすく実用的な内容を心がけましょう。
表現は読者に寄り添いつつも、専門家としての信頼性を損なわないよう、丁寧かつ論理的な文章を意識することが大切です。
また、誤字脱字や語句の誤用がないかなど、校正もしっかり行いましょう。
3.表紙やレイアウトのデザイン
商業出版の場合はプロのデザイナーが担当するので、「水色を基調としたい」「イラストや図解を多用したい」など大まかな要望で問題ありません。
自分でデザインするなら、オンラインで使える無料のグラフィックデザインツールであるCanva(キャンバ)で作成する方法があります。
また、自分をデフォルメしたキャラクターを使うと、専門書のような堅い印象が薄まり、専門知識がない人でも読みやすくなるでしょう。
反対にイラストやキャラクターが一切ないと、堅実性や真面目さが演出でき、同業や事業者向けに仕上げられます。
なお、出版プラットフォームによりEPUB(イーパブ)やPDFといった電子書籍に合う形式に変換する必要があります。
4.出版プラットフォームの選定
出版プラットフォームには、Amazon Kindle・楽天Kobo・Apple Booksなどが挙げられます。
それぞれの特徴や手数料、対応している形式などを比較し、自身の出版目的やターゲット層に最適なプラットフォームを選びましょう。
また、販売手数料やデザイナー費などをかけたくない場合は、有料販売やメンバーシップなどの形式で販売できるnoteがおすすめです。
もし司法書士事務所の公式Webサイトでも電子書籍を販売したいなら、購入への導線を確保してください。
5.価格設定
出版プラットフォームの販売手数料は、一般的に売上の30%〜65%程度なので、それを踏まえて販売価格を設定します。
多くの人に読んでもらいたいなら1,000円代〜2,000円代と安価で、専門性が高く特定の読者に読んでもらいたいなら3,000円代〜4,000円代と高めの価格での販売がおすすめです。
類似書籍の価格帯や自身の専門性、情報量などを考慮したうえで決定してください。
さらに、期間限定の割引セールや無料キャンペーンを活用することで、購買意欲を喚起し、読者数やレビュー数を増やす効果が見込めます。
6.販売・プロモーション
ただ電子書籍を出版しただけでは、読者の目に触れる機会は限られてしまうので、積極的にプロモーションすることが大切です。
WebサイトやSNS、ブログやメルマガなどで電子書籍を出版した旨を告知し、少しでも販売数を伸ばしましょう。
予約限定で特典をつけたり、数量限定で無料配布したりするなどのキャンペーンを実施するのもおすすめです。
電子書籍の中に「ご相談はこちら」とSNSのQRコードやWebサイトのURLを載せたり、事務所のメール署名や名刺にも電子書籍の販売ページへのリンクを入れたりすると、問い合わせ件数や販売部数の増加が期待できます。
司法書士が電子書籍を販売するときの注意点

いくら誰もが電子書籍を販売できるようになったとはいえ、司法書士が出版するときには守らなければならない注意点が存在します。
読者が正しい知識を得られるように、また法に抵触しないように、以下の注意点を踏まえたうえで電子書籍を出版しましょう。
- 最新の法律情報を正確に記載できているか気をつける
- 著作権や個人情報保護への違反に注意する
- 印税収入が出たら必ず確定申告する
とくに著作権法や個人情報保護法など、出版時に遵守すべき具体的な法律に基づいて内容を確認することが重要です。
以下では、司法書士が電子書籍を販売する際に、特に気をつけるべきポイントについて紹介します。
最新の法律情報を正確に記載できているか気をつける
法律情報の正確性と最新性は必ずチェックし、原稿が仕上がったらすべての文章を校閲してください。
「法律を誤って解釈している」「最新の法改正の情報が載っていない」といった問題が発覚すると、読者からの信頼が失われて集客に結びつかなったり、既存の顧客が離れたりする恐れがあります。
電子書籍を執筆中に法改正や判例の変更があるかもしれないので、常に最新の情報に目を光らせ、速やかに内容を更新できるように心がけましょう。
著作権や個人情報保護への違反に注意する
著作権法第32条に基づき、著作物の引用は「公正な慣行に合致すること」「報道・批評・研究などの正当な範囲であること」「本文と引用部分の主従関係が明確であること」などの条件を満たす必要があります。
(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。引用元:著作権法 第32条
また、実例を紹介する場合は、個人が特定されないように一部内容をぼかして掲載しましょう。
著作権法や個人情報保護法に違反しないよう、法的リスクに充分に注意しながら執筆します。
印税収入が出たら必ず確定申告する
出版した電子書籍が売れて印税収入が生まれたら、必ず確定申告してください。
なお、電子書籍の印税は「事業所得」ではなく「雑所得」として申告するケースが多くなります。
ただし、継続的かつ反復的に出版・販売を行っている場合は「事業所得」として扱われる可能性もあるため、状況に応じた判断が必要です。
なお、出版社との打ち合わせや取材などで使った交通費、執筆のために購入した資料や文献の費用などは経費として計上できるので、確定申告で記載し忘れないように気をつけましょう。
もし不明な点があれば、税理士や会計事務所などの専門家に相談し、適切な税務処理を行ってください。
司法書士が電子書籍を販売するときのよくある質問
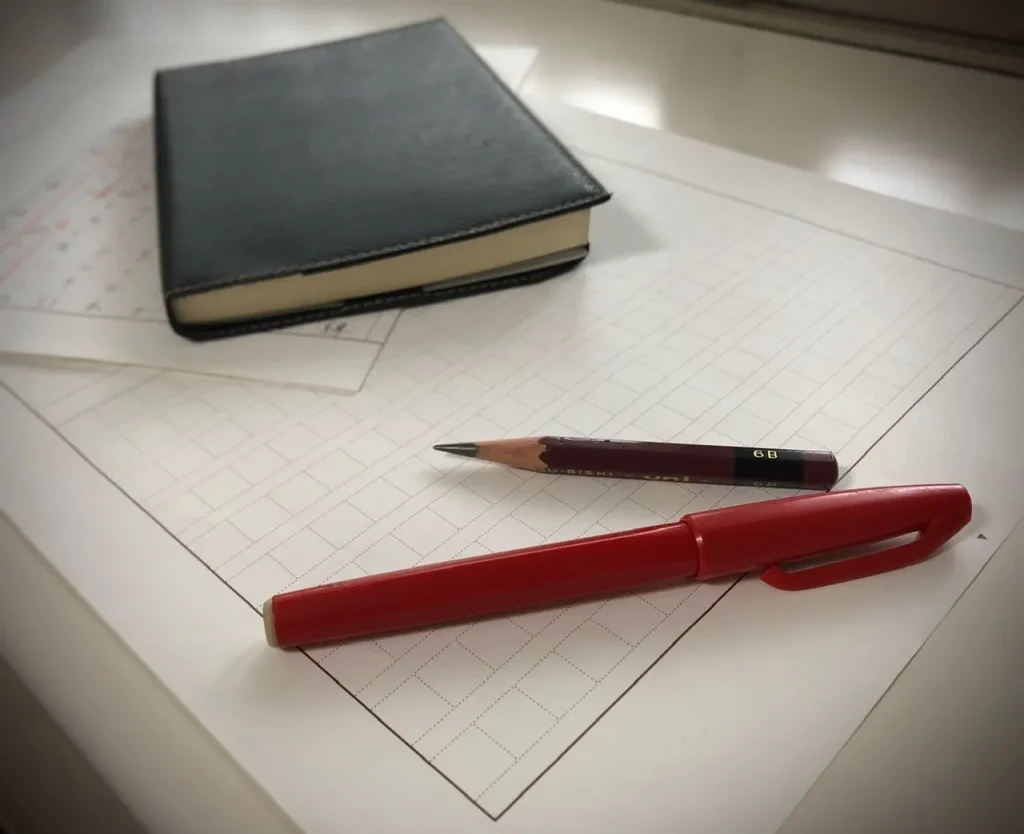
司法書士が電子書籍を販売するときに生まれやすい疑問や不安について解説します。
よくある質問として紹介するので、気になるものがあれば必ずチェックしてください。
電子書籍と併せて紙でも出版するべきですか?
出版科学研究所『出版指標 2025年冬号』によれば、2024年の出版市場全体では、紙と電子を合算した規模が1兆5,716億円と、前年比で1.5%の減少でしたが、内訳を見ると紙が5.2%減少する一方、電子は5.8%の増加となっています。
一方、株式会社ナイルが2024年に実施した「電子書籍サービスに関する調査」によると、電子書籍サービスを「現在利用している」と回答した人は20代が52.9%と半数以上に至りましたが、60代は26.3%しかいません。
そのため、60代以上の高齢者層には紙媒体を併用することで接触機会を広げると効果的です。
幅広い年齢層をターゲットにする場合は、電子と紙の両方で展開するのが望ましいでしょう。
このように、電子媒体の伸長が出版市場を下支えしており、両者を併売することで世代や読者層の幅を広げる戦略が必要といえます。
ターゲットによっては紙媒体を併用することで接触機会を増やし、信頼性や保存性を重視する層のニーズにも応えられるでしょう。
電子書籍出版にかかる費用はどれくらいですか?
Amazon Kindleで展開されているKindle Direct Publishing(KDP)という出版サービスを利用すると、初期費用は無料です。
KDPでは、ロイヤリティを「35%」または「70%」から選択可能。
70%のロイヤリティを受け取るには、著作権が保護されているオリジナル作品であり、指定された国・地域の読者向けに販売すること、かつ希望小売価格が印刷版の価格より少なくとも20%低いことなど、複数の条件を満たす必要があります。
また、日本・ブラジル・インド・メキシコ向けの70%ロイヤリティ適用には「KDPセレクト」への登録が必須です。
条件を満たさない場合は35%ロイヤリティが適用されます。
ロイヤリティは、販売価格から配信コスト(1冊あたり平均0.06ドル)を差し引いた金額に対して計算されるため、収益の見積もりにはこの点も考慮しましょう。
一方、デザイナー費用は5,000円〜30,000円程度が、電子書籍フォーマットへの変換費用は5,000円〜15,000円程度が相場です。
なお、電子書籍の出版代行の相場は1冊あたり20万円〜30万円ほどとなるため、プロの技術を借りるとなると、それなりの費用がかかると考えましょう。
電子書籍の印税はいくらくらいですか?
電子書籍の印税は、通常の紙の書籍よりも高く、30〜70%程度になることが多いです。
ただし、出版社と契約すると電子書籍の印税率は大きく異なり、10〜20%という低めの率で設定されている場合もあります。
司法書士が電子書籍をより多く販売したいならドットアンドノードへご相談ください
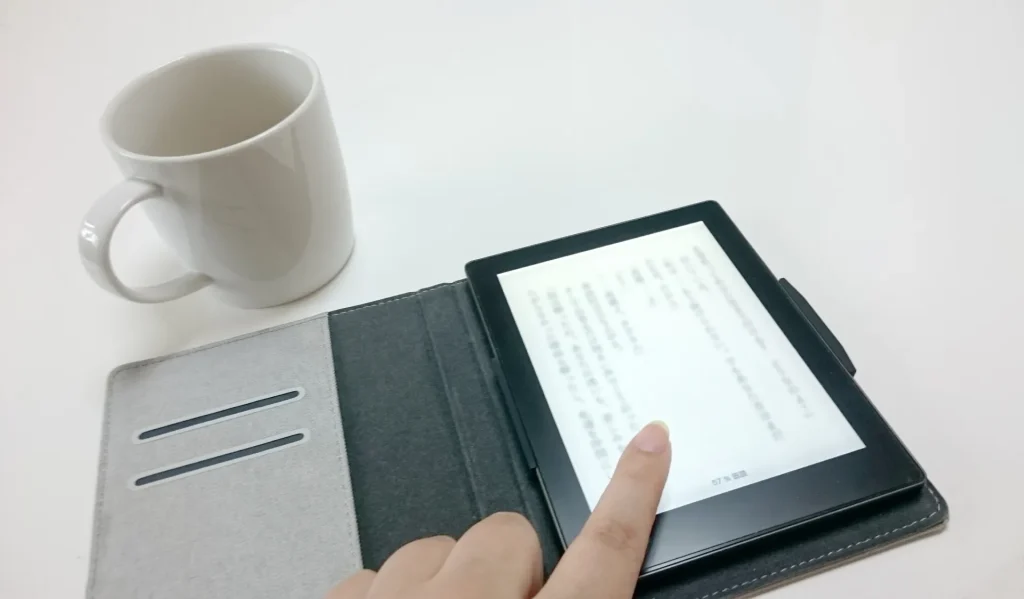
今回は、司法書士の電子書籍について解説しました。
電子書籍は、司法書士自身の知名度向上や新たな収入源の確保、専門性をアピールしたブランディングにつながる有力なツールです。
実務で培われた豊富な知識と経験を活かし、読者のニーズに応える質の高い電子書籍を出版することで、集客に効果的といえるでしょう。
もし「電子書籍をより多くの方に向けて販売したい」「電子書籍をきっかけに集客に力を入れたい」という方は、ドットアンドノードにご相談ください。
ドットアンドノードでは、司法書士専門のWeb集客サービスである「繁盛司法書士パック」をご用意しております。
費用を抑えつつ、毎月のWeb広告運用や地域特性に合わせた広告の調整などに対応いたしますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。