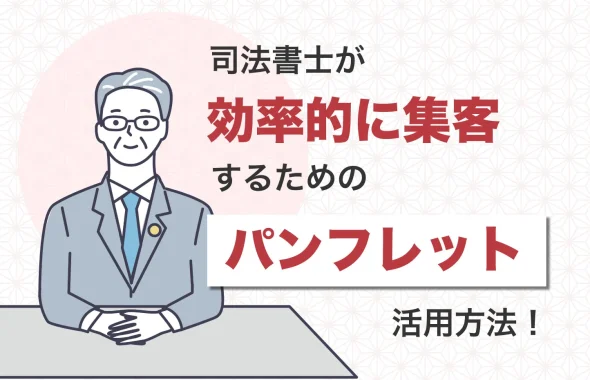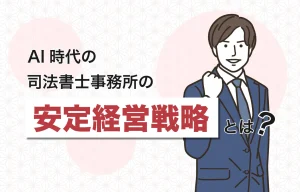司法書士はAIとどう向き合う?事務所の課題を解決するAI活用術
「AIの進化によって、10年後も司法書士として生き残れるのだろうか」
「毎日、書類の作成とチェック作業だけで一日が終わってしまう」
そのように感じている司法書士の方は、決して少なくありません。
不動産登記や商業登記、相続手続きなど、司法書士は社会に欠かせない業務を担っています。
しかし、登記や相続といった業務の大部分は、膨大な量の書類作成や判例リサーチといった定型的な作業に時間が費やされているのが現状です。
特に複雑な登記申請書の作成や、戸籍謄本の読み込みといった作業は細心の注意が求められるため、司法書士の生産性を左右する大きな要因となっています。
多くの司法書士事務所では、依然として手作業による定型業務に時間を取られて、本来注力すべき顧客への丁寧なヒアリングやより複雑なコンサルティング業務の時間を圧迫しています。
そこで注目されているのが、AIを活用した業務の効率化です。
AIは定型業務や人為的なミスを減らして、司法書士がより付加価値の高い仕事へ集中するための時間を生み出すパートナーになり得ます。
本記事では、司法書士が抱える悩みをAIでどのように解決できるのか、具体的な活用方法から明日から試せる活用事例、失敗しないための導入の進め方までわかりやすく解説します。
AIは司法書士の仕事を奪う?未来の働き方を解説

結論からお伝えすると、AIが司法書士の仕事を完全に奪うことはありません。
AIは仕事を奪う「脅威」ではなく、むしろ司法書士の専門的な価値を高める「パートナー」となり得る存在です。
確かにAIは、書類作成やリサーチといった定型業務を効率化する強力なツールです。
しかし、AIにはできないことも明確に存在します。
AIにできないこととして、次の3つが挙げられます。
- 顧客一人ひとりの複雑な事情や感情を汲み取ること
- 最終的な法的判断を下し、結果に対して責任を負うこと
- 依頼者との信頼関係を築き、柔軟な対応をおこなうこと
特に、AIに最終的な判断を委ねることには危険が伴います。
なぜなら、AIには「ハルシネーション(事実にもとづかない情報をあたかも真実であるかのように生成する現象)」という、もっともらしい嘘をつくリスクがあるからです。
総務省が公表した「令和6年版 情報通信白書」においても、「AIは誤情報を生成する可能性があるため、利用者は出力された内容が正しいか、検索などで確認することが望ましい」と注意を促しています。
生成AIは事実に基づかない誤った情報をもっともらしく生成することがあり、これをハルシネーション(幻覚)と呼ぶ。技術的な対策が検討されているものの完全に抑制できるものではないため、生成AIを活用する際には、ハルシネーションが起こる可能性を念頭に置き、検索を併用するなど、ユーザーは生成AIの出力した答えが正しいかどうかを確認することが望ましい。
引用元:総務省「令和6年版 情報通信白書|生成AIが抱える課題」
AIの回答を鵜呑みにすれば、誤った情報によって顧客が被害を受けることになり、専門家としての信頼を失いかねません。
司法書士は、AIを単純作業のアシスタントとして活用することで、定型業務から解放されるでしょう。
その結果、人間にしかできない高度なコンサルティングや依頼者との対話に注力できるようになり、司法書士としての専門性をより一層高めていくことができるのです。
司法書士の業務でAIを使う5つのメリット

AIを司法書士の業務に導入すると、単なる業務効率化にとどまらず、以下のようなメリットが期待できます。
- 書類作成と確認作業の自動化でミスを減らす
- 法令と判例リサーチを短時間でおこない業務の法的根拠を強化する
- AIチャットボットで24時間365日の問い合わせ窓口を設置する
- 複雑な案件の進捗状況をAIで見える化し情報共有の漏れを防ぐ
- AIによる相続関係説明図の自動作成で業務負担を減らす
ここからは、AIが司法書士の業務にもたらす5つの具体的なメリットをそれぞれ詳しくご紹介します。
書類作成と確認作業の自動化でミスを減らす
司法書士の業務では、登記申請書や契約書といった、正確性が求められる書類を数多く扱います。
AIを活用すれば、こうした定型的な書類のたたき台を短時間で作成することが可能です。
AIは過去のデータやテンプレートをもとに、必要項目を自動で文章化します。
さらに、完成した書類のチェック作業もAIが得意とする分野です。
誤字脱字や条文番号のズレなど、人が何度も確認しても見落としがちな細かなミスを、AIが自動で検出します。
司法書士は、人の目とAIのチェックを組み合わせることでヒューマンエラーを大幅に減らして、書類の正確性をこれまで以上に高められるのです。
法令と判例リサーチを短時間でおこない業務の法的根拠を強化する
業務の法的根拠を明らかにするための法令や判例のリサーチには、膨大な時間がかかるのが現状です。
AIを導入すると、リサーチ業務を大幅に効率化できます。
たとえば、キーワードを入力するだけで、膨大なデータベースの中からAIが関連性の高い法令や判例を瞬時に探し出してくれます。
これまで数時間を要していたリサーチ作業が、AIを使えばわずか数分で完了するケースも少なくありません。
AIが多角的な視点から情報を示すため、司法書士は人の目だけでは見つけにくかった判例を発見しやすくなります。
その結果、司法書士はより強固な法的根拠にもとづいて、業務の質を一層高めることができるでしょう。
AIチャットボットで24時間365日の問い合わせ窓口を設置する
司法書士事務所のウェブサイトにAIチャットボットを設置することで、営業時間を問わず、見込み客からの問い合わせに対応できます。
たとえば、以下のような活用が可能です。
- 相続手続きの流れや費用の目安など、よくある質問に自動で回答する
- 初回相談の予約をチャットボット上で受け付ける
- 問い合わせ内容に応じて、担当者に自動で通知する
AIチャットボットが一次対応を担うことで、司法書士事務所はこれまで対応が難しかった夜間や休日の問い合わせも確実に受け付けられます。
そのため、新規の顧客も獲得しやすくなります。
また、日中の電話対応の負担が減るため、スタッフは本来集中すべき業務に多くの時間を割けるようになるでしょう。
複雑な案件の進捗状況をAIで見える化し情報共有の漏れを防ぐ
複数のタスクが複雑に絡み合う案件では、担当者間の情報共有が欠かせません。
AIが導入された管理ツールを使えば、案件ごとのタスクや期限、進捗状況を自動で整理して、関係者全員がリアルタイムで確認できる環境を整えられます。
たとえば、あるタスクが完了した際に、AIが次の担当者へ自動で通知を送るように設定することもできます。
AIによる進捗状況の可視化によって案件全体の進行がスムーズになり、より質の高いサービスの提供が実現できるのです。
AIによる相続関係説明図の自動作成で業務負担を減らす
相続案件では、戸籍謄本を読み解いて、手作業で相続関係説明図を作成することが司法書士にとって大きな負担になりがちです。
最近では、戸籍謄本から相続関係説明図を作成するような、時間のかかる手作業をAIで自動化する技術が登場しています。
AI-OCR(光学的文字認識)技術で戸籍謄本の情報を読み取り、AIが相続関係を自動で整理して相関図を生成するのです。
この技術を活用することで、司法書士は相続関係説明図の作成にかかる手間を大幅に軽減し、最終的な確認作業に集中できるようになります。
さらに、自動作成された正確な相関図を使って顧客へスムーズに説明できる点も、大きなメリットと言えるでしょう。
司法書士がAIを導入するうえで注意すべきデメリット

AIの導入は、定型業務にかかる時間や人件費の削減、人為的なミスの防止など、多くのメリットをもたらします。
AIの活用によって、司法書士は、顧客へのコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
一見するとAI活用はメリットばかりに見えるかもしれません。
しかし、メリットの裏には司法書士として見過ごせない、以下のようなデメリットも存在します。
- 学習データに起因する情報の不正確さ
- 最新の法改正に対応できない可能性
- もっともらしい嘘を生成するリスク
AIは学習データが最新でなかったり、ハルシネーションという事実にもとづかない情報を生成してしまったりする危険性を抱えています。
そのため、最近の法改正などを正確に反映できない可能性も指摘されています。
もし誤った情報や古い情報に基づいて業務を進めてしまえば、依頼者に深刻な損害を与えかねません。
AIが提示した情報を鵜呑みにせず、最終的な判断と責任は、司法書士としての専門家である人間が負わなければなりません。
AIはあくまで業務を補助する「アシスタント」と位置付け、回答が本当に正しいのか、さまざまな角度から確認することが大切です。
司法書士が明日からできるAI活用事例5選

AIは業務効率化において、とても役立つツールといえます。
しかし、依頼者との信頼関係を築きながら業務を進めることは、司法書士にしかできません。
司法書士が明日からできるAI活用事例には、以下のようなものがあります。
- 文章生成AIで登記書類のたたき台づくりや要約をおこなう
- リサーチ特化型AIで判例や法令調査の時間を大幅に短縮する
- AI-OCRツールで紙の戸籍謄本などをすぐにデータ化する
- AIチャットボット作成ツールでウェブサイトの集客力を向上させる
- リーガルテックで法律関連業務を効率化する
ここでは、司法書士事務所の課題に合わせてすぐに取り組める、5つの活用事例をそれぞれ詳しく解説します。
文章生成AIで登記書類のたたき台づくりや要約をおこなう
「ChatGPT」や「Gemini」といった文章生成AIは、登記申請書や契約書など定型的な書類のたたき台を作成する際に役立つツールです。
司法書士は、過去のひな形や必要な要素をAIに指示することで、たたき台を短時間で作成することが可能です。
また、文章生成AIは難解な長文の判例や参考資料の要点をまとめさせることにも活用できます。
AIに内容を要約させれば、資料を読み解く時間を大幅に短縮することが可能です。
その結果、司法書士はより迅速に判断できるようになります。
ただし、AIが生成した文章は必ず司法書士自身の目で確認して、適切な修正を加えてから使用することが大前提です。
リサーチ特化型AIで判例や法令調査の時間を大幅に短縮する
判例や法令の調査には、専門のAIツールが効果的です。
たとえば、「Legalscape」のようなリーガルリサーチに特化したAIツールを使えば、キーワードを入力するだけで、膨大な量のデータベースから関連性の高い法令や判例、書籍の情報を瞬時にリストアップしてくれます。
多くのツールは最新の法改正情報と紐づけて検索できるため、調査の網羅性と正確性が向上します。
AIツールがリサーチ業務を効率化することで、司法書士はリサーチに費やしていた時間を大幅に減らして、より深い分析や検討に時間を充てられるのです。
AI-OCRツールで紙の戸籍謄本などをすぐにデータ化する
相続案件などで扱う、手書き文字の多い戸籍謄本や本人確認書類の整理は、手間のかかる作業です。
「DX Suite」に代表されるAI-OCRツールを活用すれば、手書き文字の多い紙の書類をカメラで撮影するだけで、高精度にテキストデータへ変換できます。
AI-OCRツールは、以下のような点で業務を効率化します。
- 面倒な手入力作業から解放される
- 入力ミスや転記ミスといったヒューマンエラーを防げる
- データ化することで、所内での情報共有が容易になる
データ化によって検索性が向上するため、司法書士は過去の案件資料を瞬時に探し出せるようになり、さらなる業務効率化が期待できます。
AIチャットボット作成ツールでウェブサイトの集客力を向上させる
事務所のウェブサイトは、新規の依頼につながる大切な入り口です。
「ChatPlus」のようなAIチャットボット作成ツールを使えば、プログラミングの知識がなくても、ウェブサイトに問い合わせ窓口を簡単に設置できます。
AIチャットボットが24時間365日、よくある質問への回答や、初回相談の予約受付といった一次対応を自動でおこないます。
AIチャットボットの活用で、日中の電話負担を減らしつつ、営業時間外の見込み客も将来の集客につなげられます。
リーガルテックで法律関連業務を効率化する
最近では、司法書士の業務に応用できる、最新の法律関連テクノロジー(リーガルテック)も次々と登場しています。
たとえば、「LegalForce」や「GVA assist」といったAI契約書レビュー支援サービスは、契約書に潜むリスクをAIが自動で検知し、修正案を提示してくれるツールです。
こうした法律関連業務を効率化するAIツールは現在、弁護士業務での活用が中心です。
しかし、このようなAI技術の動向を知っておくことは、司法書士にとっても将来の業務改善のヒントになります。
常に新しい技術へアンテナを張っておくことで、他の司法書士事務所に先駆けて、より効率的で質の高いサービスを提供する体制を整えることにつながります。
司法書士事務所のAI導入を成功させる5つのポイント

AIツールの導入で失敗しないためには、以下の重要なポイントを押さえることが大切です。
- なぜ導入するのか目的とゴールを明確に決める
- まずは無料ツールからスモールスタートで試す
- 司法書士の守秘義務を守るセキュリティ対策を徹底する
- 事務所全体で目的とメリットを共有してチームで取り組む
- 導入後の効果を測定して継続的に改善していく
ここでは、AI導入の失敗リスクを大幅に減らすための5つの重要なポイントをそれぞれ詳しく解説します。
なぜ導入するのか目的とゴールを明確に決める
AI導入を成功させる最初のステップは、目的とゴールを明確にすることです。
「流行っているから」「他の司法書士事務所も使っているから」といった漠然とした理由で導入すると、効果を実感できずに形骸化してしまうことになりかねません。
まずは「どの業務の、どの課題を解決したいのか」を具体的に定義することが重要です。
たとえば、「登記申請書の作成にかかる時間を今よりも半減させたい」といった具体的な数値目標を設定することが効果的です。
こうした具体的なゴールを設定することで導入すべきAIツールが明確になり、効果を測定する際の重要な基準となります。
まずは無料ツールからスモールスタートで試す
AI導入を検討する際、いきなり高額な有料ツールを契約する必要はありません。
まずはコストをかけずに「ChatGPT」の無料プランなどを活用して、AIがどのようなものか試してみる「スモールスタート」をおすすめします。
最初は一部の定型的な業務や特定の担当者だけで、試験的に導入してみましょう。
スモールスタートで試すことで、AIが本当に効果的なのか、またどのような課題があるのかをリスクを抑えつつ検証できます。
そこで得られた気づきをもとにして、必要であれば本格的な導入や有料ツールへ移行すれば、大きな失敗を防げます。
司法書士の守秘義務を守るセキュリティ対策を徹底する
司法書士にとって、個人情報を適切に管理して守秘義務を守ることは、最も基本的な義務です。
クラウド上で提供されるAIサービスに顧客情報をそのまま入力することは、情報漏洩のリスクを伴います。
AIを安全に利用するためには、以下のようなセキュリティ対策を徹底することが大切です。
- 利用するAIツールのプライバシーポリシーや利用規約を必ず確認する
- 氏名や住所といった個人情報をAIに入力しない
- 氏名などを「売主」「買主」といった役割名に置き換えるなど、個人が特定できないように質問を工夫する
こうしたひと手間をかけることが司法書士としての信頼を守り、安心してAIを活用するための大前提となります。
事務所全体で目的とメリットを共有してチームで取り組む
AIの導入が一部のスタッフだけの取り組みで終わってしまっては、AIの効果を最大限に引き出すことはできません。
「なぜAIを導入するのか」という目的や「導入によってどのようなメリットが生まれるのか」を、スタッフ全員で共有することが大切です。
簡単な勉強会や成功体験の共有などを通じてスタッフがAI活用へ取り組めるよう、雰囲気を作ることが大切です。
AI活用の目的を理解してチーム一丸となって取り組むことによって、AIは司法書士にとってより強力なツールとなります。
導入後の効果を測定して継続的に改善していく
AIは「導入して終わり」のツールではありません。
最初に設定した「書類作成の時間を半減させる」といった目標を達成できているか、定期的に効果を測定することが大切です。
もし期待した効果が出ていない場合は、効果が出ない原因を探る必要があります。
ツールの使い方が適切でないのか、あるいはそもそもAIを適用する業務の選定が間違っていたのか、一つひとつ検証して運用方法を見直すことが大切です。
計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Act)を繰り返す「PDCAサイクル」を回し続けることで、AIは司法書士にとって本当に役立つツールになっていくのです。
司法書士がAI導入で失敗しないためによくある疑問点

AIの導入を検討するにあたり、多くの司法書士の方が以下のような疑問を抱えています。
- AIの導入費用はどのくらいかかるのか?
- 顧客情報をAIに入力しても守秘義務は守れるのか?
- AIで生まれた時間やコストをどう活用すれば他の事務所との差別化になるのか?
ここでは、こうした疑問点について一つずつ解説します。
AIの導入費用はどのくらいかかるのか?
AIツールの導入費用は、目的や種類によって大きく異なります。
文章生成AIであれば、月額数千円から利用できるものも少なくありません。
一方で、専門的な業務管理システムはより高額になることもあります。
大切なのは導入費用そのものではなく、AIで削減できる業務時間や人件費と比較した「費用対効果」で判断することです。
AIを導入するときは、かけた費用に見合う効果が期待できるか、という視点で検討することが重要です。
顧客情報をAIに入力しても守秘義務は守れるのか?
司法書士にとって、守秘義務を負うことは絶対です。
しかし、適切な対策をすればAI利用のリスクは大幅に減らせます。
前提として、入力したデータをAIの学習に利用させない「オプトアウト」機能を持つツールを選ぶことが重要です。
そのうえで、顧客情報を入力する際は、氏名や住所といった個人情報を直接使わず「当事者A」「売主」のように匿名化することを徹底しましょう。
司法書士として守秘義務を遵守するのであれば、AIのリスクを正しく理解して、適切な対策をとらなければなりません。
AIで生まれた時間やコストをどう活用すれば他の事務所との差別化になるのか?
今後、多くの事務所がAIを導入すれば、業務効率化だけでは他の事務所との差別化は難しくなります。
そもそも業務効率化は目的ではなく、新たな価値を生み出すための第一歩です。
AI活用で生まれた時間や費用を、専門的なコンサルティングや顧客への丁寧な対応にあてることが重要です。
そうした戦略の一つとして「ウェブサイトを通じた新規顧客の獲得」が挙げられます。
たとえば、司法書士業界に特化したウェブ集客を手がける専門のサービスも存在し、事業のサポートをしてくれます。
AI活用後のWeb集客で悩む司法書士はドットアンドノードへ

本記事では、AIは司法書士の仕事を奪うものではなく、業務を効率化してくれる心強いパートナーであることを解説しました。
しかし、業務効率化だけでは、今後も依頼者から選ばれ続ける司法書士にはなれません。
AIの活用で生まれた時間やコストを、司法書士の今後の成長にどうつなげるかが重要です。
AI活用における効果的な戦略の一つが、司法書士事務所の強みをウェブサイトで発信して、新たな依頼者とつながるきっかけを作る「ウェブ集客」です。
「AI導入後の展開に悩んでいる」「ウェブ集客に自信がない」といったお悩みは、司法書士業界に特化したウェブ集客を専門とするドットアンドノードが解決をお手伝いします。
弊社では、以下のようなお悩みを持つ方をサポートしております。
- AIを導入して、業務効率化の先を見据えている方
- ウェブサイトからの問い合わせを増やして、新規の依頼者を獲得したい方
- 他の事務所との差別化を図り、独自の強みを確立したい方
AIを活用してウェブからの安定した集客を目指したい司法書士の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
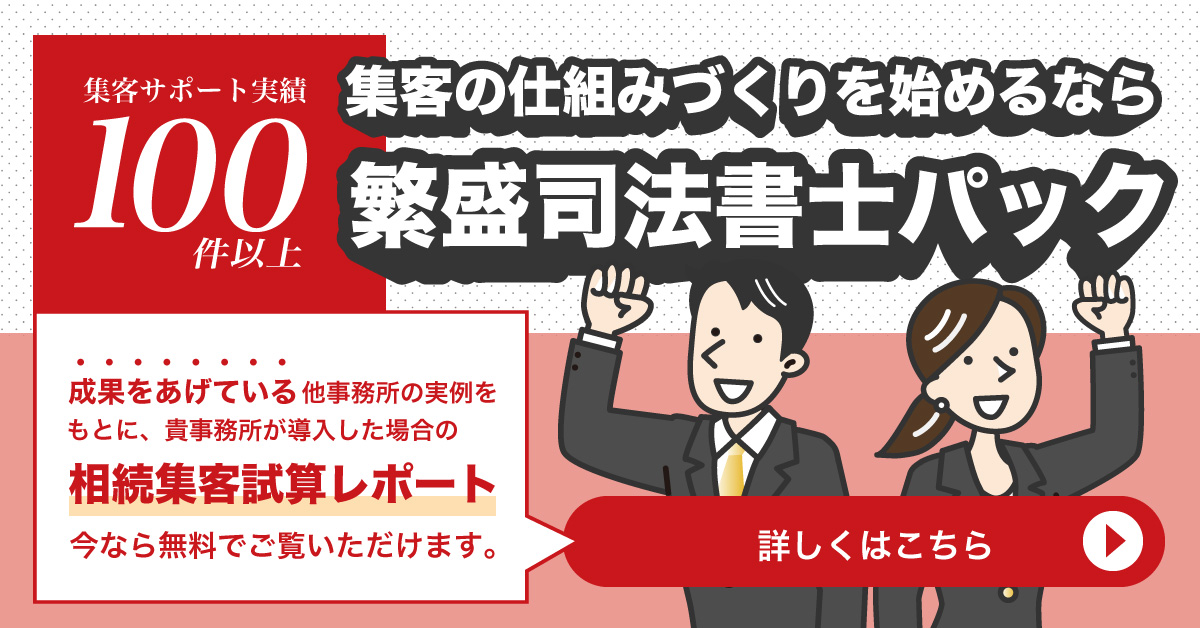
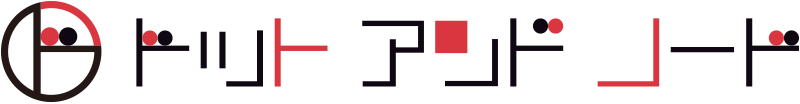

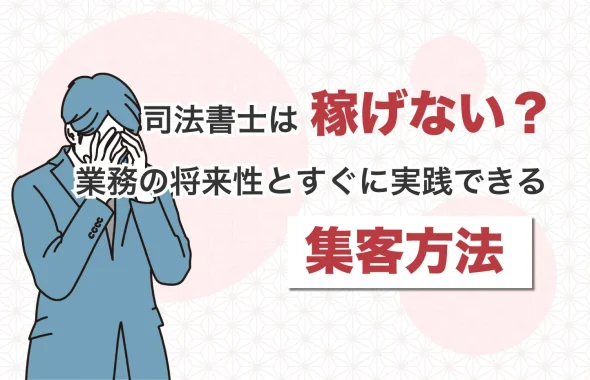
で集客するには?効果的な活用方法とWeb集客成功のポイントを解説-590x380.jpg)